特別企画 ラズパイで作る簡単VPN環境
p.48の『ユーザー名の「pi」を入力して[Enter]キーを押します。』の後に『「Password:」が表示されたら、パスワードの「raspberry」を入力して[Enter]キーを押します。』が抜けていました。お詫びして訂正いたします。
情報は随時更新致します。
test
著者:増田 嶺
前回に引き続き、SLPで開発したリズムゲームを紹介します。前回はゲームで使用する譜面作成ツールについて解説しました。今回は、ゲーム本体について解説します。ゲーム本体は「Visual Studio Code」(VSCode)で開発します。
図5 「js/game/singleNote.js」ファイルに記述するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { this.height = note.height; this.width = note.width; this.frameColor = 'rgb(' + note.frameColor + ')'; // 枠の色 this.bodyColor = 'rgba(' + note.bodyColor + ')'; // 中の色 this.this.centerY = -this.height; // ノーツ中心のY座標 this.speed = speed * note.speedRatio; // px/ms // ゲーム開始から判定ラインに到達するまでの時間 this.reachTime = reachTime + note.delay; // canvasに入る時間 this.appearTime = this.reachTime - (JUDGE_LINE.centerY + this.height / 2) / this.speed; // canvasから出る時間 this.hideTime = this.reachTime + (CANVAS_H - JUDGE_LINE.centerY + this.height / 2) / this.speed; this.act = true; // 自身がヒット処理対象かどうか this.show = false; // 自身がcanvasに描画されるかどうか } } |
図6 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 |
(略) generateNote(data) { this.note = data.map((val) => new SingleNote(val[2], val[3])); } (略) |
図7 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { (略) } draw(x) { if (this.show) { this.centerY = JUDGE_LINE.centerY - (this.reachTime - time.elapsed) * this.speed; CTX.fillStyle = this.bodyColor; CTX.fillRect(x, this.centerY - this.height / 2, this.width, this.height); CTX.strokeStyle = this.frameColor; CTX.strokeRect( x + LINE_WIDTH / 2, this.centerY - this.height / 2 + LINE_WIDTH / 2, this.width - LINE_WIDTH, this.height - LINE_WIDTH ); } } } |
図8 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 |
(略) drawNote() { this.note.forEach(val => val.draw(this.x)); } (略) |
図9 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
class SingleNote { constructor(speed, reachTime) { (略) } draw(x) { (略) } update() { this.updateShow(); } updateShow() { if (this.act || this.show) { if (this.appearTime <= time.elapsed && time.elapsed <= this.hideTime) { this.show = true; } else { this.show = false; } } } } |
図11 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 |
(略) update() { this.note.forEach(val => val.update()); } (略) |
図13 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
(略) judge() { calcElapsedTime(); // 経過時間を更新 // ヒットしているノーツを抽出 const TARGET = this.note.filter(val => val.checkHit(note.hitRange[3])); // TARGETの先頭から処理、先頭ノーツのグレードがBadだった場合のみ // 二つ目以降のノーツを処理し、それらのノーツがBadだった場合は中断 const GRADE = [3] for (let i = 0; TARGET[i] && GRADE[0] === 3; i++) { GRADE[i] = TARGET[i].getGrade(); // 二つ目以降のノーツがBadの場合はそこで中断 if (i > 0 && GRADE[i] === 3) { break; } JUDGE_LINE.setGrade(GRADE[i]); // ノーツヒットのグレードを描画 TARGET[i].close(); // 判定済みのノーツ処理を停止 } } (略) |
図15 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
class SingleNote { (略) updateShow() { (略) } checkHit(range) { if (this.act && Math.abs(time.elapsed - this.reachTime) <= range) { return true; } else { return false; } } getGrade() { let grade = 3; for (let i = 2; i >= 0; i--) { if (this.checkHit(note.hitRange[i])) { grade = i; } } return grade; } } |
図16 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
class SingleNote { (略) update() { this.updateShow(); if (!this.act) { return; } // 判定ラインから自身の判定ゾーンが // 過ぎた時点で処理 if (this.reachTime < time.elapsed && !this.checkHit(note.hitRange[3])) { JUDGE_LINE.setGrade(3); this.act = false; } } (略) close() { this.act = false; this.show = false; } } |
図18 「js/game/gameScoreManager.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
(略) calcScore(grade) { switch (grade) { case 0: this.point += 100 + this.combo; this.perfect++; this.combo++; break; case 1: this.point += 80 + this.combo * 0.8; this.great++; this.combo++; break; case 2: this.point += 50 + this.combo * 0.5; this.good++; this.combo++; break; case 3: this.bad++; this.combo = 0; break; } if (this.maxCombo < this.combo) { this.maxCombo = this.combo; } } (略) |
図19 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
(略) judge() { (略) if (GRADE[i] < 3) { // Bad以外の判定ならヒットSEを鳴らす sound.playSE(sound.seList[0]); } else { sound.playSE(sound.seList[1]); // Bad判定ならバッドSEを鳴らす } gameScore.calcScore(GRADE[i]); // スコアを更新 JUDGE_LINE.setGrade(GRADE[i]); // ノーツヒットのグレードを描画 TARGET[i].close(); // 判定済みのノーツ処理を停止 } } (略) |
図20 「js/game/singleNote.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
class SingleNote { (略) update() { (略) if (this.reachTime < time.elapsed && !this.checkHit(note.hitRange[3])) { gameScore.calcScore(3); JUDGE_LINE.setGrade(3); this.act = false; } } (略) } |
図22 「js/game/backLane.js」ファイルに追加するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
(略) draw() { (略) if (inputKey.status[this.key]) { const GRAD = CTX.createLinearGradient(this.x, JUDGE_LINE.centerY, this.x, CANVAS_H / 3); GRAD.addColorStop(0.0, 'rgba(' + this.actColor + ', 0.6)'); GRAD.addColorStop(1.0, 'rgba(' + this.actColor + ', 0)'); CTX.fillStyle = GRAD; CTX.fillRect(this.x, 0, this.width, JUDGE_LINE.centerY); } } (略) |
著者:飯尾 淳
本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第4回は、フラクタル図形の一種である「ヒルベルト曲線」を描く方法を解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図1 1次のヒルベルト曲線を描くPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 p = [[-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5]] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() for x in p: goto(screen_pos(x)) mainloop() |
図4 1 次のヒルベルト曲線を描くPythonコードの改良版
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 penup_flag = True p = [[-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5]] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() penup() for x in p: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |
図7 2 次のヒルベルト曲線を描くPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
#!/usr/bin/env python from turtle import * SIZE = 300 penup_flag = True tm = [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] e = [ [ 1.0, 0.0, 0.0], [0.0, 1.0, 0.0], [0.0, 0.0, 1.0] ] p = [ [-0.5, 0.5], [-0.5, -0.5], [0.5, -0.5], [0.5, 0.5] ] def affine_transform(m, p): return [ m[0][0] * p[0] + m[0][1] * p[1] + m[0][2], m[1][0] * p[0] + m[1][1] * p[1] + m[1][2] ] def mat_mul(m0, m1): return [ [m0[0][0]*m1[0][0]+m0[0][1]*m1[1][0]+m0[0][2]*m1[2][0], m0[0][0]*m1[0][1]+m0[0][1]*m1[1][1]+m0[0][2]*m1[2][1], m0[0][0]*m1[0][2]+m0[0][1]*m1[1][2]+m0[0][2]*m1[2][2]], [m0[1][0]*m1[0][0]+m0[1][1]*m1[1][0]+m0[1][2]*m1[2][0], m0[1][0]*m1[0][1]+m0[1][1]*m1[1][1]+m0[1][2]*m1[2][1], m0[1][0]*m1[0][2]+m0[1][1]*m1[1][2]+m0[1][2]*m1[2][2]], [m0[2][0]*m1[0][0]+m0[2][1]*m1[1][0]+m0[2][2]*m1[2][0], m0[2][0]*m1[0][1]+m0[2][1]*m1[1][1]+m0[2][2]*m1[2][1], m0[2][0]*m1[0][2]+m0[2][1]*m1[1][2]+m0[2][2]*m1[2][2]] ] def screen_pos(x): return (x[0]*SIZE, x[1]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red') width(5) hideturtle() penup() for m in tm: p2 = [ affine_transform(mat_mul(e, m), x) for x in p ] for x in p2: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |
図9 書き換えた2 次のヒルベルト曲線を描くPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
#!/usr/bin/env python from turtle import * import numpy as np SIZE = 300 penup_flag = True tm = [ np.matrix(x) for x in [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] ] e = np.eye(3) # 3次の単位行列 p = [ np.matrix(x).T for x in [ [-0.5, 0.5, 1.0], [-0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, 0.5, 1.0] ] ] def screen_pos(x): return (x[0,0]*SIZE, x[1,0]*SIZE) setup(width = 2*SIZE, height = 2*SIZE) color('red', 'yellow') width(5) hideturtle() penup() for m in tm: for x in [ e * m * x for x in p ]: goto(screen_pos(x)) if penup_flag: pendown() penup_flag = False onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |
図10 図9 の赤枠部分を置き換えるPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
def hilbert(n, m): if n > 1: for m_tm in tm: hilbert(n-1, m * m_tm) else: for x in [ m * x.T for x in p ]: goto(screen_pos(x)) global penup_flag if penup_flag: pendown() penup_flag = False hilbert(3, e) |
図13 1 ~ 7 次のヒルベルト曲線を重ねて描画するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
#!/usr/bin/env python from turtle import * import numpy as np SIZE = 300 MARGIN = 50 penup_flag = True settings = [ { 'color': 'forestgreen', 'width': 5 }, { 'color': 'navy', 'width': 4 }, { 'color': 'purple', 'width': 3 }, { 'color': 'brown', 'width': 2 }, { 'color': 'red', 'width': 2 }, { 'color': 'orange', 'width': 1 }, { 'color': 'yellowgreen', 'width': 1 } ] tm = [ np.matrix(x) for x in [ [ [0.0, -0.5, -0.5], [-0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, -0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.5, 0.0, 0.5], [ 0.0, 0.5, -0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ], [ [0.0, 0.5, 0.5], [ 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.0, 1.0] ] ] ] e = np.eye(3) p = [ np.matrix(x).T for x in [ [-0.5, 0.5, 1.0], [-0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, -0.5, 1.0], [ 0.5, 0.5, 1.0] ] ] def draw_line_to(x): goto(x[0,0]*SIZE, x[1,0]*SIZE) global penup_flag if penup_flag: pendown() penup_flag = False def reset(): penup() global penup_flag penup_flag = True def hilbert(n, m): if n > 1: for m_ in tm: hilbert(n-1, m * m_) else: for q in [ m * p_ for p_ in p ]: draw_line_to(q) setup(width = 2*SIZE+MARGIN, height = 2*SIZE+MARGIN) hideturtle() for i in range(len(settings)): reset() color(settings[i]['color'], 'white') width(settings[i]['width']) hilbert(i+1, e) onkey(exit, 'q') listen() mainloop() |
著者:川嶋 宏彰
本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。今回は、入力から予測値を出力する「回帰モデル」と、その教師あり学習について紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図5 気温に対するチョコレート菓子支出金額の散布図をプロットするPython コード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import japanize_matplotlib # pip install japanize-matplotlibが必要 import re plt.rcParams['font.size'] = 14 # 家計調査データの読み込み beg_col = 5 # 品目の始まる列 end_col = 6 # 品目の終わる列 usecols = [3] + list(range(beg_col, end_col + 1)) # 用いる列リスト # 年月の列をインデックスとするデータフレームに df_estat = pd.read_csv('estat.csv', header=0, encoding='cp932', usecols=usecols, index_col=0, parse_dates=True, date_parser=lambda x: pd.to_datetime(x, format='%Y年%m月')) # 各品目の支出金額を各月の日数で割る(★) for col in df_estat: new_col = re.sub(r'.* (.*)【円】', r'\1 (円/日)', col) df_estat[new_col] = df_estat[col] / df_estat.index.days_in_month # 気象庁の気温データの読み込み df_jma = pd.read_csv('jma.csv', skiprows=5, header=None, encoding='cp932', usecols=[0, 1], index_col=0, parse_dates=True) hitemp_col = '平均最高気温 (℃)' # 気温の列名を変える df_jma.columns = [hitemp_col] # データフレームの結合 df = pd.merge(df_estat, df_jma, left_index=True, right_index=True) df.index.name = 'y/m' # インデックスの名前を変更 # 年と月の列を追加(後で利用) df['year'] = df_estat.index.year df['month'] = df_estat.index.month print('df (merged):\n', df) # 散布図をプロット target_col = 'チョコレート菓子 (円/日)' df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.show() |
図7 チョコレート菓子支出金額の単回帰の結果を示すPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
from sklearn.linear_model import LinearRegression reg = LinearRegression() # モデルを準備 # データを準備 X = df[[hitemp_col]].values # 平均最高気温(2次元配列)。「.values」は省略可 y = df[target_col].values # 支出金額(1次元配列)。「.values」は省略可 reg.fit(X, y) # 学習(データに直線を当てはめる) print('intercept:', reg.intercept_) # 切片 print('coef:', reg.coef_[0]) # 直線の傾き print('R2:', reg.score(X, y)) # 決定係数 df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.plot(X, reg.predict(X), 'r') plt.show() |
図10 チョコレート菓子支出金額の単回帰における残差をプロットする
Pythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 |
fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.scatter(X, y - reg.predict(X)) # 残差をプロット plt.axhline(y=0, c='r', linestyle='-') # 水平線をプロット plt.ylim([-3, 3]) plt.xlabel(hitemp_col) plt.ylabel('残差') plt.show() |
図13 年を説明変数とした単回帰のためのPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
from matplotlib import cm from matplotlib.colors import ListedColormap def ListedGradation(cmapname, num=10): """ LinearSegmentedColormap から ListedColormap を作成 """ color_list = [] cmap = cm.get_cmap(cmapname) for i in range(num): color = list(cmap(i/num)) color_list.append(color) return ListedColormap(color_list) # 年ごとに散布図の色を変える df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, c=df['year'], cmap=ListedGradation('cividis', 11), sharex=False, figsize=(6, 5)) plt.show() # 「年」を説明変数とする単回帰 reg_year = LinearRegression() X = df[['year']].values # 年 y = df[target_col].values # 支出金額 reg_year.fit(X, y) # 学習(データに直線を当てはめる) print('intercept:', reg_year.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_year.coef_[0]) # 直線の傾き print('R2:', reg_year.score(X, y)) # 決定係数 df.plot(kind='scatter', x='year', y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.plot(X[:, 0], reg_year.predict(X), 'r') plt.show() |
図15 平均最高気温と年の二つを説明変数とした重回帰のためのPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D import numpy as np reg_multi = LinearRegression() X = df[[hitemp_col, 'year']].values # 二つの説明変数(2次元配列) y = df[target_col].values # 支出金額(1次元配列) reg_multi.fit(X, y) # 学習(データに平面を当てはめる) print('intercept:', reg_multi.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_multi.coef_) # 平面の傾き print('R2:', reg_multi.score(X, y)) # 決定係数 # 3次元散布図のプロット def scatter3d(X, y, xlabels, ylabel): fig = plt.figure(figsize=(9, 6)) ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], y) ax.set_xlabel(xlabels[0]) ax.set_ylabel(xlabels[1]) ax.set_zlabel(ylabel) ax.view_init(elev=30, azim=-60) return ax scatter3d(X, y, [hitemp_col, '年'], target_col) plt.show() # 平面(wireframe)を合わせてプロット ax = scatter3d(X, y, [hitemp_col, '年'], target_col) xlim = ax.get_xlim() ylim = ax.get_ylim() mesh_x = np.meshgrid(np.arange(*xlim, (xlim[1] - xlim[0]) / 20), np.arange(*ylim, (ylim[1] - ylim[0]) / 20)) mesh_y = reg_multi.intercept_ + reg_multi.coef_[0] * mesh_x[0] \ + reg_multi.coef_[1] * mesh_x[1] # 回帰式より予測 ax.plot_wireframe(*mesh_x, mesh_y, color='r', linewidth=0.5) plt.show() |
図18 平均最高気温と年の二つを説明変数とした重回帰の残差をプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 |
fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.scatter(X[:, 0], y - reg_multi.predict(X)) # 残差をプロット plt.axhline(y=0, c='r', linestyle='-') # 水平線をプロット plt.ylim([-3, 3])plt.xlabel(hitemp_col) plt.ylabel('残差') plt.show() |
図20 平均最高気温とアイスクリーム支出金額の散布図をプロットするPythonコード
|
1 2 3 |
target_col = 'アイスクリーム・シャーベット (円/日)' # 目的変数を変える df.plot(kind='scatter', x=hitemp_col, y=target_col, figsize=(5, 5)) plt.show() |
図22 多項式回帰モデルを使ったPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures from sklearn.linear_model import Ridge def poly_fit(df, xlabel, ylabel, degree=2, ylim=None): """ 多項式回帰 """ y = df[ylabel] pf = PolynomialFeatures(degree=degree, include_bias=False) Xpf = pf.fit_transform(df[[xlabel]]) reg_pf = LinearRegression(normalize=True) # reg_pf = Ridge(normalize=True, alpha=0.01) # (★) reg_pf.fit(Xpf, y) print('intercept:', reg_pf.intercept_) # 切片 print('coef:', reg_pf.coef_) # 直線の傾き print('R2:', reg_pf.score(Xpf, y)) # 決定係数 fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) plt.plot(X, y, '.', ms=8) plt.ylim(ylim) plt.xlabel(xlabel) plt.ylabel(ylabel) # x軸に等間隔に点を配置して回帰曲線を描く xlim = plt.xlim() X_lin = np.arange(*xlim, (xlim[1] - xlim[0])/50).reshape(-1, 1) Xpf_lin = pf.fit_transform(X_lin) ypf_pred = reg_pf.predict(Xpf_lin) plt.plot(X_lin, ypf_pred, color='r') X = df[[hitemp_col]].values # 平均最高気温 y = df[target_col].values # 支出金額 for p in [1, 2, 3, 20]: # 多項式の次数 poly_fit(df, hitemp_col, target_col, degree=p) plt.title(f'p = {p}') plt.show() |
著者:米田 聡
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第7回は、ボリュームスイッチのような操作を実現する拡張基板を扱います。
シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 サンプルプログラム(sample.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
import smbus import struct import time ADRSZRE_ADDR = 0x54 VALUE_HI = 0x00 RESET = 0x02 STEPS = 80 # 1回転=80カウント bus = smbus.SMBus(1) degree = 0.0 try: while True: temp = bus.read_word_data(ADRSZRE_ADDR, VALUE_HI) value = struct.unpack(">H", struct.pack("<H", temp))[0] if value == 0: bus.write_byte_data(ADRSZRE_ADDR, RESET, True) # Zero Reset degree = (value % STEPS) * 360.0 / STEPS print("%.1f" % degree, end='\r', flush=True) time.sleep(0.1) except KeyboardInterrupt: pass |
著者:麻生 二郎
小型コンピュータボードの最上位モデルである「Raspberry Pi 4 Model B」の4G/8Gバイト版と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」のサーバー版を組み合わせて、本格的なサーバーを構築しましょう。本特集では、テレワークに役立つサーバーアプリの導入方法を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.74は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図11 Sambaをインストールして実行するシェルスクリプト(samba_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
#!/bin/sh ##初期設定 WORKGROUP_NAME="SHMAG" SHARE_NAME="share" SHARE_FOLDER="/var/share" ##Sambaのインストール sudo apt update sudo apt -y install samba ##旧設定バックアップ mkdir -p ~/old_settings sudo mv /etc/samba/smb.conf ~/old_settings/. ##Sambaの共有設定 cat << EOF | sudo tee /etc/samba/smb.conf > /dev/null [global] workgroup = workgroup_name dos charset = CP932 unix charset = UTF8 [share_name] comment = Raspberry Pi share path = share_folder browsable = yes writable = yes create mask = 0777 directory mask = 0777 EOF sudo sed -i -e "s%workgroup_name%'$WORKGROUP_NAME'%" /etc/samba/smb.conf sudo sed -i -e "s%share_name%'$SHARE_NAME'%" /etc/samba/smb.conf sudo sed -i -e "s%share_folder%'$SHARE_FOLDER'%" /etc/samba/smb.conf ##共有フォルダ作成 sudo mkdir -p $SHARE_FOLDER sudo chmod 777 $SHARE_FOLDER ##Sambaの設定反映 sudo systemctl restart smbd sudo systemctl restart nmbd |
図14 MediaWikiを導入するシェルスクリプト(mediawiki_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" ##必要なパッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install mediawiki imagemagick ##データベースの作成 sudo mysql -e "create database my_wiki;" sudo mysql -e "create user 'mediawiki'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on my_wiki.* to 'mediawiki'@'%';" |
図25 ownCloudをインストールするシェルスクリプト(owncloud_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |
#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" ADMIN_NAME="admin" ADMIN_PASSWORD="admin" OWNCLOUD_FILE="owncloud-10.8.0.tar.bz2" ##ヘルパースクリプト「occ」の作成 cat << EOM | sudo tee /usr/local/bin/occ #! /bin/bash cd /var/www/owncloud sudo -E -u www-data /usr/bin/php /var/www/owncloud/occ "\$@" EOM sudo chmod +x /usr/local/bin/occ ##必要・推奨パッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install apache2 libapache2-mod-php mysql-server php-imagick php-common php-curl php-gd php-imap php-intl php-json php-mbstring php-mysql php-ssh2 php-xml php-zip php-apcu php-redis redis-server sudo apt -y install jq inetutils-ping ##ownCloudの設定ファイル作成 sudo sed -i "s%html%owncloud%" /etc/apache2/sites-available/000-default.conf cat << EOM | sudo tee /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf Alias /owncloud "/var/www/owncloud/" <Directory /var/www/owncloud/> Options +FollowSymlinks AllowOverride All <IfModule mod_dav.c> Dav off </IfModule> SetEnv HOME /var/www/owncloud SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud </Directory> EOM ##Apache HTTP Serverの設定 sudo a2ensite owncloud.conf sudo a2enmod dir env headers mime rewrite setenvif sudo systemctl restart apache2 ##ownCloudの入手と展開 wget https://download.owncloud.org/community/$OWNCLOUD_FILE tar -jxf $OWNCLOUD_FILE sudo mv owncloud /var/www/. sudo chown -R www-data /var/www/owncloud ##データベースの作成 sudo mysql -e "create database owncloud;" sudo mysql -e "create user 'owncloud'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on owncloud.* to 'owncloud'@'%';" ##ownCloudのインストール echo "しばらくおまちください。" occ maintenance:install --database "mysql" --database-name "owncloud" --database-user "owncloud" --database-pass $DB_PASSWORD --admin-user "$ADMIN_NAME" --admin-pass "$ADMIN_PASSWORD" myip=$(hostname -I|cut -f1 -d ' ') occ config:system:set trusted_domains 1 --value="$myip" ##バックグラウンド処理の設定 occ background:cron sudo sh -c 'echo "*/15 * * * * /var/www/owncloud/occ system:cron" > /var/spool/cron/crontabs/www-data' sudo chown www-data.crontab /var/spool/cron/crontabs/www-data sudo chmod 0600 /var/spool/cron/crontabs/www-data ##キャッシュとロックファイルの作成 occ config:system:set memcache.local --value '\OC\Memcache\APCu' occ config:system:set memcache.locking --value '\OC\Memcache\Redis' occ config:system:set redis --value '{"host": "127.0.0.1", "port": "6379"}' --type json ##ログローテーションの設定 cat << EOM | sudo tee /etc/logrotate.d/owncloud /var/www/owncloud/data/owncloud.log { size 10M rotate 12 copytruncate missingok compress compresscmd /bin/gzip } EOM |
図29 RainLoopをインストールするシェルスクリプト(rainloop_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
#!/bin/sh ##初期設定 SIZE="100M" DB_PASSWORD="admin" ##必要なパッケージの導入 sudo apt update sudo apt -y install apache2 php php-curl php-xml php-mysql mysql-server unzip ##RainLoop Webmailの導入 wget https://www.rainloop.net/repository/webmail/rainloop-community-latest.zip sudo mkdir -p /var/www/html/rainloop sudo unzip rainloop-community-latest.zip -d /var/www/html/rainloop/. sudo chown -R www-data /var/www/html/rainloop cat << EOF | sudo tee /etc/apache2/sites-available/rainloop.conf >> /dev/null <Directory /var/www/html/rainloop/data> Require all denied </Directory> EOF sudo a2ensite rainloop ##連絡先データベースの作成とApacheに反映 sudo mysql -e "create database rainloop;" sudo mysql -e "create user 'rainloop'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -e "grant all privileges on rainloop.* to 'rainloop'@'%';" ##添付ファイルサイズの拡大 sudo sed -i -e "s%upload_max_filesize = 2M%upload_max_filesize = '$SIZE'%" /etc/php/7.4/apache2/php.ini sudo sed -i -e "s%post_max_size = 8M%post_max_size = '$SIZE'%" /etc/php/7.4/apache2/php.ini sudo systemctl restart apache2 |
図36 Mattermostをインストールするシェルスクリプト(mattermost_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
#!/bin/sh ##初期設定 DB_PASSWORD="shmag" MATTERMOST="v5.39.0/mattermost-v5.39.0-linux-arm64.tar.gz" SITE_URL="http://192.168.11.100/" ##データベースの作成 sudo apt update sudo apt -y install mysql-server sudo mysql -uroot -e "create user 'mmuser'@'%' identified by '$DB_PASSWORD';" sudo mysql -uroot -e "create database mattermost;" sudo mysql -uroot -e "grant all privileges on mattermost.* to 'mmuser'@'%';" ##mattermostの入手と展開 wget https://github.com/SmartHoneybee/ubiquitous-memory/releases/download/$MATTERMOST tar -xvzf mattermost*.gz sudo mv mattermost /opt sudo mkdir /opt/mattermost/data sudo useradd --system --user-group mattermost sudo chown -R mattermost:mattermost /opt/mattermost sudo chmod -R g+w /opt/mattermost ##設定ファイルの書き換え sudo sed -i -e 's%"postgres"%"mysql"%' /opt/mattermost/config/config.json sudo sed -i -e 's%postgres://mmuser:mostest@localhost/mattermost_test?sslmode=disable\\u0026connect_timeout=10%mmuser:'$DB_PASSWORD'@tcp(localhost:3306)/mattermost?charset=utf8mb4,utf8\&writeTimeout=30s%' /opt/mattermost/config/config.json sudo sed -i -e 's%"SiteURL": "",%"SiteURL": "'$SITE_URL'",%' /opt/mattermost/config/config.json ##起動・停止ファイルの作成 cat << EOF | sudo tee /lib/systemd/system/mattermost.service > /dev/null [Unit] Description=Mattermost After=network.target After=mysql.service BindsTo=mysql.service [Service] Type=notify ExecStart=/opt/mattermost/bin/mattermost TimeoutStartSec=3600 KillMode=mixed Restart=always RestartSec=10 WorkingDirectory=/opt/mattermost User=mattermost Group=mattermost LimitNOFILE=49152 [Install] WantedBy=mysql.service EOF ##mattermostの起動と自動起動設定 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start mattermost sudo systemctl enable mattermost |
図43 MosP勤怠管理をインストールするシェルスクリプト(mosp_install.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
#!/bin/sh ##初期設定 MOSP="time4.war" ##必要なパッケージのインストール sudo apt update sudo apt -y install tomcat9 tomcat9-admin postgresql ##Mosp勤怠管理の導入 sudo chown tomcat:tomcat $MOSP sudo chmod 775 $MOSP sudo mv $MOSP /var/lib/tomcat9/webapps/. ##データベース管理者に切り替え sudo -i -u postgres ##初期設定 DBADMIN_PASSWORD="shmag" ##管理者パスワード設定 psql -c "alter role postgres with password '$DBADMIN_PASSWORD';" |
図A3 ラズパイサーバーの初期設定(ubuntu_init1.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
#!/bin/sh ##日本のタイムゾーン設定 sudo timedatectl set-timezone Asia/Tokyo ##全ソフトウエア更新 sudo apt update sudo apt -y upgrade sudo apt -y autoremove sudo apt clean ##ファームウエアアップデート sudo apt -y install rpi-eeprom sudo rpi-eeprom-update ##完了後の再起動 read -p "再起動しますか [y/N]:" YN if [ " $YN" = " y" ] || [ " $YN" = " Y" ]; then sudo reboot fi |
図A4 ラズパイサーバーの初期設定(ubuntu_init2.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
#!/bin/sh ##固定IPアドレス IP_ADDRESS="192.168.10.100" ##旧設定バックアップ mkdir -p ~/old_settings sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml ~/old_settings/. ##新ネットワーク設定作成 cat << EOF | sudo tee /etc/netplan/50-cloud-init.yaml > /dev/null network: ethernets: eth0: dhcp4: false addresses: [ip_address/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [8.8.8.8] version: 2 EOF sudo sed -i -e "s%ip_address%$IP_ADDRESS%" /etc/netplan/50-cloud-init.yaml ##ネットワーク設定反映 sudo netplan apply |
図A3 データ領域を拡張するシェルスクリプト(storage_expand.sh)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
#!/bin/sh ##パーティション作成とフォーマット sudo parted -s /dev/sda rm 1 sudo parted -s /dev/sda mklabel msdos sudo parted -s /dev/sda mkpart primary 0% 100% sudo mke2fs -t ext4 -F /dev/sda1 ##/varディレクトリに自動マウント sudo e2label /dev/sda1 usbssd sudo sh -c "echo 'LABEL=usbssd /var ext4 defaults 0 0' >> /etc/fstab" ##読み書き許可と/varディレクトリコピー sudo mount /dev/sda1 /mnt sudo chmod 777 /mnt sudo cp -a /var/* /mnt ##完了後の再起動 read -p "再起動しますか [y/N]:" YN if [ " $YN" = " y" ] || [ " $YN" = " Y" ]; then sudo reboot fi |
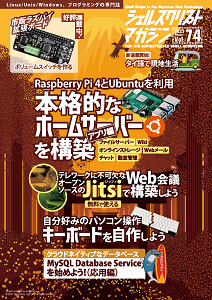
004 レポート UNIX基本コマンド集の新版
005 レポート IBMのフリー日本語ソフト
006 NEWS FLASH
008 特集1 本格的なホームサーバーを構築 アプリ編/麻生二郎 コード掲載
023 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(前編)」/シェル魔人
024 特集2 オープンソースのJitsiで構築しよう/橋本知里
034 特集3 キーボードを自作しよう/東峰沙希
044 特別企画 MDSを始めよう!(応用編)/生駒眞知子
054 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載
057 Hello Nogyo!
058 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載
068 タイ語から分かる現地生活/つぎみき
072 MySQLのチューニング/稲垣大助
080 PPAP/桑原滝弥、イケヤシロウ
082 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
086 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
088 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載
094 香川大学SLPからお届け!/増田嶺 コード掲載
102 Bash入門/大津真
110 Techパズル/gori.sh
111 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(後編)」/シェル魔人
小型コンピュータボードの最上位モデル「Raspberry Pi 4 Model B」と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」を組み合わせれば、省スペースの本格的なホームサーバーを構築できます。しかし、無料でも利用できるさまざまなクラウドサービスが存在している今、ホームサーバーで何をすればよいのでしょうか。特集1では、テレワークをテーマに自宅での職場環境を豊かにするサーバーアプリの導入方法を解説します。
特集2では、オープンソースのWeb会議システムソフト「Jitsi」(ジッツィ)を紹介しました。新型コロナ感染症拡大によりWeb会議が普及・一般化しています。これにより、Web会議の利便性が多くの人に伝わりました。ただし、Zeem MeetingsやCisco Webex Meetings、Microsoft TeamsのようなWeb会議サービスはとても便利ですが、無料で利用する場合は制限があります。有料版は、複数の会議を同時に行う場合はその数だけ契約したくてはいけません。この機会に無料で使えるJitsiの実力を体験してみてください。
特集3では、自作キーボードを扱いました。自宅でのテレワークが増えてノートパソコンにもつなげられるキーボードの需要は高まっています。市販のキーボードでもよいでしょうが、この機会に自分だけのキーボードを自作してみましょう。オリジナルキーボードならきーの設定をカスタマイズできるので、複数のキーを使った特別な操作も一つのキーで実現できます。
特別企画では、オープンソースのデータベース管理システムクラウドサービス「MySQL Database Service」(MDS)が備えるインメモリークエリーアクセラレータ「HeatWave」を紹介しました。HeatWaveならオンライン分析処理(OLAP)を高速に実行できます。MDSのトライアルアカウントでも利用できますので、ぜひ試してください。
このほかに、タイ王国独特の文化が分かる連載「タイ語から分かる現地生活」を開始しました。タイ在住の日本人が経験した、タイの不思議な文化に触れられます。現在のタイ(チェンマイ)の写真も多数掲載しています。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.74。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
著者:岩本 和真
SLPでは最近、Webブラウザで動作するリズムゲームをチームで開発しました。さまざまな曲でプレーできるように、リズムゲーム本体と並行して、ゲームで使用する譜面を作成するツールも開発しました。このツールもWebブラ
ウザで動作します。今回は、この譜面作成ツールの実装について紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 最初に実行されるコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
window.onload = async function() { const {bpm, musicL} = getMusicInfoViaElement() await getWidth(); await numberQLine(bpm, musicL); await setCanvas(); await setQLine(); await setXLine(); await update(); await draw(); await scrollBottom(); } |
図4 getMusicInfoViaElement()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 |
function getMusicInfoViaElement() { const bpm = document.getElementById('bpm').value; const musicL = document.getElementById('musicL').value; const musicBody = document.getElementById('musicBody').value; return {bpm, musicL, musicBody} } |
図5 getWidth()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
const can = document.getElementById("can2"); const ctx = can.getContext("2d"); can.setAttribute('style', 'background-color: #f6f7d7'); function getWidth() { return new Promise(function(resolve) { cst = window.getComputedStyle(can); canvasW = parseInt(cst.width); can.width = canvasW; resolve(); }) } |
図6 numberQLine()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 |
function numberQLine(bpm, musicL) { return new Promise(function(resolve) { qLineQty = Math.floor(musicL / (60 / bpm) + 1); resolve(); }) } |
図7 setCanvas()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
let qLineMargin = 80; function setCanvas() { return new Promise(function(resolve) { canvasH = qLineQty * qLineMargin; can.height = canvasH; ctx.translate(0, can.height); ctx.scale(1, -1); can.style.height = canvasH * 2.5 +'px'; resolve(); }) } |
図8 setQLine()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
function setQLine() { return new Promise(function(resolve) { for (let i = quarterLine.length; i < qLineQty; i++) { quarterLine[i] = new QuarterLine(i); } resolve(); }) } |
図9 QuarterLineクラスのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
class QuarterLine { constructor(no) { this.no = no; this.y = qLineMargin * this.no + qLineMargin / 4; } update() { this.y = qLineMargin * this.no + qLineMargin / 4; } draw() { ctx.beginPath(); ctx.strokeStyle = "#3ec1d3"; ctx.lineWidth = Q_LINE_T; ctx.moveTo(0, Math.round(this.y)); ctx.lineTo(canvasW, Math.round(this.y)); ctx.stroke(); } } |
図10 setXLine()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
function setXLine() { return new Promise(function(resolve) { for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = xLine[i].length; j < qLineQty; j++) { xLine[i][j] = []; for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k] = new XthLine(i, j, k); } } } resolve(); }) } |
図11 update()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
function update() { return new Promise(function (resolve) { // ノーツの縦の長さを更新 noteH = (qLineMargin / 9 >= Q_LINE_T || divValue == 8) ? qLineMargin / 9 : Q_LINE_T // ノーツの位置と各拍、各連符の横線の位置を更新 const laneMargin = canvasW / 5; laneSet = [laneMargin / 2, laneMargin * 1.5, laneMargin * 2.5, laneMargin * 3.5, laneMargin * 4.5]; noteW = laneMargin / 3; quarterLine.forEach((val) => val.update() ) editLane.forEach((val) => val.update() ) for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].update(); } } } resolve(); }) } |
図12 draw()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
function draw() { return new Promise(function(resolve) { ctx.clearRect(0, 0, can.width, can.height); for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].draw(); } } } for (let i = 0; i < qLineQty; i++) { quarterLine[i].draw(); } editLane.forEach((val) => val.draw()) for (let i = 0; i < 4; i++) { for (let j = 0; j < qLineQty; j++) { for (let k = 0; k < 14; k++) { xLine[i][j][k].drawNote(); } } } resolve(); }) } |
図13 draw()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 |
function scrollBottom() { return new Promise(function(resolve) { let target = document.getElementById('scroll'); target.scrollTop = target.scrollHeight; resolve(); } ) |
図14 レーン上のノーツをマウスクリックで制御するためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
let mouseDown; can.addEventListener('mousedown', async function(e) { mouseDown = true; await pos(e); await update(); await draw(); }); can.addEventListener('mouseup', function(e) { mouseDown = false; }); function pos(e) { return new Promise(function(resolve) { mouseDownX = (e.clientX - can.getBoundingClientRect().left); mouseDownY = -(e.clientY - can.getBoundingClientRect().bottom) / 2.5; resolve(); }) } |
図15 スライダ機能のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
let canScale = document.getElementById('canScale'); canScale.onchange = async function() { qLineMargin = this.value; await setCanvas(); await update(); await draw(); await scrollBottom(); } |
図16 apply()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
async function apply() { const {bpm, musicL} = getMusicInfoViaElement() await numberQLine(bpm, musicL); await setCanvas(); await setQLine(); await setXLine(); await update(); await draw(); return Promise.resolve(); } |
図17 convert()関数のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
function calcNote(jnoteValue, calced, musicBody) { return Math.round((jnoteValue+calced+musicBody*1000)*100)/100; } async function convert() { await apply(); const fileName = document.getElementById('fileName').value; const speed = document.getElementById("speed").value; const {bpm, musicL, musicBody} = getMusicInfoViaElement() const {noteValue, note32Value, note6Value} = calcNoteValue(bpm) const outInfo = Array() xLine.forEach((val1, i) => { val1.forEach((val2, j) => { val2.forEach((val3, k) => { if (val3.note) { const tmp = k < 8 ? calcNote(j*noteValue, k*note32Value, musicBody) : calcNote(j*noteValue, k%8*note6Value, musicBody) outInfo.push(Array(1, i+1, speed, tmp)) } }) }) }) createAndDownloadCsv(fileName, outInfo, bpm, musicL, musicBody); } |
筆者:川嶋 宏彰
本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。今回は「確率モデル」による機械学習である、ガウス分布を用いた教師あり学習と教師なし学習の手法を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 二つの特徴量を抽出して散布図をプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.size'] = 14 penguins = sns.load_dataset('penguins') # 取り出す特徴量 features = ['bill_depth_mm', 'body_mass_g'] # ★ # 対象とするペンギン種 target_species = ['Adelie', 'Gentoo'] # ★ # 今回用いる特徴量をクラスラベルと共に取り出す df = penguins[['species'] + features].copy() df.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 # 今回用いるペンギン種のみとする df2 = df[df['species'].isin(target_species)].copy() print(df2.shape) # (274, 3) と表示される # 種(target_species)に合わせたパレットを作成 palette = {c: sns.color_palette()[k] for k, c in enumerate(df['species'].unique()) if c in target_species} fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) sns.scatterplot(data=df2, x=features[0], y=features[1], hue='species', palette=palette) plt.show() |
図4 各クラス(ペンギン種)の体重分布をプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
import numpy as np import scipy X = df2[features].values # 各個体の2次元特徴量(行数=個体数) y = df2['species'].values # 各個体のクラスラベル prob_y = {c: np.sum(y==c)/y.size for c in target_species} # 事前確率 print('Prior:', prob_y) # 平均と分散は2次元にまとめてベクトルや行列として計算しておく mu = {c: X[y==c, :].mean(axis=0) for c in target_species} # 平均 sigma2 = {c: X[y==c, :].var(axis=0, ddof=1) for c in target_species} # 不偏分散 f_idx = 1 # 用いる特徴量のindex(これは1次元の場合) fig = plt.figure(figsize=(10, 5)) ax1 = fig.add_subplot(111) ax2 = ax1.twinx() # 右の縦軸 # ヒストグラムをプロット (体重のみ) sns.histplot(ax=ax1, x=X[:, f_idx], hue=y, palette=palette, alpha=0.2) xmin = np.min(X[:, f_idx]) xmax = np.max(X[:, f_idx]) xs = np.linspace(xmin-(xmax-xmin)/10, xmax+(xmax-xmin)/10, 100) # 等間隔に100点用意 # 確率密度関数を準備 (体重のみ) norm_dist1d = {c: scipy.stats.multivariate_normal(mu[c][f_idx], sigma2[c][f_idx]) for c in target_species} for c in target_species: # 各クラスの確率密度関数をプロット sns.lineplot(ax=ax2, x=xs, y=norm_dist1d[c].pdf(xs)*prob_y[c], hue=[c]*len(xs), palette=palette) # 各データを小さな縦線でプロット sns.rugplot(x=X[:, f_idx], hue=y, palette=palette, height=0.05) ax2.set_ylabel('Probability density') ax1.set_xlabel(features[f_idx]) plt.show() |
図6 1次元での決定境界を求めるPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 |
# 曲線の上下が変化するおおよその点を求める diff = norm_dist1d['Adelie'].pdf(xs)*prob_y['Adelie'] - norm_dist1d['Gentoo'].pdf(xs)*prob_y['Gentoo'] # 符号の変化点を見つけるために隣り合う要素の積を計算 ddiff = diff[1:] * diff[:-1] print('boundary:', xs[np.where(ddiff < 0)[0][0]]) |
図8 2次元ガウス分布とその等高線を表示するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d from matplotlib import cm # 共分散行列を求めておく Sigma = {c: np.cov(X[y==c, :].T, ddof=1) for c in target_species} def gen_2dgrid(X): """ 2次元メッシュグリッドの生成 """ d = X.shape[1] xmin = X.min(axis=0) # 各列の最小値 xmax = X.max(axis=0) # 各列の最大値 xstep = [(xmax[j]-xmin[j]) / 100 for j in range(d)] # グリッドのステップ幅 xmin = [xmin[j] - 10*xstep[j] for j in range(d)] # 少し広めに xmax = [xmax[j] + 10*xstep[j] for j in range(d)] aranges = [np.arange(xmin[j], xmax[j] + xstep[j], xstep[j]) for j in range(2)] return np.meshgrid(*aranges) # d=2のときは (x0grid, x1grid) が返る def gaussian_2dgrid(m, S, x0grid, x1grid): """ 2次元ガウス分布の密度関数の値を2次元メッシュで計算 """ gaussian = scipy.stats.multivariate_normal(m, S) return gaussian.pdf(np.c_[x0grid.ravel(), x1grid.ravel()]).reshape(x0grid.shape) c = 'Adelie' # プロットするクラスを設定 xgrid_2d = gen_2dgrid(X) # xgrid_2d: (x0grid, x1grid) のような二つ組 px_adelie = gaussian_2dgrid(mu[c], Sigma[c], *xgrid_2d) # *xgrid_2d で2引数に展開 fig = plt.figure(figsize=(8, 5)) # 3次元プロット ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') # 2次元ガウシアンの3次元的プロット cmap = cm.coolwarm # カラーマップを設定 ax.plot_surface(*xgrid_2d, px_adelie, cmap=cmap) # 等高線のプロット z_offset = -np.max(px_adelie) ax.contour(*xgrid_2d, px_adelie, zdir='z', offset=z_offset, cmap=cmap) ax.set_zlim(z_offset, ax.get_zlim()[1]) ax.view_init(elev=40, azim=-60) # 3次元プロットの表示角度の設定 plt.show() |
図10 2次元ガウス分布の等高線と元データの散布図を表示するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
def plot_ellipses(ms, Ss, pys, xgrids, xylabels=None, fig=None): """ 各クラスの確率だ円をプロット """ if fig is None: fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) # 新たに作成 else: plt.figure(fig.number) # 既存のfigureを利用 levels = None # クラス名を辞書キーから取得 for c in ms.keys() if type(ms) is dict else range(len(ms)): cs = plt.contour(*xgrids, gaussian_2dgrid(ms[c], Ss[c], *xgrids)*pys[c], cmap=cmap, levels=levels) levels = cs.levels # 二つ目以降は一つ目のlevelsを利用 # 密度(山の標高)をだ円に表示 # plt.clabel(cs, inline=True, fontsize=8) if xylabels is not None: plt.xlabel(xylabels[0]) plt.ylabel(xylabels[1]) return fig plot_ellipses(mu, Sigma, prob_y, xgrid_2d, xylabels=features) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], hue=y, palette=palette) plt.show() |
図12 2次の識別による決定境界を表示するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
from sklearn.discriminant_analysis import QuadraticDiscriminantAnalysis # plot_decision_boundary()は # 注釈のリンク先を参照して別途定義 clf_qda = QuadraticDiscriminantAnalysis() clf_qda.fit(X, y) # 学習 # 決定境界の表示 fig = plot_decision_boundary(X, y, clf_qda, features, palette) # 確率だ円の表示 plot_ellipses(mu, Sigma, prob_y, xgrid_2d, fig=fig) plt.show() |
図15 ガウス分布によるデータの生成をするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) Ngen_each = 120 # 各クラスで120個体生成する場合 # 各クラスの割合を変化させてもよい X_gen = np.vstack( [np.random.multivariate_normal(mu[c], Sigma[c], Ngen_each) for c in target_species]) y_gen = np.hstack([[c] * Ngen_each for c in target_species]) sns.scatterplot(x=X_gen[:, 0], y=X_gen[:, 1], hue=y_gen, palette=palette) plt.xlabel(features[0]) plt.ylabel(features[1]) plt.show() |
図18 混合ガウス分布によるソフトクラスタリングをするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
from sklearn.mixture import GaussianMixture from sklearn.cluster import KMeans from sklearn.preprocessing import StandardScaler k = 2 # クラスタ数(非階層的クラスタリングなので決める必要がある) use_gmm = True # Falseにするとk-meansになる if use_gmm: gmm = GaussianMixture(n_components=k, covariance_type='full') # full、diagはスケーリング無しも可(sphericalでは必要) Xu = X # GMM推定による各データのクラスタID y_pred = gmm.fit_predict(Xu) else: kmeans = KMeans(n_clusters=k) # 標準化によるスケーリング Xu = StandardScaler().fit_transform(X) # k-meansによる各データのクラスタID y_pred = kmeans.fit_predict(Xu) fig = plt.figure(figsize=(11, 5)) fig.add_subplot(121) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], color='k') plt.xlabel(features[0]) plt.ylabel(features[1]) plt.title('Unlabeled data') fig.add_subplot(122) sns.scatterplot(x=Xu[:, 0], y=Xu[:, 1], hue=y_pred, palette='bright') method_str = 'GMM' if use_gmm else 'k-means' plt.title(f'{method_str} clustering') if use_gmm: plot_ellipses(gmm.means_, gmm.covariances_, gmm.weights_, xgrid_2d, fig=fig) plt.show() |
著者:飯尾 淳
本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第3回は、Pythonの言語機能である「ジェネレータ」に親しむための活用例を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 「jugem.txt」の内容を行単位で反転して表示するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() lines = readJugemu() for l in lines: print(l.rstrip()[::-1]) |
図5 lines変数を使わないコード例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() for l in readJugemu(): print(l.rstrip()[::-1]) |
図6 ジェネレータを使用したPythonコード「reverse2.py」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: yield line for l in readJugemu(): print(l.rstrip()[::-1]) |
図7 関数readJugemu()が返すデータの種類を調べるPythonコード「test.py」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: return f.readlines() lines = readJugemu() print(type(lines)) |
図8 ジェネレータ関数readJugemu()が返すデータの種類を調べるPythonコード「test2.py」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: yield line lines = readJugemu() print(type(lines)) |
図9 ジェネレータ関数readJugemu()をfor文で使用するPythonコード「reverse3.py」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
#!/usr/bin/env python def readJugemu(): with open('jugemu.txt', 'r') as f: for line in f: print('readJugemu') yield line for l in readJugemu(): print('main: ', end='') print(l.rstrip()[::-1]) |
図11 ハノイの塔の解を求めるPythonコード「hanoi.py」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
#!/usr/bin/env python def hanoi(n, src, via, dst): if n <= 1: yield src, dst else: yield from hanoi(n-1, src, dst, via) yield src, dst yield from hanoi(n-1, via, src, dst) for src, dst in hanoi(3, 'A', 'B', 'C'): print(f'{src}->{dst}') |
図12 yield from構文を使わない場合のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
#!/usr/bin/env python def hanoi(n, src, via, dst): if n <= 1: yield src, dst else: for s, d in hanoi(n-1, src, dst, via): yield s, d yield src, dst for s, d in hanoi(n-1, via, src, dst): yield s, d for src, dst in hanoi(3, 'A', 'B', 'C'): print(f'{src}->{dst}') |
著者:麻生 二郎
新型コロナウイルス感染症対策として、日々の手洗いと検温は重要です。ただ、1人暮らしの人など、それらを習慣化するのは難しいかもしれません。本特集では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と電子回路を用いて、新型コロナウイルス感染症対策を習慣化できるような支援システムを構築します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 pirm_sensor.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(21,GPIO.IN) pir = GPIO.input(21) print(pir) |
図3 temp_sensor.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/usr/bin/env python3 from smbus2 import SMBus from mlx90614 import MLX90614 bus = SMBus(1) sensor = MLX90614(bus, address=0x5A) print(sensor.get_ambient(),sensor.get_object_1()) bus.close() |
図4 go_out.shのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |
#!/bin/bash ##外出確認の初期値と玄関にいる時間(秒) GOOUT_CHECK=0 STAY_TIME=3 ##表面体温の初期値と基準値 OUTSIDE_TEMP=0 OUTSIDE_TEMP_BASE=32 ##周辺温度の初期値と基準値 AMBIENT_TEMP=35 AMBIENT_TEMP_BASE=28 ##体内温度の基準値 INTSIDE_TEMP_BASE=36.7 ##体内温度との差分 INSIDE_BODY_DIFF=4.2 ##メッセージ集 MESSAGE1="おはようございます。出かける前に検温をしてください" MESSAGE2="周辺温度が${AMBIENT_TEMP}であり、検温に適していません。エアコンをかけてください" MESSAGE3="周辺温度が${AMBIENT_TEMP}です。検温を開始します。おでこをセンサーに向けてください" MESSAGE4="今朝の体温は${INSIDE_TEMP}です。正常値なので外出可能です。マスクを着用し、予備のマスクも持って出かけてください" MESSAGE5="今朝の体温は${INSIDE_TEMP}です。熱がありますので、正確に測れる体温計で再度測定してください" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##外出の確認 while [ ${GOOUT_CHECK} -lt ${STAY_TIME} ] do if [ $(pirm_sensor.py) -eq 1 ];then GOOUT_CHECK=$(echo "${GOOUT_CHECK} + 1" | bc) else GOOUT_CHECK=0 fi sleep 1 done voice_message ${MESSAGE1} ##周辺温度の確認 while [ ${AMBIENT_TEMP} -ge ${AMBIENT_TEMP_BASE} ] do AMBIENT_TEMP=$(/usr/bin/python3 temp_sensor.py | cut -d " " -f 1) voice_message ${MESSAGE2} sleep 5 done voice_message ${MESSAGE3} ##検温 while [ ${OUTSIDE_TEMP} -gt ${OUTSIDE_TEMP_BASE} ] do OUTSIDE_TEMP=$(/usr/bin/python3 temp_sensor.py | cut -d " " -f 2) sleep 1 done echo "$OUTSIDE_TEMP,$(date +%Y%m%d-%H:%M)" >> ${HOME}/body_temp.csv ##測定結果 INSIDE_TEMP=$(echo "scale=1; ${OUTSIDE_TEMP} + ${INSIDE_BODY_DIFF}" | bc) if [ ${INSIDE_TEMP} -lt ${OUTSIDE_TEMP_BASE} ]; then voice_message ${MESSAGE4} else voice_message ${MESSAGE5} fi |
図5 handwash_mouthwash.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
#!/usr/bin/env python3 import board import busio i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) ads = ADS.ADS1115(i2c) chan1 = AnalogIn(ads, ADS.P0) chan2 = AnalogIn(ads, ADS.P1) print(chan1.voltage,chan2.voltage) |
図6 go_home.shのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 |
#!/bin/sh ##帰宅確認の初期値 GOHOME_CHECK=0 ##手洗いとうがいの初期値 HAND_WASH=1 MOUTH_WASH=1 ##ハンドソープのポンプ圧力基準値 POMP_PUSH_BASE=3 ##うがい用コップの重量基準値 CUP_WEIGHT_BASE=3 ##メッセージ集 MESSAGE1="おかえりなさい。帰ってきたら,手を洗って、うがいをしましょう" MESSAGE2="手洗いを確認しました" MESSAGE3="うがいを確認しました" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##帰宅の確認 while [ ${GOHOME_CHECK} == 1 ] do GOHOME_CHECK=$(pirm_sensor.py) sleep 1 done voice_message ${MESSAGE1} ##手洗いとうがいの検出 while [ ${HANDWASH} == 1 -o ${MOUTHWASH} == 1 ] do ##手洗い検出の処理 HANDWASH_MOUTHWASH=$(handwash_mouthwash.py) if [ $(cut -d " " -f 1 ${HANDWASH_MOUTHWASH}) -gt ${POMP_PUSH_BASE} ]; then if [ $(HANDWASH) == 1 ]; then voice_message ${MESSAGE2} echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/handwash.csv fi HANDWASH=0 fi ##うがい検出の処理 if [ $(cut -d " " -f 2 ${HANDWASH_MOUTHWASH}) -lt ${CUP_WEIGHT_BASE} ]; then if [ $(MOUTHWASH) == 1 ]; then voice_message ${MESSAGE3} echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/mouthwash.csv fi MOUTHWASH=0 fi sleep 0.5 done |
図7 open_close.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
#!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(20,GPIO.IN) window = GPIO.input(20) print(window) |
図8 ventilation.shのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
#!/bin/bash ##メッセージ MESSAGE="窓を開けて空気を入れ換えましょう" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##在宅の確認 STAY_HOME=$(pirm_sensor.py) ##開閉の確認 OPEN_CHECK=$(open_close.py) ##換気の通知 if [ ${STAY_HOME} == 1 -a ${OPEN_CHECK} == 0 ]; then voice_message ${MESSAGE} sleep 180 if [ ${OPEN_CHECK} == 1 ]; then echo $(date +%Y%m%d-%H%M-%S) >> ${HOME}/ventilation.csv fi fi |
図9 spo2_sensor.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
#!/usr/bin/env python3 import max30102 import hrcalc m = max30102.MAX30102() red, ir = m.read_sequential() hr_spo2 =hrcalc.calc_hr_and_spo2(ir, red) print(hr_spo2[2], hr_spo2[3]) |
図10 spo2.shのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
#!/bin/bash ##在宅状態の初期値 STAY_HOME=0 ##メッセージ集 MESSAGE1="寝るときは血中酸素飽和度を測定しましょう" MESSAGE2="酸素が不足しています。医療機器で正確な値を測定してください。同じ値を示せば、至急病院に連絡しましょう" ##音声メッセージ関数 function voice_message(){ echo $1 | open_jtalk -m /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-m001/nitech_jp_atr503_m001.htsvoice -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic -ow /dev/stdout | aplay --quiet } ##在宅の確認 While [ ${STAY_HOME} == 0 ] do STAY_HOME=$(pirm_sensor.py) sleep 180 done ##血中酸素飽和度測定の通知 voice_message ${MESSAGE1} sleep 300 ##血中酸素飽和度の測定開始 while [ 1 ] do SPO2=$(/usr/bin/python3 spo2_sensor.py) SPO2_VALUE=$(echo ${SPO2} | cut -d " " -f 1) SPO2_JUDGE=$(echo ${SPO2} | cut -d " " -f 2) if [ ${SPO2_JUDGE} == "True" ]; then echo "${SPO2_VALUE} $(date +%Y%m%d-%H%M)" >> ${HOME}/spo2.csv if [ ${SPO2_VALUE} -le 93 ]; then voice_message ${MESSAGE2} exit 0 fi fi sleep 300 done |
著者:長久保 篤、酒井 利治
ソフトウエアの開発・生産性を高めるには「CI(Continuous Integration)/CD(Continuous Delivery)」が不可欠となっています。本特集では、CI/CDとは何か、オープンソースソフトウエアの「Jenkins」を用いてCI/CD環境を構築する方法を分かりやすく解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図9 Dockerfileの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
FROM jenkins/jenkins:2.277.4-lts-jdk11 USER root RUN apt update && apt install -y apt-transport-https \ ca-certificates curl gnupg2 \ software-properties-common RUN curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add - RUN apt-key fingerprint 0EBFCD88 RUN add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \ $(lsb_release -cs) stable" RUN apt update && apt install -y docker-ce-cli USER jenkins RUN jenkins-plugin-cli --plugins "blueocean:1.24.6 docker-workflow:1.26" |
図21 Jenkinsfileの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
pipeline { agent any stages { stage('ビルド') { steps { sh 'mvn -B -DskipTest clean package' } } stage('テスト') { steps { sh 'mvn -B test' } } stage('デプロイ') { steps { sh './jenkins/scripts/deliver.sh' } } } } |
図41 説明した内容を反映したJenkinsfile
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
pipeline { agent { label 'mvn3' } stages { stage('ビルド') { steps { sh 'mvn -B -DskipTest clean package' archiveArtifacts artifacts: 'target/*.jar' } } stage('テスト') { steps { sh 'mvn -B test' } post { always { junit 'target/surefire-reports/*.xml' } } } stage('デプロイ') { when { branch 'master' beforeInput true } input { message "デプロイしますか?" } steps { sh './jenkins/scripts/deliver.sh' } } } post { failure { emailext ( subject: "失敗: プロジェクト '${env.JOB_NAME} [${env.BUILD_NUMBER}]'", body: """次のページでコンソールの出力を確認してください: ${env.BUILD_URL}""", recipientProviders: [developers()] ) } } } |
著者:三沢 友治
PowerShellとは、米Microsoft社が開発したシェルおよびスクリプト言語です。Windows OSや、Microsoft Office製品に関連するサービス「Microsoft 365」を管理するのに活用されています。本特集では、これからPowerShellに取り組み始めたい人を対象に、PowerShellについて基本から分かりやすく解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.73は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図47 時刻を取得するスクリプト(writeTime.ps1)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
# 現在の時刻で時間オブジェクトを取得 # 時間オブジェクトは文字列ではなく時間の情報を保持している # そのため一部の情報を容易に取得できる $date = Get-Date # 取得した時間から指定のフォーマットでファイルを上書き # 時間を取得するhh:mmを指定し、その内容をfile.txtに上書きしている。追記したい場合は >> file.txtとする $date.ToString("hh:mm") > file.txt |
図48 ランダムな名前、ランダムな作成日でファイルを作成するスクリプト(CreateRandomFiles.ps1)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
# 指定したディレクトリにランダムな内容のファイルを指定サイズで作成する # 成功時はTrue、失敗時はFalseを返す Function CreateRandomBiteArrayFile([string]$Path, [int]$sizeMB) { try { # ランダムな10文字のファイル名を作成 $fileName = -join ((1..10) | %{(65..90) + (97..122) | Get-Random} | foreach-object {[char]$_}) # フルパスのファイル名を作る $fullFileName = $Path + "\" + $fileName + ".tmp" # ファイルの存在を確認 if(Test-Path $fullFileName) { # 同一ファイル名が失敗として終了する return $false } # 指定サイズでバイト配列を作成する $file = new-object byte[] ($sizeMB * 1024 * 1024) # バイト配列にランダムデータを入れる (new-object Random).NextBytes($file) # IO APIを利用してファイルに書き込む [IO.File]::WriteAllBytes($fullFileName, $file) # 100日の間でランダムな日を決める $day = Get-Random -maximum 100 # ファイルの作成日付を変更する(100日の間でランダム) Set-ItemProperty $fullFileName -Name LastWriteTime -Value (Get-Date).addDays($day * -1) return $true } catch { # サンプルスクリプトのため例外を大きく割愛している # 実務的なコードでは例外発生個所が分かる範囲でCatchするのが理想となる(同じ例外が発生しない粒度で) return $false } } # ファイルを格納するディレクトリ(今回の指定はカレントディレクトリ) $fileDirectoryPath = pwd # ファイルサイズ(Mバイト指定) $size = 1 # 作成ファイル数 $num = 10 # num個のファイルが作成される # ただし、ランダムなファイル名が被る場合、作成されるファイルが減る @(1..$num) | Foreach{ CreateRandomBiteArrayFile $fileDirectoryPath $size } |
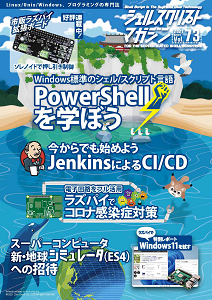
004 レポート Windows 11発表
005 レポート HE C++ Transpiler
006 NEWS FLASH
008 特集1 PowerShellを学ぼう/三沢友治 コード掲載
024 特集2 JenkinsによるCI/CD/長久保篤、酒井利治 コード掲載
042 特集3 ラズパイでコロナ感染症対策/麻生二郎 コード掲載
066 特別企画 新・地球シミュレータ(ES4)への招待/今任嘉幸、上原均
074 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡
076 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載
085 Hello Nogyo!
086 CRM/桑原滝弥、イケヤシロウ
088 レッドハットのプロダクト/宇都宮卓也
096 MySQLのチューニング/稲垣大助
104 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
106 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
110 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載
114 香川大学SLPからお届け!/岩本和真 コード掲載
120 Bash入門/大津真
130 Techパズル/gori.sh
131 コラム「ユニケージは従来のやり方と何が違うのか(前編)」/シェル魔人
UNIXやLinuxなどのOSでは、コマンドや、コマンドをプログラムのように記述したシェルスクリプトを利用してさまざまな操作が可能です。実は、Windowsでもそのようなコマンドやシェルスクリプトに相当する仕組みが「PowerShell」として用意されています。特集1では、このPowerShellを使い始めたい人向けに、PowerShellの基本操作や構文、使いこなしなどを分かりやすく解説しています。
特集2では、「Jenkins」というオープンソースソフトウエアを紹介しています。Jenkinsは、CI(継続的インテクレーション/CD(継続的デリバリ)を実現するツールであり、アプリやシステムの開発におけるコード管理、ビルド、テスト、デプロイ(配備)などを自動化します。開発者の負担を減らし、開発効率を上げるのにはとても最適です。
特集3では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と電子回路を組み合わせて新型コロナ感染症対策を支援する四つのシステムを構築しています。電子回路を初めて触る人でも簡単に作成できますので、ぜひチャレンジしてみてください。
特別企画では、2021年3月に稼働を開始した、海洋研究開発機構が運用するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」の第4世代を紹介しています。地球シミュレータがどのようなもので、何に利用されていて、どのような仕組みで動作しているのかを知るにはよい記事です。
そのほか、2021年内の提供されるWindows 11をラズパイで試すレポート、入門者や初心者向けの機械学習連載など、面白い記事満載です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.73。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
pp.18-21の図33~図34のキャプション内容に誤りがありました。キャプションの内容が一つずつずれています。正しくは、以下の通りです。お詫びして訂正いたします。
図33 テーマ「powerlevel10k_rainbow」を適用した画面
図34 フォントのインストール
図35 インストールしたフォントをPowerShellに適用する
図36 プロファイルの配置を確認する
図37 Windows PowerShell ISEの起動
図38 ISEの初期画面
図39 インテリセンスにより候補を表示する
図40 コマンド アドオンからコマンドレットを調べる
図41 コマンド アドオンからコマンドレットを選択したら、パラメータを付けてそのまま実行できる
図42 ISEのデバックメニュー
図43 ブレークポイントは茶色で表示される
図44 スニペットを表示して挿入できる
図45 ISEが意図しない状態で停止した場合に表示されるダイアログ
図46 復元されたスクリプトはタブに「回復済み」と表示される
図47 時刻を取得するスクリプト(writeTime.ps1)
p.22の「図48 ランダムな名前、ランダムな作成日でファイルを作成するスクリプト(CreateRandomFiles.ps1)」の最終行として「}」が抜けていました。 お詫びして訂正いたします。
p.59の「図2 pirm_sensor.pyのソースコード」の先頭にある「1 !/usr/bin/env python3」は「2 #!/usr/bin/env python3」の誤りです。お詫びして訂正します。
2021年6月号(Vol.72)と同じ内容でした。2021年8月号(Vol.73)のコラムはこちらから閲覧できます(Kindle版やPDF版は反映済みです)。次号となる2021年10月号(Vol.74)にも掲載する予定です。お詫びして訂正します。
情報は随時更新致します。
著者:重松 亜夢
今回は、「gRPC」という通信プロトコルを使った、Webアプリケーションの作成方法を紹介します。gRPCを使うことで、通信量が減らせます。最近注目のマイクロサービスの連携にも活用できます。
シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 「pb/picture.proto」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
syntax = "proto3"; option go_package = "example.com/user_name/sample/pb/go/picture"; package picture; service Picture { rpc GetPictures (GetPicturesRequest) returns (GetPicturesReply) {} } message GetPicturesRequest { uint32 num = 1; } message GetPicturesReply { repeated bytes pictures = 1; } |
図4 「pb/protoc-web/Dockerfile」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
FROM node:15-buster WORKDIR /pb RUN npm i rimraf -g RUN curl -L -O https://github.com/protocolbuffers/protobuf/releases/download/v3.15.8/protoc-3.15.8-linux-x86_64.zip RUN curl -L -O https://github.com/grpc/grpc-web/releases/download/1.2.1/protoc-gen-grpc-web-1.2.1-linux-x86_64 RUN unzip protoc-3.15.8-linux-x86_64.zip && cp ./bin/protoc /usr/local/bin/. && chmod +x /usr/local/bin/protoc RUN cp protoc-gen-grpc-web-1.2.1-linux-x86_64 /usr/local/bin/protoc-gen-grpc-web && chmod +x /usr/local/bin/protoc-gen-grpc-web |
図5 「pb/scripts/picture-compile.sh」ファイルに追記する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
docker build protoc-web -t streaming-protoc-web mkdir -p js/picture docker run -v "$(pwd):/pb" -w /pb --rm streaming-protoc-web \ protoc --proto_path=. picture.proto \ --js_out=import_style=commonjs:js/picture \ --grpc-web_out=import_style=typescript,mode=grpcwebtext:js/picture mkdir -p ../services/client/src/pb cp -r ./js/* ../services/client/src/pb/ |
図6 「Makefil e」ファイルの変更内容
|
1 2 3 4 |
proto: pb/js/picture/picture_pb.js # make .proto pb/js/picture/picture_pb.js: pb/picture.proto bash ./pb/scripts/picture-compile.sh |
図8 「docker-compose.yaml」ファイルに追加する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
proxy: container_name: sample-proxy-container image: envoyproxy/envoy-dev:1f642ab20b8975654482411537a6bdc5e2f6c4f6 ports: - "8080:8080" volumes: - ./services/proxy/envoy.yaml:/etc/envoy/envoy.yaml |
図9 「services/client/src/components/Picture.tsx」ファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
import { useState } from 'react'; import { GetPicturesRequest, GetPicturesReply } from "../pb/picture/picture_pb"; import { PictureClient } from "../pb/picture/PictureServiceClientPb"; import { Error } from 'grpc-web'; export const Picture = () => { const [num, setNumber] = useState(1); // 枚数の指定 const [pictures, setPictures] = useState<JSX.Element[]>([]); const jspb = require('google-protobuf'); const client = new PictureClient(`http://${window.location.hostname}:8080/server`, {}, {}); const getPictures = () => { if (num <= 0) return; const request = new GetPicturesRequest(); request.setNum(num); client.getPictures(request, {}, (err: Error, response: GetPicturesReply) => { if (err || response === null) { throw err; } setPictures(jspb.Message.bytesListAsB64(response.getPicturesList()) .map((images: string, index: number) => ( <img key={`${index}`} width="200px" src={`data:image/jpg;base64,${window.atob(images)}`} alt="pictures" /> ))); }); } const onChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { const n = event.target.valueAsNumber; if (!isNaN(n)) { setNumber(n); } }; return ( <div> <input type="number" min="1" defaultValue="1" onChange={onChange} /> <button onClick={getPictures}>GetPictures</button> <div className="getPictures">{pictures}</div> </div> ); } |
図10 「services/client/src/App.tsx」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
import {Picture} from './components/Picture' import './App.css'; function App() { return ( <div className="App"> <header className="App-header"> <Picture/> </header> </div> ); } export default App; |
著者:川嶋 宏彰
本連載では、機械学習の基礎となるさまざまな手法の仕組みや、それらの手法のPythonでの利用方法を解説していきます。第1回となる今回は、機械学習の概要についても解説します。また、「k近傍法」という手法を使いながら機械学習の重要な概念をいくつか紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図7 データセットを読み込んで散布図行列をプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams['font.size'] = 14 # seabornより読み込む場合 penguins = sns.load_dataset('penguins') # seabornではなくpalmerpenguinsから読み込む場合 # from palmerpenguins import load_penguins # penguins = load_penguins() # 散布図行列をプロット sns.pairplot(penguins, hue='species') plt.show() # 相関係数を計算 print(penguins.corr()) |
図9 二つの特徴量を抽出して散布図をプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
features = ['bill_depth_mm', 'body_mass_g'] target_species = ['Adelie', 'Gentoo'] # 特徴量をクラスラベルと共に取り出す df = penguins[['species'] + features].copy() df.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 # 読み込むデータセットを対象種のものだけにする df2 = df[df['species'].isin(target_species)].copy() print(df2.shape) # (274, 3) と表示される # カラーパレットの取得と設定 palette = sns.color_palette() palette2 = {'Adelie':palette[0], 'Gentoo':palette[2]} fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) sns.scatterplot(data=df2, x=features[0], y=features[1], hue='species', palette=palette2) # plt.axis('equal') # ★この行は後で利用 plt.show() |
図11 k-NNによる判定をするシンプルなPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
import numpy as np import scipy X = df2[features].values # 2次元特徴量 y = df2['species'].values # クラスラベル x_test = np.array([16, 4000]) # 判定したいデータ k = 5 # 近い順に何個のデータまで見るか # x_testとXの各点(各行)との距離の二乗 dist2 = ((X - x_test) ** 2).sum(axis=1) # 距離の小さいk個の点のラベル k_labels = y[np.argsort(dist2)][:k] result = scipy.stats.mode(k_labels)[0][0] # 最頻ラベル |
図12 k-NNによる判定をする改良版のPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 |
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier clf = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf.fit(X, y) # 学習 y_pred = clf.predict([[16, 4000], [16, 5000]]) # 一度に複数判定 print(y_pred) |
図13 分類器の決定境界を描画するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
import matplotlib as mpl def plot_decision_boundary(X, y, clf, xylabels=features, palette=None): # 分類器clfの決定境界を描画 fig = plt.figure(figsize=(5, 5)) # 2次元空間にグリッド点を準備 xmin = X.min(axis=0) # 各列の最小値 xmax = X.max(axis=0) # 各列の最大値 xstep = [(xmax[i]-xmin[i]) / 50 for i in range(2)] # グリッドのステップ幅 xmin = [xmin[i] - 8*xstep[i] for i in range(2)] # 少し広めに xmax = [xmax[i] + 8*xstep[i] for i in range(2)] aranges = [np.arange(xmin[i], xmax[i] + xstep[i], xstep[i]) for i in range(2)] x0grid, x1grid = np.meshgrid(*aranges) # 各グリッド点でクラスを判定 y_pred = clf.predict(np.c_[x0grid.ravel(), x1grid.ravel()]) y_pred = y_pred.reshape(x0grid.shape) # 2次元に y_pred = np.searchsorted(np.unique(y_pred), y_pred) # 値をindexへ clist = palette.values() if type(palette) is dict else palette cmap = mpl.colors.ListedColormap(clist) plt.contourf(x0grid, x1grid, y_pred, alpha=0.3, cmap=cmap) sns.scatterplot(x=X[:, 0], y=X[:, 1], hue=y, palette=palette) plt.legend() plt.xlim([xmin[0], xmax[0]]) plt.ylim([xmin[1], xmax[1]]) plt.xlabel(xylabels[0]) plt.ylabel(xylabels[1]) clf_orig = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_orig.fit(X, y) plot_decision_boundary(X, y, clf_orig, palette=palette2) plt.show() |
図16 スケーリング後に決定境界を描画するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
from sklearn.preprocessing import StandardScaler scaler = StandardScaler() Xs = scaler.fit_transform(X) # StandardScaler を用いず以下のようにしてもよい # Xs = (X - X.mean(axis=0))/X.std(axis=0) clf_scaled = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_scaled.fit(Xs, y) # 軸ラベル変更 xylabels = [s.replace('_mm', '_s').replace('_g', '_s') for s in features] # スケーリング後の決定境界を描く plot_decision_boundary(Xs, y, clf_scaled, xylabels=xylabels, palette=palette2) plt.show() |
図21 kの値を変えた場合の3種のペンギンの決定境界を描画するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
# 取り出す特徴量を変える features2 = ['bill_depth_mm', 'bill_length_mm'] df3 = penguins[['species'] + features2].copy() df3.dropna(inplace=True) # NaN が含まれる行は削除 Xs = scaler.fit_transform(df3[features2]) y = df3['species'] palette3 = dict(zip(y.unique(), palette)) # 3種用カラーパレット xylabels = [s.replace('_mm', '_s') for s in features2] for k in [1, 5, 11]: clf_scaled = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) clf_scaled.fit(Xs, y) plot_decision_boundary(Xs, y, clf_scaled, xylabels=xylabels, palette=palette3) plt.title(f'k = {k}') plt.legend(loc='upper left', borderaxespad=0.2, fontsize=12) plt.show() |
著者:米田 聡
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第3回は、温度、湿度、気圧を測定する拡張基板を扱います。
シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 温度、湿度、気圧を測定するサンプルプログラム(sample.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
import smbus2 import bme280 BME_ADDRESS = 0x76 # BME280のI2Cアドレス bus = smbus2.SMBus(1) data = bme280.sample(bus, BME_ADDRESS) # 測定データを得る print("温度: %.2f ℃" % data.temperature) print("気圧: %.2f hPa" % data.pressure) print("湿度: %.2f %%" % data.humidity) |
著者:麻生 二郎
小型コンピュータボードの最上位モデルである「Raspberry Pi 4 Mobel B」の4G/8Gバイト版と、人気のLinuxディストリビューションのサーバー版「Ubuntu Server」を組み合わせて、本格的なサーバーを構築しましょう。本特集では、サーバー向けにハードウエアを強化する方法を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.72は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図20 無線LANの設定
|
1 2 3 4 5 6 |
wifis: wlan0: access-points: SSID: password: パスワード dhcp4: true |
図27 固定IPアドレスを割り当てる
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
wifis: wlan0: dhcp4: false addresses: [192.168.10.100/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [192.168.10.1] access-points: SSID: password: パスワード |
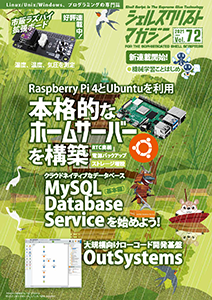
004 レポート eBPF for Windows
005 レポート TechLIONが10周年
006 NEWS FLASH
008 特集1 本格的なホームサーバーを構築/麻生二郎 コード掲載
020 特集2 MDSを始めよう!(基礎編)/生駒眞知子
029 Hello Nogyo!
030 特別企画 ローコード開発基盤 OutSystems/阿島哲夫
040 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載
042 機械学習ことはじめ/川嶋宏彰 コード掲載
052 インタプリタ/桑原滝弥、イケヤシロウ
054 レッドハットのプロダクト/暮林達也
066 Pythonあれこれ 飯尾淳
070 香川大学SLPからお届け!/重松亜夢 コード掲載
076 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
078 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
082 MySQLのチューニング/稲垣大助
090 Bash入門/大津真
098 Techパズル/gori.sh
099 コラム「ロールオーバーラップのススメ」/シェル魔人
緊急事態宣言などにより自宅にいる時間が増えています。外出できずにイライラしている、こんなときこそ、小型コンピュータボード「Rapsberry Pi」(ラズパイ)でホームサーバーを立ててみましょう。特集1では、人気のLinuxディストリビューションのサーバー版「Ubuntu Server」とラズパイを用いて、ホームサーバーを構築します。
なお、ラズパイにUbuntu Serverをインストールして初期設定を施せば、あとはパソコンとほぼ同じようにサーバーアプリを導入・できます。したがって、リアルタイムクロック(RTC)、電源バックアップ、ストレージ拡張などのハードウエア強化を中心にホームサーバーの構築を紹介します。
特集2では、オープンソースのデータベース管理システム「MySQL」のクラウドサービス「MySQL Database Service」(MDS)を紹介します。MDSは、MySQLの開発元である米Oracle社および日本オラクルが提供します。データ分析の分野では注目のサービスです。
特別企画では、大規模システムの構築可能なローコード開発基盤「OutSystems」を扱います。このOutSystemsは、無償でも使えます。OutSystemsの開発環境となる「Service Studio」を触りながら、特別企画をお楽しみください。
このほかに、入門者や初心者向けに機械学習について解説した連載「機械学習ことはじめ」が始まりました。AI(人工知能)の技術を学びたい人には最適です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.72。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
著者:飯尾淳
本連載では「Pythonを昔から使っているものの、それほど使いこなしてはいない」という筆者が、いろいろな日常業務をPythonで処理することで、立派な「蛇使い」に育つことを目指します。その過程を温かく見守ってください。皆さんと共に勉強していきましょう。第1回は、アンケート結果から非定型なデータを取り出して集計します。
シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図5 形態素解析の処理をするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/usr/bin/env python import spacy import sys nlp = spacy.load('ja_ginza') for line in sys.stdin: # 一行ずつ処理 for sent in nlp(line.strip()).sents: # 一文ずつに分解 for token in sent: # さらに文中のトークンごとに処理 # i:トークン番号, orth_:表層形, lemma_:基本形, # pos_:品詞(英語), tag_:品詞細分類(日本語) sys.stdout.write(f'{token.i}\t{token.orth_}\t{token.lemma_}\t' f'{token.pos_}\t{token.tag_}\n') sys.stdout.write('EOS\n') |
図7 名詞の連接処理と抽出をするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
#!/usr/bin/env python import sys import re def sequence_gen(): sequence = [] for line in sys.stdin: if line == 'EOS\n': yield sequence sequence = [] continue word_info = line.strip().split('\t') pos = word_info[4].split('-') sequence.append({'surface': word_info[1], 'base': word_info[2], 'pos': pos[0]}) pattern = re.compile('N+') for seq in sequence_gen(): encode_str = ''.join('N' if w['pos'] in ('名詞') else '?' for w in seq) for m in pattern.finditer(encode_str): print(''.join(w['surface'] for w in seq[m.start():m.end()])) |
図9 データを分析してプロットするPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
#!/usr/bin/env python import sys import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.decomposition import PCA import spacy from matplotlib import rcParams rcParams['font.family'] = 'sans-serif' rcParams['font.sans-serif'] = ['Hiragino Maru Gothic Pro', 'Yu Gothic', 'Meiryo', 'Takao', 'IPAexGothic', 'IPAPGothic', 'VL PGothic', 'Noto Sans CJK JP'] nlp = spacy.load('ja_ginza') with open(sys.argv[1]) as f: texts = [s.strip() for s in f.readlines()] vectors = [nlp(t).vector for t in texts] pca = PCA(n_components=2).fit(vectors) trans = pca.fit_transform(vectors) pc_ratio = pca.explained_variance_ratio_ plt.figure() plt.scatter(trans[:,0], trans[:,1]) i = 0 for txt in texts: plt.text(trans[i,0]+0.02, trans[i,1]-0.02, txt) i += 1 plt.hlines(0, min(trans[:,0]), max(trans[:,0]), linestyle='dashed', linewidth=1) plt.vlines(0, min(trans[:,1]), max(trans[:,1]), linestyle='dashed', linewidth=1) plt.xlabel('PC1 ('+str(round(pc_ratio[0]*100,2))+'%)') plt.ylabel('PC2 ('+str(round(pc_ratio[1]*100,2))+'%)') plt.tight_layout() plt.show() |
著者 志茂博、高畑祐輔
「インターネット誕生以来の革命」と称されることもあるブロックチェーン。そのブロックチェーン技術を利用したものの中で、幅広い用途での活用が注目されている「Ethereum(イーサリアム)」という分散アプリケーション基盤について解説します。後半では、実際に自分専用のブロックチェーンを立ち上げて操作する方法を紹介します。Ethereumとブロックチェーンの世界を体験してみてください。
シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 「genesis.json」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
{ "config": { "chainId": 15 }, "nonce": "0x0000000000000042", "timestamp": "0x0", "parentHash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", "extraData": "", "gasLimit": "0x8000000", "difficulty": "0x4000", "mixhash": "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", "coinbase": "0x3333333333333333333333333333333333333333", "alloc": {} } |
著者:樋口史弥
COVID-19の流行により、香川大学でもサークル活動に制限がかかっています。そこで、ICカードと非接触ICカードリーダーを用いて、部室の入退室をモニタリングするシステムを作成しました。部室の利用状況をリアルタイムに確認できれば密を避ける目安になりますし、何かあったときのための記録としても有用です。
シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図6 IDmを読み取って表示するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
import nfc import binascii def on_connect(tag): data={'idm': binascii.hexlify(tag.idm).decode('utf-8')} print(data) return True def main(): with nfc.ContactlessFrontend('usb:ベンダーID:プロダクトID') as clf: while clf.connect(rdwr={'targets': ['212F'], 'on-connect': on_connect}): pass if __name__ == "__main__": main() |
図7 サーバーと連携させるために挿入するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
import json from os import getenv import urllib.request def post_data(data): headers = { 'Content-Type': 'application/json', } req = urllib.request.Request(getenv('REQUEST_URI'), data=json.dumps(data).encode('utf-8'), headers=headers, method='POST') try: with urllib.request.urlopen(req) as res: if res.code == 200: result = json.loads(res.read().decode('utf-8'))['result'] if result == 'in': print('IN') else: print('OUT') except urllib.error.HTTPError as err: print("err: ", err.read()) |
図12 退出かどうかを調べるSQL 文
|
1 2 3 4 5 6 7 |
$sql = 'SELECT * '. 'FROM log INNER JOIN user '. 'ON log.user_id=user.id '. 'WHERE exit_time IS NULL '. 'AND enter_time >= DATE_SUB(CURRENT_TIMESTAMP, INTERVAL 1 DAY) '. 'AND user.idm=? '. 'ORDER BY log.enter_time DESC LIMIT 1'; |
図13 入室情報を表示するコード(index.js)により追加される情報の例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
<div class="use_now"> <div> <div class="time">2021-03-12 12:54:31</div> <div class="name">guest</div> </div> <div> <div class="time">2021-03-12 12:42:27</div> <div class="name">user1</div> </div> </div> |
図15 音を鳴らすために挿入するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
from gpiozero import TonalBuzzer from gpiozero.tones import Tone from time import sleep def beep(hertz): bz = TonalBuzzer(4) bz.play(Tone(frequency=hertz)) sleep(0.2) bz.stop() |
著者 麻生二郎
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)の最大の特徴(Picoを除く)は、LinuxなどのOSが動作することです。そのOSとして「Ubuntu」という、パソコンやサーバー向けで人気の高いLinuxディストリビューションが利用できます。本特集では、ラズパイとUbuntuを組み合わせて、Stack Overflowに似たサービスを提供できるQ&Aサイトを構築します。
シェルスクリプトマガジン Vol.71は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図20 無線LANの設定
|
1 2 3 4 5 6 |
wifis: wlan0: access-points: SSID: password: パスワード dhcp4: true |
図27 固定IPアドレスを割り当てる
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
wifis: wlan0: dhcp4: false addresses: [192.168.10.100/24] gateway4: 192.168.10.1 nameservers: addresses: [192.168.10.1] access-points: SSID: password: パスワード |

004 レポート Linuxシス管向け日本語講座
005 レポート Windows 10用無償RPAツール
006 NEWS FLASH
008 特集1 はじめてのExcel VBA/松井元
018 特集2 1Rでも快適なテレワーク環境/北谷明日香
030 特集3 ラズパイ4でQ&Aサイトを構築する/麻生二郎 コード掲載
040 特別企画 ゼロから始めるEthereum/志茂博、高畑祐輔 コード掲載
051 Hello Nogyo!
052 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡
056 レッドハットのプロダクト/田中司恩
065 MySQLのチューニング/稲垣大助
064 Webhook/桑原滝弥、イケヤシロウ
074 香川大学SLPからお届け!/樋口史弥 コード掲載
080 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
082 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
086 Pythonあれこれ/飯尾淳 コード掲載
092 Bash入門/大津真
098 Techパズル/gori.sh
100 コラム『ユニケージの作法は「生き方」に通じる』/シェル魔人
社会人になって最も使っているソフトウエアといえば、「表計算ソフト」でしょう。その表計算ソフトの代表ともいえるのが「Micrsoft Excel」です。
それでは、「Microsoft Excelが備える『マクロ』を利用したことはありますか」という質問には、多くの人がノー(NO)と答えるでしょう。マクロは、表の作成や計算に伴う手作業を自動化し、業務効率を大幅に向上できる大切な機能です。
特集1では、Microsoft Excelのマクロを利用するためのプログラミング言語である「VBA」を紹介します。VBAを使い始めたい人向けの内容で、プログラミングスキルがない人でも理解しやすいように解説しています。
特集2では、一人暮らしの人向けに、テレワーク時代におけるインテリアコーディネーションのポイントを解説しました。コロナ禍によって在宅勤務を強いられ、自宅でのテレワークが一般的になっています。ただ、ワンルームや1Kといった1部屋の空間では、仕事とプライベートを分けることが難しく、「仕事がぜんぜん進まない」「休憩がまったく取れない」のような状況に陥ることが多いでしょう。インテリアの観点からそのような状況に陥らない工夫を紹介しています。
特集3では、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)と、人気のLinuxディストリビューション「Ubuntu」を組み合わせて、実用性の高いサーバーを構築する方法を紹介しました。Stack Overflowライクな「Q&Aサイト」が簡単に立ち上げられるので、ぜひ試してみてください。
特別企画は、グロックチェーンの「Ethereum」(イーサリアム)を解説しました。ビットコインのような仮想通貨だけではなく、企業間取引の中核システムにも活用できるEthereumなので、ぜひこの機会にEthereumを学んでみましょう。
このほかに、2本の連載が始まりました。一つは、プログラミング言語「Python」をさまざまなことを利用する「Pythonあれこれ」、もう一つは、Linuxの標準シェル「Bash」の入門です。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.71。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
著者:しょっさん
ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。最終回は、本番環境として恥ずかしくないシステムをリリースする方法を解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 最終的に実装された各レイヤーのソースコード
■「src/api/expense.ts」の経費精算部分
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; import { ExpenseModel } from "./interfaces/expenseModel"; import { ExpenseController } from "./interfaces/expenseController"; const router = Express.Router(); // DBモデルおよびコントローラのインスタンス化 const expense_model = new ExpenseModel(); const expense_controller = new ExpenseController(expense_model); // コントローラへ、DBモデルのインスタンスを引き継いでいます // POST 経費の入力 router.post("/", async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { const result = await expense_controller.submitExpense(req.body!); res.send(result); }); (略) export default router; |
■「src/interfaces/expenseController.ts」の経費精算部分
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
import { SubmitExpense } from "../usecases/SubmitExpense"; import { IExpenseValue } from "../domains/expenseEntity"; import { ExpenseRepository } from "../adapters/ExpenseRepository"; import { IExpenseModel } from "./IExpenceModel"; export class ExpenseController { private expenseRepository: ExpenseRepository; // DBモデルのインスタンスを基にリポジトリをインスタンス化 constructor(model: IExpenseModel) { this.expenseRepository = new ExpenseRepository(model); } async submitExpense( expense: IExpenseValue ): Promise<IExpenseValue> { try { // リポジトリのインスタンスをユースケースへ引き継いでユースケースを実行 const usecase = new SubmitExpense(this.expenseRepository); const result = await usecase.execute(expense); return result.read(); } catch (error) { throw new Error(error); } } (略) } |
■「src/adapters/ExpenseRepository.ts」の経費精算部分
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
import { ExpenseEntity } from "../domains/expenseEntity"; import { IExpenseRepository } from "./IExpenseRepository"; import { IExpenseModel } from "../interfaces/IExpenceModel"; export class ExpenseRepository implements IExpenseRepository { private expense_model: IExpenseModel; // コントローラから引き継いだDBモデルのインスタンスをここで保持 constructor(model: IExpenseModel) { this.expense_model = model; } store(expense: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity> { // 特にフォーマットなど変更を今回はしていないので、そのまま保管メソッドをコール return this.expense_model.store(expense); } } |
図5 アクセス認可を制御する方法
■ロールによって実行するモデル操作を変更する
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
export class ExpenseModel implements IExpenseModel { private _userModel: IUserModel constructor(user: IUser) { this._userModel = user; } (略) findUnapproval(boss_id: number): Promise<ExpenseEntity[]> { if (this._userModel.role.find(role => role === 'APPROVER') { return Expense.findAll({ where: Sequelize.literal( `approval = ${approval_status.unapproved}` ), (略) } else { return Expense.findAll({ where: Sequelize.literal( `approval = ${approval_status.unapproved} and user_id IN (SELECT id FROM users WHERE boss_id = '${boss_id}')` ), (略) } } |
■経費精算テーブルにアクセス認可用の「role」カラムを追加してアクセス認可させる
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
export class ExpenseModel implements IExpenseModel { private _userModel: IUserModel constructor(user: IUser) { this._userModel = user; } (略) findUnapproval(boss_id: number): Promise<ExpenseEntity[]> { return Expense.findAll({ where: { approval: ${approval_status.unapproved} role: ${this._userModel.role} } (略) } } |
著者:大津真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。最終回となる今回は、関数について解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図1 シェルスクリプト「hello1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#!/bin/bash function hello() { echo "Hello Function" } hello hello hello |
図2 シェルスクリプト「param_test1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
#!/bin/bash function param_test() { echo "\$0: $0" echo "\$1: $1" echo "\$2: $2" echo "\$3: $3" echo "\$4: $4" echo "\$#: $#" echo "\$@: $@" } param_test 春 夏 秋 冬 |
図3 シェルスクリプト「scope1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/bin/bash function scope_test() { g1="グローバル" local l1="ローカル" } scope_test echo "g1: $g1" echo "l1: $l1" |
図4 シェルスクリプト「file_test1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
#!/bin/bash function check_file() { if [[ -f $1 ]]; then echo "ファイルが存在します" return 0 else echo "$1が見つかりません" return 1 fi } if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi check_file $1 echo "終了ステータス: $?" |
図5 ライブラリファイル「my_lib.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
function check_file() { if [[ -f $1 ]]; then echo "ファイルが存在します" return 0 else echo "$1が見つかりません" return 1 fi } |
図6 シェルスクリプト「file_test2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
#!/bin/bash source ./my_lib.sh if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi check_file $1 echo "終了ステータス: $?" |
図7 シェルスクリプト「sum_test1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
#!/bin/bash function calc_sum() { sum=0 for n in $(seq $1) do sum=$(expr $sum + $n) done echo $sum } # 引数があるかどうかのチェック if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数を指定してください" exit 1 fi # 引数が整数値であることを調べる expr $1 + 1 &> /dev/null if [[ $? -ge 2 ]] then echo "整数値を指定してください" exit $? fi # calc_sum関数を呼び出す echo "1から$1までの総和: $(calc_sum $1)" |
図8 シェルスクリプト「test1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
#!/bin/bash num=10 sum=0 for n in $(seq $num) do sum=$(expr $sum + $n) done echo "総和: $sum" |
著者:高嶋真輝
今回は、本物に限りなく近いデータを生成できる「敵対的生成ネットワーク」(Generative Adversarial Networks)という機械学習の技術と、「Fashion-MNIST」という服飾画像のデータセットを用いて、靴の画像生成に挑戦します。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 各種ライブラリをインポートするためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
%matplotlib inline import tensorflow as tf import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from tensorflow.keras.datasets import fashion_mnist from tensorflow.keras import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Reshape, LeakyReLU from tensorflow.keras.optimizers import Adam from google.colab import drive |
図4 モデルの入力次元を設定するためのコード
|
1 2 3 4 5 |
img_rows = 28 #画像の横軸 img_cols = 28 #画像の縦軸 channels = 1 #画像のチャンネル数(モノクロは「1」、カラーは「3」) img_shape = (img_rows, img_cols, channels) z_dim = 100 #ノイズベクトルの次元数 |
図5 生成器のモデルを構築する関数を定義するためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
# 生成器モデル構築(画像形状情報:tuple, 入力ノイズベクトル次元数:int) def generatorBuilder(img_shape, z_dim): model = Sequential() # 全結合層(ノード数:int, 入力の形状(第1層のときのみ):z_dim(int)) model.add(Dense(128, input_dim=z_dim)) # LeakyReLUによる活性化(alpha=負の場合の傾き:double) model.add(LeakyReLU(alpha = 0.2)) # 出力層(全結合層)と活性化(ノード数:int, activation = :活性化関数(string)) model.add(Dense(28*28*1, activation="tanh")) # 整形(整形後の形状:img_shape(tuple)) model.add(Reshape(img_shape)) return model |
図9 生成器のモデルを構築する関数を定義するためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
# 識別器モデル構築(画像形状情報:tuple(rows:int,cols:int,channels:int) def discliminatorBuilder(img_shape): model = Sequential() # データを並べる(第1層なので入力の形状:img_shape(tuple)) model.add(Flatten(input_shape=img_shape)) # 全結合層(ノード数:int) model.add(Dense(128)) # LeakyReLUによる活性化(alpha= : double) model.add(LeakyReLU(alpha = 0.01)) #出力層と活性化(ノード数:int, activation = :活性化関数(string)) model.add(Dense(1, activation="sigmoid")) return model |
図11 GANのシステムモデルを構築する関数を定義するためのコード
|
1 2 3 4 5 6 |
# GANモデル構築関数 def ganBuilder(generator, discriminator): model = Sequential() model.add(generator) model.add(discriminator) return model |
図12 学習モデルをコンパイルするためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
# 識別器モデル作成(入力形状:img_shape(tuple)) discriminator = discliminatorBuilder(img_shape) # 識別器コンパイル # (loss = :損失関数, optimizer = :最適化手法, metrics = :評価関数) discriminator.compile(loss = "binary_crossentropy", optimizer=Adam(), metrics=['accuracy']) # 生成器モデル作成(出力形状:img_shape(tuple), 入力形状:z_dim(int)) generator = generatorBuilder(img_shape, z_dim) discriminator.trainable = False # 識別器モデルの学習停止 # GANモデル作成(生成器モデル:generator, 識別器モデル:discriminator) gan = ganBuilder(generator, discriminator) # GANコンパイル:(loss = :損失関数, optimizer = :最適化手法) gan.compile(loss = "binary_crossentropy", optimizer = Adam()) |
図13 損失などのデータを格納する変数を定義するためのコード
|
1 2 3 |
losses = [] accuracies = [] iteration_checkpoints = [] |
図14 学習用データを準備するためのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
# 訓練用データの抽出 (trainData, trainLabel), (_, _) = fashion_mnist.load_data() trainData = trainData / 127.5 - 1.0 trainData = np.expand_dims(trainData, axis=3) # 真画像ラベル作成 batch_size = 128 real = np.ones((batch_size, 1)) # 偽画像ラベル作成 fake = np.zeros((batch_size, 1)) # 靴のデータの抜き出し # trainLabelは、5がサンダル、7がスニーカ、9がブーツ trainData = trainData.tolist() trainShoes = [] for i in range(len(trainLabel)): if trainLabel[i] in [5,7,9]: trainShoes.append(trainData[i]) |
図15 学習処理用の関数を定義するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
def train(iterations, batch_size, sample_interval): for iteration in range(iterations): # 真画像群の作成 idx = np.random.randint(0, len(trainShoes), batch_size) imgs = [trainShoes[i] for i in idx] imgs = np.asarray(imgs) # 生成画像群の作成 # ランダムノイズ作成(正規分布の平均値:float, 標準偏差:float, 形状:tuple) z = np.random.normal(0,1,(batch_size, z_dim)) # 生成画像の取得 gen_imgs = generator.predict(z) # 識別器訓練:真偽のそれぞれで実施 d_loss_real = discriminator.train_on_batch(imgs, real) d_loss_fake = discriminator.train_on_batch(gen_imgs, fake) # 損失と正確さを計算(2損失の合算を半分にする) d_loss, accuracy = 0.5 * np.add(d_loss_real, d_loss_fake) ## 生成画像群の作成(GAN学習用) z = np.random.normal(0,1,(batch_size, z_dim)) g_loss = gan.train_on_batch(z, real) if (iteration + 1) % sample_interval == 0: # 記録と出力 losses.append((d_loss, g_loss)) accuracies.append(100.0 * accuracy) iteration_checkpoints.append(iteration + 1) print("%d [D loss: %f, acc: %.2f%%][G loss: %f]" % (iteration + 1, d_loss, 100.0*accuracy, g_loss)) ## 学習済みgeneratorを渡す(iteration+1は保存に使う) showSample(generator, iteration+1) |
図16 画像の表示と保存をする関数を定義するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
# 画像生成と表示 # (学習済みgenerator:TensorFlowSequential, 画像表示用の行, 列:int) def showSample(generator, iteration, img_grid_rows=4, img_grid_cols=4): z = np.random.normal(0, 1, (img_grid_rows*img_grid_cols, z_dim)) gen_imgs = generator.predict(z) # 画像生成 gen_imgs = 0.5 * gen_imgs + 0.5 # 画素値を[0, 1]でスケーリング #画像の表示領域の確保(画像表示の行, 列, 画像サイズ, 表示画像の行と列を共有) fig,axs = plt.subplots(img_grid_rows, img_grid_cols, figsize=(4,4), sharey=True, sharex=True) cnt = 0 #画像の表示 for i in range(img_grid_rows): for j in range(img_grid_cols): axs[i, j].imshow(gen_imgs[cnt, :, :, 0], cmap='gray') axs[i,j].axis('off') cnt += 1 # 現在のfigをGoogleドライブのMy Driveに保存 fig.savefig('./gdrive/My Drive/'+str(iteration)+'FMShoesfig.png') |
著者:飯尾淳
コロナ禍の影響を受けて、2020年度は大学の講義の多くがオンライン講義になりました。対面での講義に比べると、情報伝達の面でオンライン講義はかなり不利です。また、受講状況がどうだったかについても気になります。最終回となる今回は、久しぶりに棒グラフが登場します。棒グラフで、講義コンテンツがいつ視聴されたのかを可視化します。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 未読率を計算するRubyスクリプト「midoku.rb」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
#!/usr/bin/env ruby # # for n in `seq -w 1 13`;do # ./midoku.rb Rawdata/rawdata_$n.csv $n; # done m1 = m2 = m3 = 0 File.open(ARGV[0], "r") {|f| f.each_line {|line| a = line.chomp.split(',') m1 += a.count('未読') m2 += a.count('閲覧済') m3 += a.count('更新後未読') } } printf "%s,%d,%d,%d,%04.1f\n", ARGV[1],m1,m2,m3,m1.to_f*100/(m1+m2+m3).to_f |
図7 視聴率の総計を計算するRubyスクリプト「hours.rb」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
#!/usr/bin/env ruby # # cat Rawdata/* > all.csv # ./hours.rb all.csv | sort | uniq -c | \ # sort -n -k 2 | awk '{printf("%d,%d\n", $2,$1)}' > hours.csv number = "(\\d+)" m1 = m2 = m3 = 0 File.open(ARGV[0], "r") {|f| f.each_line {|line| a = line.chomp.split(',') a.map!{|x| /#{number}:#{number}:#{number}/.match(x).to_a[1] } a -= [nil] a.map{|x| print x, "\n" } } } |
著者:森和哉
近年、ビジネスのさまざまな分野において、業務の熟練者の高齢化と、後継者不足が深刻化しています。中でも、「計画策定」業務は、豊富な経験や特殊なスキルが必要とされることから、特に属人化が進行しています。「Red Hat Business Optimizer」は、そのような企業の計画策定業務を標準化し、より効率的な計画の立案を可能にします。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図8 制約条件「すべてのシフトに従業員が割り当てられていること」のコード
■employeeRosteringScoreRules.drl
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
(略) rule "Assign every shift" when Shift(employee == null) then scoreHolder.penalize(kcontext); end (略) |
■RosterConstraintConfiguration.java
|
1 2 3 4 5 6 |
(略) public static final String CONSTRAINT_ASSIGN_EVERY_SHIFT = "Assign every shift"; (略) @ConstraintWeight(CONSTRAINT_ASSIGN_EVERY_SHIFT) private HardMediumSoftLongScore assignEveryShift = HardMediumSoftLongScore.ofMedium(1); (略) |
図9 制約条件「従業員が勤務を希望している時間帯へのシフトの割り当て」のコード
■employeeRosteringScoreRules.drl
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
(略) rule "Desired time slot for an employee" when $availability: EmployeeAvailability( state == EmployeeAvailabilityState.DESIRED, $e : employee, $startDateTime : startDateTime, $endDateTime : endDateTime) Shift(employee == $e, $startDateTime < endDateTime, $endDateTime > startDateTime) then scoreHolder.reward(kcontext, $availability.getDuration().toMinutes()); end (略) |
■RosterConstraintConfiguration.java
|
1 2 3 4 5 6 7 |
(略) public static final String CONSTRAINT_DESIRED_TIME_SLOT_FOR_AN_EMPLOYEE = "Desired time slot for an employee"; (略) @ConstraintWeight(CONSTRAINT_DESIRED_TIME_SLOT_FOR_AN_EMPLOYEE) private HardMediumSoftLongScore desiredTimeSlot = HardMediumSoftLongScore.ofSoft(10); (略) |
著者:米田聡
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第3回は、電源断でもラズパイを正常終了するための拡張基板を扱います。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 ADRSZUPコマンドのソースコード(ADRSZUP.c)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 |
#include <stdio.h> #include <fcntl.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <poll.h> #include <string.h> #include <time.h> #include <linux/reboot.h> #define TRUE 1 #define FALSE 0 /* エラーメッセージ */ void error(char *s) { fputs(s, stderr); } /* GPIO初期化 */ int initGpio(unsigned int gpio) { char buf[256]; int i, fd; // export fd = open("/sys/class/gpio/export", O_WRONLY); if( fd < 0 ) { error("/sys/class/gpio/export cant be opened \n"); return FALSE; } sprintf(buf,"%d",gpio); write(fd, buf, strlen(buf)); close(fd); // direction sprintf(buf, "/sys/class/gpio/gpio%d/direction", gpio); for( i=0; i < 10000; i++) { fd = open(buf,O_WRONLY ); if(fd >= 0) break; } if(fd < 0) { error("Direction cant opened\n"); return FALSE; } sprintf(buf,"in"); write(fd, buf, strlen(buf)); close(fd); // High -> Low falling edge sprintf(buf, "/sys/class/gpio/gpio%d/edge", gpio); for( i=0; i < 10000; i++) { fd = open(buf,O_WRONLY ); if(fd >= 0) break; } if( fd < 0 ) { error("Edge cant opended\n"); return FALSE; } sprintf(buf, "falling"); write(fd, buf, strlen(buf)); close(fd); return TRUE; } /* GPIO開放 */ int deinitGpio(unsigned int gpio) { char buf[256]; int fd; sprintf(buf, "%d", gpio); fd = open("/sys/class/gpio/unexport", O_WRONLY); if(fd < 0 ){ error("GPIO cant opened"); return FALSE; } write(fd, buf, strlen(buf)); close(fd); return TRUE; } /* シャットダウン */ int shutdown(void) { sync(); sync(); return reboot(LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF); } #define PWDN_GPIO 6 // 電源断通知GPIO番号 int main(int argc, char *argv[]) { int retval = 0; int fd; char buf[256]; char c; if(! initGpio(PWDN_GPIO) ) { error("GPIO cant be initialized\n"); return 0; } // GPIOオープン sprintf(buf,"/sys/class/gpio/gpio%d/value", PWDN_GPIO ); fd = open(buf, O_RDONLY); if(fd < 0) { error("Value cant opened"); return 0; } // 空読み read(fd, &c, 1); while(1) { struct pollfd pfd; pfd.fd = fd; pfd.events = POLLPRI; pfd.revents = 0; // GPIO fallingイベント待ち lseek(fd, 0, SEEK_SET); int r = poll(&pfd, 1, -1); fputs("Power down detected\nWait for 5 seconds\n", stdout); // 5秒待つ sleep(5); read(fd, &c, 1); if( c == '0' ) { close(fd); deinitGpio(PWDN_GPIO); fputs("Shutdown now\n",stdout); retval = shutdown(); break; } } return retval; } |
図4 /etc/systemd/system/adrszup.serviceファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
[Unit] Description=Auto shutdown process for ADRSZUP [Service] Type=simple Restart=no User=root ExecStart=/usr/local/bin/ADRSZUP [Install] WantedBy=multi-user.target |
著者:五味秀仁、板倉景子
パスワード課題の解決に注力する業界団体FIDO(ファイド)アライアンスは、
フィッシング攻撃に耐性のある、シンプルで堅牢な認証の展開を推進してい
ます。その新しい仕様「FIDO2」は、標準化団体W3Cで策定されるWeb認証仕
様「WebAuthn」(ウェブオースン)を包含し、さらにAndroidとWindowsに加えて、iOSやmacOSにも対応するなど、プラットフォーム拡大を進めています。本特集では、FIDO2の概要や仕組み、最新動向について解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.70は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図8 publicKeyデータの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
{ "publicKey": { "attestation": "direct", "authenticatorSelection": { "authenticatorAttachment": "platform", "requireResidentKey": false, "userVerification": "required" }, "challenge": "bWhMbDgxc1h4Z3B...",, "excludeCredentials": [], "pubKeyCredParams": [ { "alg": -7, "type": "public-key" } ], "rp": { "id": "example.com", "name": "Example corporation" }, "timeout": 60000, "user": { "displayName": "Ichiro Suzuki", "id": [70, 60, ...], "name": "ichiro.suzuki@example.com” } } } |
図9 認証器に登録要求を出すJavaScriptプログラムの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
if (!window.PublicKeyCredential) { WebAuthn APIが使えない場合の処理 } // プラットフォーム認証器が使える場合 PublicKeyCredential.isUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable() .then(function () { // 以下で設定するのがPublicKeyCredentialCreationOptions var options = { "publicKey": ... }; return navigator.credentials.create(options); }).then(function (newCredentialInfo) { 生成されたクレデンシャルの処理 }).catch( function(err) { エラー処理 }); |
図10 PublicKeyCredentialデータの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
{ "id": "sL39APyTmisrjh11vghaqNfuru...", "rawId": "sL39APyTmisrjh11vghaqNf...", "response": { "attestationObject": "eyJjaGFsbGVuZ2...", "clientDataJSON": "o2NmbXRmcGFja2..." }, "type": "public-key" } |
図11 attestationObject項目に設定される情報の例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
{ "fmt": "packed", "attStmt": { "alg": -7, "sig": "MEYCIQDyCG+pKJmcV...", "x5c": [ "MIICQjCCAcmgAwIBA..." ] }, "authData": { "credentialData": { "aaguid": "vfNjNcR0U8...", "credentialId": "Y0GeiMghzi...", (略) }, (略) } } |
図12 clientDataJSON項目に設定される情報の例
|
1 2 3 4 5 |
{ "challenge": "bWhMbDgxc1h4Z3B...", "origin": "https://example.com", "type": "webauthn.create" } |
図14 publicKeyデータの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
{ "publicKey": { "allowCredentials": [ { "id": "Y0GeiMghzi...", "type": "public-key" } ], "challenge": "lZgXWOY0Go6HxmQP03...", "rpId": "example.com", "timeout": 60000, "userVerification": "required" } } |
図15 認証器に認証要求を出すJavaScriptプログラムの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
// 以下で設定するのがPublicKeyCredentialRequestOptions var options = { "publicKey": ... }; navigator.credentials.get(options) .then(function (assertion) { アサーションをRPサーバーに返す処理 }).catch(function (err) { エラー処理 }); |
図16 PublicKeyCredentialデータの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
{ "id": "Y0GeiMghzi...", "rawId":"Y0GeiMghzi...", "response": { "authenticatorData": "yHxbnq0iOEP3QN0K...", "clientDataJSON": "eyJjaGFsbG...", "signature": "NRUVOWSMtH..." }, } |

004 レポート RHEL互換OSのCentOS終了
005 NEWS FLASH
008 特集1 第4世代Ryzenプロセッサ/麻生二郎
014 特集2 FIDO2の最新動向/五味秀仁、板倉景子 コード掲載
026 特別企画 Forguncyを使ってみよう/須山亜紀
040 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載
044 レッドハットのプロダクト/森和哉 コード掲載
054 MySQLのチューニング/稲垣大助
059 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
064 CI/CD/桑原滝弥、イケヤシロウ
066 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
070 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
072 香川大学SLPからお届け!/高嶋真輝 コード掲載
082 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
084 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載
096 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
102 Techパズル/gori.sh
104 コラム「ユニケージとその将来」/シェル魔人
パソコン向けのCPUとして快進撃を続けているプロセッサがあります。米Advance Micro Devices(AMD)社が開発する「Ryzen」(ライゼン)です。PlayStation 5のCPUにも採用されました。
特に、2020年11月に発売した新アーキテクチャ「Zen 3」を採用する「Ryzen 5000シリーズ」は、同程度のインテルCPUを凌駕する性能を備えています。特集1では、Ryzen 5000シリーズのZen 3アーキテクチャと対応マザーボードについて触れました。
今の時代、何をするのも個人を特定する、認証が欠かせないものになっています。しかし、古くからあるID/パスワード認証だけでは、セキュリティ上不安です。特集2では、生体認証など、新しい認証技術の業界標準「FIDO」(ファイド)の最新規格である「FIDO2」を紹介します。
ITシステムの「内製化」は、さまざまな業界で大きなキーワードになりそうです。この内製化を実現するには、複雑なプログラムや開発スタイルを排除し、誰でもシステムを作れるようにしなくてはいけません。それを実現するのが、コードを書かない、または少しのコードしか書かない「ノンコード・ローコード開発」です。
特別企画では、最もビジネスマンに浸透しているであろう表計算ソフト「Microsoft Excel」を操作するようにWebアプリを開発できるシステム構築基盤「Forguncy」(フォーガンシ―)を紹介します。
このほか、さまざまな用途に合わせてオープンソースのデータベース管理システム「MySQL」をチューニングする新連載が始まりました。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.70。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら

シェルスクリプトマガジン Vol.69(2020年12月号)の特集1で扱った、Jetson Nano 開発キットとRaspberry Piの両方で利用できる拡張基板「Jetson Nano & Pi 電力測定ボード」の販売を、自社サイトでも開始いたしました。特別価格の4540円(別途送料360円)で購入できます。
Jetson Nano & Pi 電力測定ボードは、デジタル電流・電圧・電力計モジュール「INA260」と単色有機ELディスプレイ「SSD1306」(OLEDモジュール)を搭載しています。INA260で、Jetson Nano 開発キットやRaspberry Piの消費電力をリアルタイムに測定できます。そして、SSD1306にはさまざまな情報を表示可能です。

Jetson Nano & Pi 電力測定ボードを購入して、Jetson Nano 開発キットとRaspberry Piを便利に使いましょう。
購入ページはこちらです。
筆者:大津 真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。第5回は、複数の文字列を柔軟なパターンで指定できる正規表現の基礎について解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 シェルスクリプト「pref1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/bin/bash if [[ $# -ne 1 ]]; then echo "都道府県名を一つ指定してください" exit 1 fi file=meibo.txt if grep ":${1}$" $file; then count=$(grep -c ":${1}$" $file) echo "-- ${1}は${count}件ありました --" else echo "-- ${1}は見つかりませんでした --" fi |
図3 シェルスクリプト「whileRead1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 |
#!/bin/bash while read line do echo $line done < meibo.txt |
図4 シェルスクリプト「whileRead2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 |
#!/bin/bash cat meibo.txt | while read line do echo $line done |
図5 シェルスクリプト「tokyo.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
#!/bin/bash count=0 grep ":東京$" meibo.txt | while read line do echo "$((++count)):${line}" done |
図6 シェルスクリプト「addpref.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/bin/bash while read line do if echo $line | grep -q ":東京$"; then echo $line | sed "s/:東京$/:東京都/" elif echo $line | grep -q -e ":大阪$" -e ":京都$"; then echo $line | sed "s/:\(..\)$/:\1府/" elif echo $line | grep -q ":北海道"; then echo $line else echo $line | sed "s/:\(..*\)$/:\1県/" fi done < meibo.txt |
著者:菅 雄一
2000年にLinuxサーバーを導入して以来、筆者は、主に費用面での手軽さからOSS(オープンソースソフトウエア)を活用したシステム構築に取り組んできた。だが、2020年になってWindowsサーバーに初めて触れることになった。勤務先の会社が、バッファローの「TeraStation」という法人向けのNAS(Network Attached Storage)製品を購入し、そのOSがWindowsサーバーだったからだ。今回は、そのWindowsサーバー搭載のNAS製品を設定した話を書く。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 Sambaの設定ファイル(smb.conf)の記述例
|
1 2 3 4 5 6 7 |
[global] map to guest = bad user guest account = nobody [public] path = /home/samba guest ok = yes |
著者:石塚 美伶
今回は、音楽の「耳コピ」を支援する音源可視化ツールをPythonで制作する方法について紹介します。制作するツールは、WAVファイルを読み取って音を判別し、その音をピアノの鍵盤で示すGIFアニメーションを生成します。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 「main.py」ファイルに記述する内容(その1)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
import scipy.io.wavfile # WAVファイルを読み込むために使用 from scipy import signal # 極大値を求めるために使用 import numpy as np # データの整形や高速フーリエ変換に使用 import pandas as pd # ピアノの音階辞書を作成するために使用 import matplotlib.pyplot as plt # 図の作成に使用 import matplotlib.animation as anm # アニメーション作成に使用 import matplotlib.patches as pat # 長方形を描画するために使用 import time # 時間を表示するために使用 |
図5 「main.py」ファイルに記述する内容(その2)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
wav_filename = "./source.wav" # 音声ファイルの読み込み rate, data = scipy.io.wavfile.read(wav_filename) print("サンプリング周波数:", rate) print("データ数:", len(data)) if data.ndim < 2: # 配列の次元数 print("モノラル") else: print("ステレオ") data = np.ravel(data)[::2] # 連結して偶数要素を抽出する #(振幅)の配列を作成 (「-1」~「1」の範囲に正規化) data = data / 32768 # データを0.1秒ごとに分割 split_datas = np.array_split(data, int(len(data) / (rate * 0.1))) |
図6 「main.py」ファイルに記述する内容(その3)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
count = 0 ex_freqency = [] # 抽出したデータを格納するために用意 for short_data in split_datas: ex_freqency.append([]) # データを格納するために空リストを追加 # フーリエ変換により周波数成分と振幅を取得 fft_short_data = np.abs(np.fft.fft(short_data)) freqList = np.fft.fftfreq(short_data.shape[0], d=1.0/rate) maxid = signal.argrelmax(fft_short_data, order=2) # 極大値を求める for i in maxid[0]: if fft_short_data[i] > 10 and 25 < freqList[i] < 4200: ex_freqency[count].append(freqList[i]) # 周波数を格納 count += 1 |
図8 「main.py」ファイルに記述する内容(その4)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
piano_dic = pd.read_csv("./piano_dict.csv", encoding="utf-8") print(piano_dic) black_keys = piano_dic[piano_dic["scaleNameEn"].str.contains("#")].index print(black_keys) count = 0 keys = [] # 含まれる周波数の行 for row in ex_freqency: keys.append([]) # 各フレームの周波数を格納するために空リストを追加 for i in row: # 差が最小の音階 key = piano_dic.loc[abs(piano_dic.frequency - i).idxmin(), "keyNumber"] if (key in keys[count]) == False: keys[count].append(key) # 重複してなければ音階を追加 count += 1 print(keys) |
図9 「main.py」ファイルに記述する内容(その5)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
fig, ax = plt.subplots(figsize = (10, 2)) # 各フレームの描画 def update(i, fig_title, data_list, ax): if i != 0: plt.cla() # 現在描写されているグラフを消去 ax.axis("off") # 軸と目盛りを削除 ax.set_xlim(0, 52.1) ax.set_ylim(-0.5, 2.5) skip = False white_count = 0 plt.title(fig_title + time.strftime("%M:%S", time.gmtime(i * 0.1))) for j in range(0, 88): if skip == True: skip = False # フラグを降ろす continue # 既に描画した白鍵をスキップする if j in black_keys: # 黒鍵の右側の白鍵を描画 color = "white" if j + 1 in data_list[i]: color = "red" # 音が鳴っていれば色を赤にする # 長方形を作成 rec = pat.Rectangle(xy = (white_count, 0), \ width = 1, height = 1.5, \ fc = color, ec = "black") ax.add_patch(rec) # Axesに長方形を追加 skip = True # スキップフラグを立てる # 白鍵の上に黒鍵を描画 color = "gray" x, y = white_count - 0.3, 0.5 w, h = 0.6, 1 else: # 白鍵を描画 color = "white" x, y = white_count, 0 w, h = 1, 1.5 if j in data_list[i]: color = "red" # 音が鳴っていれば色を赤にする # 長方形を作成 rec = pat.Rectangle(xy = (x, y), width = w, \ height = h, fc = color, ec = "black") ax.add_patch(rec) # Axesに長方形を追加 white_count += 1 # 白鍵の数をカウント # アニメーションを生成 ani = anm.FuncAnimation(fig, update, fargs=("Mimicopy ", keys, ax), \ interval=100, frames=len(keys)) # GIFファイルとして保存 ani.save("Sample.gif", writer="pillow") |
著者:飯尾 淳
Twitterのトレンドを分析に関する解説の最終回です。これまで、TwitterのトレンドAPIを叩いてトレンドを集め、Twitter Standard search APIでトレンドに関するツイートを収集、そのデータに基づいてトレンドの構造を分析する手法を紹介しました。今回は、その日の主要なトピックは何だったかを可視化する方法を解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図7 JSONデータを得るスクリプト(get_data.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
#!/usr/bin/env python import json import urllib.request import sys import re # replace urlbase to the base address of your application # this script should be called as $ ./get_data.py 2019-02-01 # which means the argument should be a date formatted in YYYY-MM-DD urlbase = 'http://iiojun.xyz/twt' jsonapi = '/api/' + sys.argv[1] word_dict = {} words = [] req = urllib.request.Request(urlbase+jsonapi) with urllib.request.urlopen(req) as res: content = json.loads(res.read().decode('utf8')) # loop for labels for item in content: label = item['label'] wid = item['id'] url2 = "{0}/api/trends/{1}".format(urlbase, wid) req2 = urllib.request.Request(url2) dct = {} # loop for words of each label with urllib.request.urlopen(req2) as res2: content2 = json.loads(res2.read().decode('utf8')) for item2 in content2[0]: word = item2['word'] freq = item2['freq'] dct[word] = freq # keep the all words used in the nodes in the array 'words' if not word in words: words.append(word) # keep the ary of {word, freq} in the dictionary 'word_dict' word_dict[label] = dct print("label", end="") for item in words: print("\t{0}".format(item), end="") print() for key in word_dict: print(key, end="") dct = word_dict[key] for item in words: freq = dct[item] if item in dct else 0.0 print("\t%6.3f" % freq, end="") print() |
図9 コサイン類似度を計算するスクリプト(calc_cos_sim.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
#!/usr/bin/env python3 import numpy as np import sys def cos_sim(v1, v2): return np.dot(v1, v2) / (np.linalg.norm(v1) * np.linalg.norm(v2)) lines = sys.stdin.readlines() lines.pop(0) wdic = {} visited = [] for line in lines: words = line.split('\t') label = words.pop(0) wdic[label] = list(map(lambda x: float(x),words)) for key1 in wdic: for key2 in wdic: visited.append(key2+key1) if key1 == key2 or key1+key2 in visited: continue print("{0}\t{1}\t{2:9.6f}" .format(key1,key2,cos_sim(wdic[key1],wdic[key2]))) |
図11 dotスクリプトを作成するスクリプト(mk_net.rb)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |
#!/usr/bin/ruby word_ary = [] freq_ary = [] node_set = [] node_color = {} color_tbl = %w(khaki lemonchiffon aliceblue mistyrose coral goldenrod aquamarine lavender palegreen gold lightpink plum yellow lightcyan lavenderblush gainsboro yellowgreen lightsteelblue palegoldenrod lightskyblue greenyellow plum cornflowerblue) th_val = 0.75 mthd = 'fdp' title = 'topicmap' STDIN.each {|line| (kw1,kw2,freq) = line.split(/\t/) word_ary.push(kw1) unless word_ary.include?(kw1) word_ary.push(kw2) unless word_ary.include?(kw2) if freq.to_f > th_val freq_ary.push(line) flag = false node_set.each {|x| if x.include?(kw1) && x.include?(kw2) flag = true break end len0 = x.length x.push(kw2) if x.include?(kw1) && !x.include?(kw2) x.push(kw1) if !x.include?(kw1) && x.include?(kw2) if len0 < x.length flag = true break end } node_set.push([kw1, kw2]) unless flag end } def get_set(ary_of_ary, x) ret_ary = [] ary_of_ary.each {|ary| ret_ary = ret_ary + ary if ary.include?(x) } return ret_ary end def delete_set(ary_of_ary, x) ary_of_ary.each {|ary| ary_of_ary.delete(ary) if ary.include?(x) } end freq_ary.each {|x| (kw1,kw2,freq) = x.split(/\t/) x1 = get_set(node_set, kw1) x2 = get_set(node_set, kw2) next if (x1 == x2) x3 = x1 | x2 delete_set(node_set, kw1) delete_set(node_set, kw2) node_set.push(x3) } word_ary.map {|x| node_color[x] = 'white' } node_set.each_with_index {|value,index| i = index % color_tbl.length value.map{|x| node_color[x] = color_tbl[i] } } print "graph \"#{title}\" {\n" print " graph [\n layout = #{mthd}\n ];\n" word_ary.each {|x| printf " \"%s\" [ fontname = \"ヒラギノ丸ゴ\"; style = \"filled\"; fillcolor = \"%s\"; fontcolor = \"%s\" ];\n", x, node_color[x], 'black' } while (!freq_ary.empty?) do (f,t,prob) = freq_ary.shift.split(/\t/) printf " \"%s\" -- \"%s\" [label = \"%4.2f\"];\n", f, t, prob end print "}\n" |
著者:伊藤 智博
最近は昔と比べ、ビジネス要件のレベルが高くなりました。この要件を実現するためさまざまな技術が新たに誕生していますが、それらの技術を開発者が組み合わせて使用するのは非常に困難です。第5回では、これらの技術を組み合わせて高いレベルの要件を簡単に実現するJavaフレームワークの「Quarkus」を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図7 「quarkus-getting-started/src/main/java/sample/GreetingResource.java」ファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
package sample; import javax.ws.rs.GET; import javax.ws.rs.Path; import javax.ws.rs.Produces; import javax.ws.rs.core.MediaType; @Path("/hello") public class GreetingResource { @GET @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN) public String hello() { return "hello"; } } |
著者:米田 聡
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第2回は、赤外線信号の受信が可能な拡張基板を扱います。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 /boot/config.txtファイルの末尾に追加する2行
|
1 2 |
dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=4 dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=13 |
図4 /etc/lirc/lirc_options.confファイルの変更箇所
|
1 2 3 4 5 |
(略) driver = default device = /dev/lirc1 (略) |
著者:KinoCode、ハリー
「エンジニアが次に学びたい言語」のランキングでたびたび上位にランクインしているGo言語。本特集では、Goの特徴やプログラミングについての概要を、1日で学習できるようにコンパクトに解説します。この機会にぜひGoを学んでみてください。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図13 挨拶文を表示するサンプルプログラム「greeting.go」のコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
package main import ("fmt") func main(){ fmt.Println("Good morning") fmt.Println("Good afternoon") fmt.Println("Good evening") } |
著者:北崎 恵凡
ユーザーコミュニティ「Jetson Japan User Group」のメンバーである筆者が設計した、小型コンピュータボードの「Jetson Nano」と「Raspberry Pi」で共通に使える拡張基板「Jetson & Pi 電力測定ボード」をシェルスクリプトマガジンオリジナルとして作成しました。本特集では、このJetson & Pi電力測定ボードの使い方を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.69は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図7 電源電圧を表示するサンプルプログラム「ina260.py」のソースコード
|
1 2 3 4 5 |
import smbus i2c = smbus.SMBus(1) word = i2c.read_word_data(0x40, 0x02) & 0xFFFF result = ( (word << 8) & 0xFF00 ) + (word >> 8) volt = result * 1.25 / 1000 |
図9 ina260_adafruit.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
import time import board import adafruit_ina260 i2c = board.I2C() ina260 = adafruit_ina260.INA260(i2c) while True: print("Current: %.2f Voltage: %.2f Power: %.2f" %(ina260.current, ina260.voltage, ina260.power)) time.sleep(1) |
図12 ina260_plot.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
(略) import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.animation as animation (略) NUM_BUF_POINTS = 180 PLOT_INTERVAL = 1000 def get_values(): return([float("{0:.2f}".format(ina260.current / 1000)), float("{0:.2f}".format(ina260.voltage)), float("{0:.2f}".format(ina260.power / 1000))]) (略) def plot(i): global Data zone_names = get_names() zone_temps = get_values() print(zone_temps) Data = np.append(Data, np.array([zone_temps]), axis = 0) if i >= NUM_BUF_POINTS: Data = np.delete(Data, 0, axis = 0) plt.cla() plt.plot(Data, marker = 'x') plt.xlim(0, NUM_BUF_POINTS) plt.ylim(0.0, 10.0) plt.title('Current Monitor', fontsize = 14) plt.xlabel('Time', fontsize = 10) plt.ylabel('Current[A],Voltage[V],Power[W]', fontsize = 10) plt.tick_params(labelsize=10) plt.grid(True) plt.legend(labels = zone_names, loc = 'upper left', fontsize = 10) def main(): global Data zone_names = get_names() print(zone_names) Data = np.empty((0, len(zone_names)), float) fig = plt.figure(figsize=(10, 4)) ani = animation.FuncAnimation(fig, plot, fargs = (), interval = PLOT_INTERVAL) plt.show() (略) |
図14 ssd1306_stats.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
(略) from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont import adafruit_ssd1306 (略) i2c = busio.I2C(SCL, SDA) (略) disp = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(128, 32, i2c) (略) width = disp.width height = disp.height image = Image.new("1", (width, height)) (略) draw = ImageDraw.Draw(image) (略) cmd = "hostname -I | cut -d' ' -f1" IP = subprocess.check_output(cmd, shell=True).decode("utf-8") cmd = "top -bn1 | grep load | awk '{printf \"CPU Load: %.2f\", $(NF-2)}'" CPU = subprocess.check_output(cmd, shell=True).decode("utf-8") cmd = "free -m | awk 'NR==2{printf \"Mem: %s/%s MB %.2f%%\", $3,$2,$3*100/$2 }'" MemUsage = subprocess.check_output(cmd, shell=True).decode("utf-8") cmd = 'df -h | awk \'$NF=="/"{printf "Disk: %d/%d GB %s", $3,$2,$5}\'' Disk = subprocess.check_output(cmd, shell=True).decode("utf-8") (略) draw.text((x, top + 0), "IP: " + IP, font=font, fill=255) draw.text((x, top + 8), CPU, font=font, fill=255) draw.text((x, top + 16), MemUsage, font=font, fill=255) draw.text((x, top + 25), Disk, font=font, fill=255) (略) disp.image(image) disp.show() |
図19 ina260_oled.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(略) import adafruit_ina260 i2c2 = board.I2C() ina260 = adafruit_ina260.INA260(i2c2) (略) c = ina260.current v = ina260.voltage p = ina260.power print("Current: %.2f Voltage: %.2f Power: %.2f" %(c, v, p)) (略) draw.text((x, top + 0), "Current(mA): " + str("{0:.2f}".format(c)) + ' ', font=font, fill=255) draw.text((x, top + 14), "Voltage(V): " + str("{0:.2f}".format(v)) + ' ', font=font, fill=255) draw.text((x, top + 28), "Power(mW): " + str("{0:.2f}".format(p)) + ' ', font=font, fill=255) (略) disp.image(image) disp.show() (略) |
図21 ssd1306_jp_font.pyのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 |
(略) font = ImageFont.truetype('usr/share/fonts/truetype/fonts-japanese-gothic.ttf', 14) (略) draw.text((x, top + 0), "てすと", font=font, fill=255) draw.text((x, top + 14), "日本語", font=font, fill=255) (略) |
図28 imagenet-console_oled.pyのソースコード
|
1 2 3 4 |
(略) draw.text((0, 0), "分類: " + translator.convert(class_desc), font=font, fill=255) draw.text((0, 14), "確率: " + "{:0.2f}%".format(confidence * 100), font=font, fill=255) (略) |
図32 imagenet-camera_oled.pyのソースコード
|
1 2 3 4 |
(略) draw.text((0, 0), "分類: " + translator.convert(class_desc), font=font2, fill=255) draw.text((0, 14), "確率: " + "{:0.2f}%".format(confidence * 100), font=font2, fill=255) (略) |
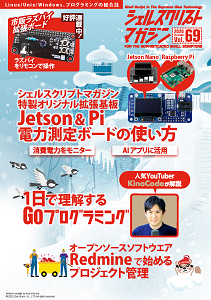
004 レポート MacのApple M1
005 レポート セキュリティゲーム「TERMINAL」
006 NEWS FLASH
008 特集1 Jetson & Pi 電力測定ボードの使い方/北崎恵凡 コード掲載
026 特集2 1日で理解するGoプログラミング/KinoCode、ハリー コード掲載
036 特別企画 Redmineで始めるプロジェクト管理/前田剛
048 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載
051 Hello Nogyo!
052 レッドハットのプロダクト/伊藤智博 コード掲載
062 Docker/桑原滝弥、イケヤシロウ
064 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
070 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
072 香川大学SLPからお届け!/石塚美伶 コード掲載
076 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
078 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一 コード掲載
084 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
092 Techパズル/gori.sh
094 コラム「長続きの秘訣」/シェル魔人
Jetson Japan User Groupの協力を得て、シェルスクリプトマガジン特製オリジナル拡張基板の第3弾となる「Jetson & Pi 電力測定ボード」を開発しました。この拡張基板は、Jetson Nanoの開発キットとRaspberry Pi(ラズパイ)の小型コンピュータボードの両方で利用できます。特集1では、Jetson & Pi 電力測定ボードの概要や使い方などを詳しく紹介します。
特集2では、人気YouTuberであるKinoCode(キノコード)氏が解説するGoプログラミングです。Goは、米Google社が開発したプログラミング言語です。コンパイル型のために高速な上、プログラムが書きやすく、安全性も高く作られています。最近、最も注目されています。
特集3では、オープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」を分かりやすく紹介します。Redmineは「チケット」という単位でさまざまなタスクを管理できます。とても柔軟性が高く、設定次第ではプロジェクト管理だけでなく、さまざまな用途に活用できます。
このほか、市販の拡張ボードでラズパイを100%利用する記事や、中小企業のシステム管理者の実体験を紹介した奮戦記なども連載として掲載しています。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.69。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
著者:大津 真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。第4回は、繰り返し処理を実現する制御構造を中心に解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図1 リストにある果物名を一つずつ表示するシェルスクリプトの例
|
1 2 3 4 |
for name in メロン バナナ イチゴ ミカン do echo $name done |
図2 シェルスクリプト「showArgs1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash for name in $@ do echo $name done |
図3 シェルスクリプト「showArgs2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash for name in "$@" do echo $name done |
図4 シェルスクリプト「showArgs3.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash for name do echo $name done |
図5 シェルスクリプト「colon_to_comma2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi if [[ ! -f $1 ]]; then echo "$1が見つかりません" exit 1 fi fname=$1 cp "$fname" "${fname}~" tr ":" "," < "${fname}~" > "$fname" |
図6 シェルスクリプト「colon_to_comma3.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi for file in $@ do if [[ ! -f $file ]]; then echo "$fileが見つかりません" exit 1 fi fname=$file echo "変換中: $file" cp "$fname" "${fname}~" tr ":" "," < "${fname}~" > "$fname" done |
図7 シェルスクリプト「hello10.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash for i in $(seq 10) do echo "$i: こんにちは" done |
図8 シェルスクリプト「case1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/bin/bash case $1 in [a-z]*) echo "アルファベット小文字で始まります" ;; [A-Z]*) echo "アルファベット大文字で始まります" ;; [0-9]*) echo "数字で始まります" ;; *) echo "その他" esac |
図9 シェルスクリプト「case2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
#!/bin/bash for file do case $file in *.txt) echo "テキスト: $file" ;; *.htm | *.html) echo "HTML: $file" ;; *) echo "その他: $file" esac done |
図10 シェルスクリプト「pat1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 |
#!/bin/bash path="/home/o2/music/sample.test.mp3" echo '${path#/*/} = ' ${path#/*/} echo '${path##/*/} = ' ${path##/*/} echo '${path%.*} = ' ${path%.*} echo '${path%%.*} = ' ${path%%.*} |
図11 シェルスクリプト「cgExt1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi for file do case $file in *.htm) newfile=${file%.*}.html echo "$file to $newfile" mv $file $newfile ;; *.jpeg) newfile=${file%.*}.jpg echo "$file to $newfile" mv $file $newfile ;; esac done |
図12 シェルスクリプト「while1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
#!/bin/bash read -p "文字列? " str while [[ -n $str ]] do echo $str | tr "a-z" "A-Z" read -p "文字列? " str done |
図13 シェルスクリプト「while2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/bin/bash while true do read -p "文字列? " str if [[ -z $str ]]; then break fi echo $str | tr "a-z" "A-Z" done |
図14 シェルスクリプト「cgExt2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo "引数でファイルを指定してください" exit 1 fi for file do if [[ ! -f $file ]]; then echo "${file}が見つかりません" continue fi case $file in *.htm) newfile=${file%.*}.html echo "$file to $newfile" mv $file $newfile ;; *.jpeg) newfile=${file%.*}.jpg echo "$file to $newfile" mv $file $newfile ;; esac done |
著者:飯尾 淳
Twitterのトレンド分析に関する解説も、とうとう3回目に突入しました。今回は、共起ネットワークグラフの描画処理について説明します。描画にはD3.jsというグラフ描画フレームワークを使います。この描画処理では、データの受け渡し方法にちょっとした工夫をしており、それについても解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 トレンド表示画面を構成するビューのソースコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
<h2> <%= link_to @trend.label, "https://twitter.com/search?q=#{@trend.label}", :target => '_blank' %> </h2> <p> <%= t('collected') %> <%= link_to l(@trend.collected, format: :long), "../#{@trend.collected}", :class => 'href' %> <%= link_to t('prev_item'), trend_path(@prev), :class => 'href' if @prev != nil %> <%= link_to t('next_item'), trend_path(@next), :class => 'href' if @next != nil %> </p> <div id="graph_canvas" data-src="<%= api_trend_path(@trend) %>"> </div> |
図5 サーバー側の処理をするRailsのコントローラのコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
class Api::TrendsController < ApplicationController def index render json: Trend.where(collected: params[:date]) end def show l = [] @trend = Trend.find(params[:id]) l.push(@trend.nodes) @trend.nodes.each {|n| l.push(n.links) } render json: l end end |
図6 クライアント側の処理をするコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 |
$(document).on('turbolinks:load', function() { if ($('#graph_canvas').attr('data-src') != undefined) { $.ajax({ url: $('#graph_canvas').attr('data-src'), dataType: 'json', success: function(data) { drawGraph(data); }, error: function(data) { alert('error'); } }); } }); function drawGraph(data) { "use strict" var width, height, chartWidth, chartHeight, margin d3.select("#svg").remove() var svg = d3.select("#graph_canvas") .append("svg").attr("id", "svg") var chartLayer = svg.append("g").classed("chartLayer", true) setSize() drawChart(convertData(data)) function convertData(data) { var nodes = data.shift() var n_ary = nodes.map(function(d) { d['r'] = d.freq / 4 + 15; return d }) var l_hash = {} var ctr = 0 for (var n_links of data) { for (var link of n_links) { if (l_hash[link.id] == undefined) { l_hash[link.id] = { line_width: link.corr / 20, source: nodes[ctr] } } else { l_hash[link.id]['target'] = nodes[ctr] } } ctr++ } return { nodes: n_ary, links: Object.values(l_hash) } } function setSize() { width = document.querySelector("#graph_canvas").clientWidth height = document.querySelector("#graph_canvas").clientHeight margin = { top:0, left:0, bottom:0, right:0 } chartWidth = width - (margin.left+margin.right) chartHeight = height - (margin.top+margin.bottom) svg.attr("width", width).attr("height", height) chartLayer .attr("width", chartWidth) .attr("height", chartHeight) .attr("transform", "translate("+[margin.left, margin.top]+")") } function drawChart(data) { var STEM_LENGTH=30 var simulation = d3.forceSimulation() .force("link", d3.forceLink().id(function(d) { return d.index })) .force("collide", d3.forceCollide(function(d) { return d.r + STEM_LENGTH }) .iterations(16) ) .force("charge", d3.forceManyBody()) .force("center", d3.forceCenter(chartWidth / 2, chartHeight / 2)) .force("y", d3.forceY(0)) .force("x", d3.forceX(0)) var link = svg.append("g") .attr("class", "links") .selectAll("line") .data(data.links) .enter() .append("line") .attr("stroke", "brown") .attr("stroke-width", function(d) { return d.line_width }) var node_label = svg.append("g") .attr("class", "nodes") .selectAll("g") .data(data.nodes) .enter().append("g") .call(d3.drag() .on("start", dragstarted) .on("drag", dragged) .on("end", dragended)); var node = node_label.append("circle") .attr("r", function(d) { return d.r }) .attr("fill", function(d) { return (d.freq > 60.0) ? "moccasin" : (d.freq > 20.0) ? "lemonchiffon" : (d.freq > 5.0) ? "beige" : "lavender" }); var label = node_label.append("text") .attr("text-anchor", "middle") .attr("font-family", "Arial") .attr("dy", "0.5em") .attr("font-size", function(d) {return d.r / 1.5; }) .text(function(d) { return d.word; }) var ticked = function() { link.attr("x1", function(d) { return d.source.x; }) .attr("y1", function(d) { return d.source.y; }) .attr("x2", function(d) { return d.target.x; }) .attr("y2", function(d) { return d.target.y; }); node_label.attr("transform", function(d) { return "translate("+d.x+","+d.y+")"; }) } simulation.nodes(data.nodes).on("tick", ticked); simulation.force("link").links(data.links); function dragstarted(d) { if (!d3.event.active) { simulation.alphaTarget(0.1).restart(); } d.fx = d.x; d.fy = d.y; } function dragged(d) { d.fx = d3.event.x; d.fy = d3.event.y; } function dragended(d) { if (!d3.event.active) simulation.alphaTarget(0); d.fx = null; d.fy = null; } } } |
著者:しょっさん
ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。第8回は、第1回で述べた「クリーンアーキテクチャ」に習って、ロジックと、フレームワークやライブラリ、その他の処理を分離します。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図1 経費精算申請を処理しているコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; import { Expense } from "../models/expense"; const router = Express.Router(); // POST 経費の入力 router.post("/", (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { Expense.create(req.body) .then((result) => { res.status(200).json(result); }) .catch((err) => { console.log(err); res.status(400).json({ id: 20002, message: err }); }); }); |
図3 「User Entity」オブジェクト
|
1 2 3 4 5 6 |
class User { id: number; name: string; salaray: number; } |
図5 「common/index.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
export enum approval_status { minimum, unapproved, approved, reject, reimburse, maximum, } // エンティティ用のオブジェクトの基本構成 export abstract class EntityObject<T> { protected props: T; protected constructor(props: T) { this.props = props; } } // プリミティブ型のビジネスルール実装のための基本構成 export abstract class PrimitiveObject<T> extends EntityObject<T> { get value(): T { return this.props; } } |
図6 「domains/expenseEntity.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |
import { EntityObject, approval_status, PrimitiveObject } from "../common"; export const MAX_LENGTH = 64; export const MAX_AMOUNT = 1000000; // 費目名のルール class Type extends PrimitiveObject<string> { static create(value: string): Type { if (value.length > MAX_LENGTH || value.length <= 0) throw new Error("費目名が長すぎるか、ありません"); return new Type(value); } } // 承認コードのルール class Approval extends PrimitiveObject<approval_status> { static create(value: approval_status = approval_status.unapproved): Approval { if (value <= approval_status.minimum || value >= approval_status.maximum) throw new Error("承認コードがおかしい"); return new Approval(value); } } // 請求金額のルール class Amount extends PrimitiveObject<number> { static create(value: number): Amount { if (value <= 0 || value >= MAX_AMOUNT) throw new Error("請求金額が範囲を超えている"); return new Amount(value); } } // 経費精算で利用されるクラスの実態 interface IExpenseProps { id?: number | undefined; user_id: string; user_name?: string; date: Date; type: Type; description?: string | null; approval: Approval; amount: Amount; } // オブジェクトを構成する要素 export interface IExpenseValue { id?: number | undefined; user_id: string; user_name?: string; date: Date; type: string; description?: string | null; approval: approval_status; amount: number; } export class ExpenseEntity extends EntityObject<IExpenseProps> { constructor(props: IExpenseProps) { super(props); } set approval(status: approval_status) { this.props.approval = Approval.create(status); } static create(values: IExpenseValue): ExpenseEntity { return new ExpenseEntity({ id: values.id, user_id: values.user_id, user_name: values.user_name, date: values.date, type: Type.create(values.type), description: values.description, approval: Approval.create(values.approval), amount: Amount.create(values.amount), }); } public read(): IExpenseValue { return { id: this.props.id, user_id: this.props.user_id, user_name: this.props.user_name, date: this.props.date, type: this.props.type.value, description: this.props.description, approval: this.props.approval.value, amount: this.props.amount.value, }; } } |
図7 「usecases/SubmitExpense.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
import { IExpenseRepository } from "./IExpenseRepository"; import { ExpenseEntity, IExpenseValue } from "../domains/expenseEntity"; export class SubmitExpense { private _expenseRepository: IExpenseRepository; constructor(expenseRepository: IExpenseRepository) { this._expenseRepository = expenseRepository; } execute(expense: IExpenseValue) { const e = ExpenseEntity.create(expense); return this._expenseRepository.store(e); } } |
図8 「usecases/IExpenseRepository.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
import { ExpenseEntity } from "../domains/expenseEntity"; export interface IExpenseRepository { findAllApproved(): Promise<ExpenseEntity[]>; findAllRejected(): Promise<ExpenseEntity[]>; findUnapproval(id: string): Promise<ExpenseEntity[]>; updateApproval(id: number, expense: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity>; findById(id: number): Promise<ExpenseEntity>; update(expense: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity>; store(expense: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity>; } |
図9 「interfaces/ExpenseController.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
import { SubmitExpense } from "../usecases/SubmitExpense"; import { IExpenseValue } from "../domains/expenseEntity"; import { ExpenseRepository } from "./expenseRepository"; export class ExpenseController { async submitExpenseController(expense: IExpenseValue): Promise<IExpenseValue> { const expenseRepository = new ExpenseRepository(); try { const usecase = new SubmitExpense(expenseRepository); const result = await usecase.execute(expense); return result.read(); } catch (error) { throw new Error(error); } } } |
図10 「interfaces/ExpenseRepository.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
import { Expense } from "../../models/expense"; import { approval_status } from "../common"; import { ExpenseEntity } from "../domains/expenseEntity"; import { IExpenseRepository } from "../usecases/IExpenseRepository"; export class ExpenseRepository implements IExpenseRepository { findAllApproved(): Promise<ExpenseEntity[]> { return Expense.findAll({ where: { approval: approval_status.approved, }, }).then((results) => { return results.map((value, index, array) => { return ExpenseEntity.create(value); }); }); } (略) store(e: ExpenseEntity): Promise<ExpenseEntity> { return Expense.create(e.read()) .then((result) => { return ExpenseEntity.create(result); }) .catch((err) => { throw new Error("請求処理が失敗しました"); }); } } |
図11 「expense.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
// POST 経費の入力 router.post("/", (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { const e = new ExpenseController(); e.submitExpenseController(req.body!) .then((result) => { res.status(200).json(result); }) .catch((err) => { res.status(400).json({ id: "20201", message: err }); }); }); |
図13 「index.ts」ファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
// API app.use("/api/auth", auth); app.use("/api/expense", Authorization.isAuthorized, expense); app.use( "/api/payment", Authorization.isAuthorized, Authorization.isAccounting, payment ); app.use( "/api/approval", Authorization.isAuthorized, Authorization.isBoss, approval ); |
著者:山下 賢治
初めまして。香川大学 工学研究科 修士1年の山下賢治です。今回は、JavaScriptライブラリ「React」と、API向けのクエリー言語「GraphQL」を用いて、GitHubで公開されているリポジトリの検索Webアプリケーションを作成します。リポジトリの絞り込みには、開発言語とスター数を利用します。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 「src/auth.js」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
import { ApolloClient, createHttpLink, InMemoryCache } from '@apollo/client'; import { setContext } from '@apollo/client/link/context'; const httpLink = createHttpLink({ uri: 'https://api.github.com/graphql', }); const authLink = setContext(() => { const TOKEN = process.env.REACT_APP_TOKEN; return { headers: { Authorization: `Bearer ${TOKEN}`, }, }; }); export const client = new ApolloClient({ link: authLink.concat(httpLink), cache: new InMemoryCache(), }); |
図4 「src/index.js」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom'; import { ApolloProvider } from '@apollo/client'; import { client } from './auth'; import RepoInfo from './components/RepoInfo'; import * as serviceWorker from './serviceWorker'; ReactDOM.render( <React.StrictMode> <ApolloProvider client={client}> <RepoInfo /> </ApolloProvider> </React.StrictMode>, document.getElementById('root') ); // If you want your app to work offline and load faster, you can change // unregister() to register() below. Note this comes with some pitfalls. // Learn more about service workers: https://bit.ly/CRA-PWA serviceWorker.unregister(); |
図5 「src/graphql/index.js」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
import { gql } from '@apollo/client'; export const SEARCH_REPO = gql` query getData($queryString: String!) { search(query: $queryString, type: REPOSITORY, first: 10) { nodes { ... on Repository { databaseId nameWithOwner openGraphImageUrl } } } } `; |
図6 「src/components/RepoInfo.jsx」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
import React, {useState, useEffect, useCallback} from 'react'; import {useLazyQuery} from '@apollo/client'; import { SEARCH_REPO } from '../graphql'; const useRepoData = () => { const [getData, {loading, error, data}] = useLazyQuery(SEARCH_REPO) const [query, setQuery] = useState('') const fetchData = useCallback(() => { getData({ variables: { queryString: query } }); }, [getData, query]); useEffect(() => { fetchData() }, [fetchData]) return [setQuery, {loading, error, data}] } const RepoInfo = () => { const [fetchData, {loading, error,data}] = useRepoData() const handleOnClick = () => { fetchData(`language:python stars:>100`) } if (loading) return <p>Loading Repository</p> if (error) return <p>Error while searching Repository</p> return ( <> <button onClick={handleOnClick}> search </button> { data ? data.search.nodes.map( repo => <div key={repo.databaseId}> <h2>{repo.nameWithOwner}</h2> <img src={repo.openGraphImageUrl} alt='repoImage' /> </div> ) : <></> } </> ) } export default RepoInfo; |
図9 変更後の「src/components/RepoInfo.jsx」ファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
import React, {useState, useEffect, useCallback} from 'react'; import {useLazyQuery} from '@apollo/client'; import { SEARCH_REPO } from '../graphql'; const useInput = initialValue => { const [value, set] = useState(initialValue) return {value, onChange: (e) => set(e.target.value)} } const useRepoData = () => { const [getData, {loading, error, data}] = useLazyQuery(SEARCH_REPO) const [query, setQuery] = useState('') const fetchData = useCallback(() => { getData({ variables: { queryString: query } }); }, [getData, query]); useEffect(() => { fetchData() }, [fetchData]) return [setQuery, {loading, error, data}] } const RepoInfo = () => { const stars = useInput(0) const language = useInput('') const [fetchData, {loading, error,data}] = useRepoData() const handleOnClick = () => { fetchData(`language:${language.value} stars:>${stars.value}`) } if (loading) return <p>Loading Repository</p> if (error) return <p>Error while searching Repository</p> return ( <> <label> Language : <input type='text' {...language} /> </label> <label> More than : <input type='text' {...stars} /> Stars </label> <button onClick={handleOnClick}> search </button> { data ? data.search.nodes.map( repo => <div key={repo.databaseId}> <h2>{repo.nameWithOwner}</h2> <img src={repo.openGraphImageUrl} alt='repoImage' /> </div> ) : <></> } </> ) } export default RepoInfo; |
著者:小杉 研太
前回(第3回)に引き続き、アプリやデータの連携を実現するためのミドルウエア製品「Red Hat Integration」を紹介します。第4回はRed Hat Integrationに含まれる「Red Hat AMQ」と「Red Hat Fuse」のアップストリームとなる「Strimzi」と「Apache Camel」について触れます。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図17 KafkaとSlackを統合できるコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
FromKafkaToSlack.java import org.apache.camel.builder.RouteBuilder; import org.apache.camel.component.slack.SlackComponent; public class FromKafkaToSlack extends RouteBuilder { @Override public void configure() throws Exception { final SlackComponent slackComponent = (SlackComponent) this.getContext().getComponent("slack"); slackComponent.setWebhookUrl(Webhook URL); from("kafka:my-topic?brokers=my-cluster-kafka-bootstrap:9092") .routeId("from-kafka-to-slack") .to("slack:#my-kafka-project"); } } |
著者:米田 聡
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けにさまざまな拡張ボードが発売されています。その拡張ボードとラズパイを組み合わせれば、ラズパイでいろいろなことが簡単に試せます。第1回は、電子ペーパーディスプレイ搭載の拡張基板を扱います。
シェルスクリプトマガジン Vol.68は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図3 電子ペーパーディスプレイに文字を表示するサンプルプログラム(text.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
from inky import Inky from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw DEFAULT_FONT = '/usr/share/fonts/truetype/fonts-japanese-gothic.ttf' FONT_SIZE = 24 LINE_HEIGHT = 26 ink = Inky() # 2値イメージの作成 image = Image.new('P',(ink.width, ink.height)) draw = ImageDraw.Draw(image) font = ImageFont.truetype(DEFAULT_FONT, FONT_SIZE) # 文字描画 draw.text((0, 0), "シェルスクリプト" , font=font, fill=1) draw.text((0,26), "マガジン" , font=font, fill=1) draw.text((0,52), "ゼロ・ワンシリーズ", font=font, fill=1) draw.text((0,78), "電子ペパーモニタ" , font=font, fill=1) # セットして表示 ink.set_image(image) ink.show() |
図5 電子ペーパーディスプレイに画像を表示するサンプルプログラム(logo.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
from inky import Inky from PIL import Image ink = Inky() img = Image.open("shelllogo.png") # サイズ変換 img = img.resize((ink.width, ink.height)) # 2値画像への変換 img = img.convert('1', dither=True) # セットして表示 ink.set_image(img) ink.show() |
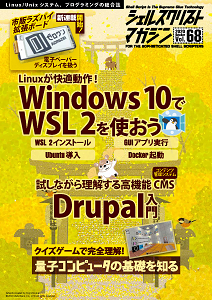
004 レポート 暗号通信のTLS1.2以前に脆弱性
005 NEWS FLASH
008 特集1 Windows 10でWSL 2を使おう/三沢友治
020 特集2 高機能CMS Drupal入門/小薗井康志
034 特別企画 量子コンピュータの基礎を知る/沼田祈史、小林有里
046 Raspberry Piを100%活用しよう/米田聡 コード掲載
049 Hello Nogyo!
050 レッドハットのプロダクト/小杉研太 コード掲載
059 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
064 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
066 香川大学SLPからお届け!/山下賢治 コード掲載
072 RPA/桑原滝弥、イケヤシロウ
074 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載
084 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
086 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
092 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
100 Techパズル/gori.sh
102 コラム「人生の入り口」/シェル魔人
Linuxを使ってみたいと思っても環境を用意するのはかなりの手間です。しかし、その状況は変わりつつあります。パソコンのOSとしてデファクトスタンダード(事実上の標準)となる「Windows」を開発している米Microsoft社が、Linuxに関連する技術やソフトウエアに対して積極的に取り組んでいるからです。
そこで、特集1では、Windows 10の標準機能となった、WindowsとLinuxを一緒に動作させるための仕組み「Windows Subsystem for Linux」(WSL)を取り上げます。2020年5月に登場したWSL 2では、Linuxとして使える機能や性能が大幅に向上しています。本特集では、このWSL 2のインストールおよび、Linuxディストリビューション「Ubuntu」の導入、GUIアプリの実行、Dockerの起動などのやり方を初心者にも分かりやすく解説しています。
特集2では、コンテンツ管理システム(CMS)の「Drupal」を紹介しています。このDrupalは、簡単に導入してそのまま使えるだけでなく、高い拡張性によりカスタマイズして使えます。米国の政府機関、米Johnson & Johnson社などの製薬会社、米IBM社や米Red Hat社といったIT企業などのWebサイトで利用されている本格的なものです。
特別企画では、最近話題の「量子コンピュータ」を扱いました。量子コンピュータは、現在のコンピュータと異なる仕組みや原理で動いています。簡単な計算の処理を理解するだけでも一苦労です。そこで「Minecraft」風のクイズゲームで楽しみながら、量子コンピュータについて学びましょう。
このほか、Raspberry Pi(ラズパイ)に関する新連載、詩とアートを組み合わせたIT用語の連載も開始しました。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.68。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
WSL 2ですが、Windows 10 May 2020 Updateを適用したWindows 10 バージョン2004以降だけでなく、バージョン1909や1903にもバックポートされて使えるようになりました。詳しくは、こちらを参照してください。
情報は随時更新致します。
著者:山内 真仁
以前、ゲームエンジン「Unity」を使ったレースゲームをSLPのチーム活動で
作成しました。その経験を生かして今回は、Unityとプログラミング言語「C#」を使って、簡単なレースゲームを作成する方法を紹介します。Unityの物理エンジンを使用することで、複雑なコードを書かなくてもリアルな挙動のゲームを作成できます。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図12 「CarController.cs」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
using UnityEngine; public class CarController : MonoBehaviour { public GameObject[] wheelMeshes = new GameObject[4]; // ホイールオブジェクトを格納する配列 public WheelCollider[] wheelColliders = new WheelCollider[4]; // Wheel Colliderを格納する配列 public float maxMotorTorque = 300f; // 車輪に加える最大トルク public float brakeTorque = 500f; // ブレーキのトルク public float maxSteerAngle = 25f; // ステアリングの最大舵角 float accel, steer; // アクセルとステアリングの入力値 bool brake; // ブレーキをかけているかどうか // 画面を描画するたびに実行されるメソッド(実行間隔はフレームレートに依存) void Update() { steer = Input.GetAxis("Horizontal"); // ←→で旋回 accel = Input.GetAxis("Vertical"); // ↑↓でアクセル brake = Input.GetKey(KeyCode.Space); // スペースでブレーキ // Wheel Colliderの動きを見た目に反映する for (int i = 0; i < 4; i++) { wheelColliders[i].GetWorldPose(out Vector3 position, out Quaternion rotation); wheelMeshes[i].transform.position = position; wheelMeshes[i].transform.rotation = rotation; } } // フレームレートに依存せず、定期的に実行されるメソッド(0.02秒に1回) void FixedUpdate() { // Wheel Colliderに各パラメータを代入 for(int i = 0; i < 4; i++) { if (i < 2) wheelColliders[i].steerAngle = steer * maxSteerAngle; // ステアリング(前輪) wheelColliders[i].motorTorque = accel * maxMotorTorque; // アクセル wheelColliders[i].brakeTorque = brake ? brakeTorque : 0f; // ブレーキ } } } |
図14 CarController.csファイルに追加する記述
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
GameObject brakeLight, headLight; // ランプ類のオブジェクトを格納する変数 // ゲーム開始時に1回のみ実行されるメソッド void Start() { // ランプ類のオブジェクトを探して取得 brakeLight = GameObject.Find("SkyCarBrakeLightsGlow"); headLight = GameObject.Find("SkyCarHeadLightsGlow"); } void Update() { // ランプ類の点灯・消灯 brakeLight.SetActive(brake); if (Input.GetKeyDown(KeyCode.H)) { headLight.SetActive(!headLight.activeSelf); } |
図16 「Timer.cs」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
using UnityEngine; using UnityEngine.UI; using UnityEngine.SceneManagement; public class Timer : MonoBehaviour { public Text timeText; // タイム表示用のテキスト float startTime; // 計測開始の時刻 bool start, check, goal; // 各地点の通過フラグ void Start() { // オブジェクトのコンポーネントを取得 timeText = GameObject.Find("TimeText").GetComponent<Text>(); timeText.text = "TIME 00.000"; // テキストの初期化 } void Update() { // スタートしてからゴールするまでタイムを表示 if (!goal && start) timeText.text = "TIME " + (Time.time - startTime).ToString("00.000"); // ゴール後に[R]キーを押すとリスタート if (goal && Input.GetKey(KeyCode.R)) SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name); } // トリガーオブジェクトに侵入した時に呼び出されるメソッド void OnTriggerEnter(Collider other) { if (other.gameObject.name == "StartPoint") { if (check) { goal = true; // チェックポイント通過済みならゴール timeText.color = Color.red; } else if (!start && !check) { start = true; // チェックポイントを通過していない場合、タイム計測開始 startTime = Time.time; } } else if (start && other.gameObject.name == "CheckPoint") check = true; // チェックポイントを通過 } } |
著者:しょっさん
ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。第7回は、JavaScriptフレームワーク「Vue.js」でアプリを作成し、テストとリリースの方法を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 Vue.js および各ライブラリを利用するための定義(simple.htmlから抜粋)
|
1 2 3 4 |
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.11"></script> <script src="https://unpkg.com/vue-router@3.3.2/dist/vue-router.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios@0.19.2/dist/axios.min.js"></script> <script src="./jwt-decode.min.js"></script> |
図3 Vue RouterのHTMLファイル側の定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
<div id="app"> <h1>経費精算アプリケーション(Vue.js)</h1> <router-link to="/expense">経費登録</router-link> <router-link to="/payment">経費精算</router-link> <router-link to="/login">ログイン</router-link> <router-link to="/logout">ログアウト</router-link> <router-view /> </div> |
図4 Vue RouterのJavaScript側の定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
const router = new VueRouter({ routes: [ // 精算処理 { path: "/expense", }, // 支払処理 { path: "/payment", }, // 認証 - ログイン { path: "/login", }, // 認証 - ログアウト { path: "/logout", }, // どのURLにも該当しなかった場合 { path: "*", redirect: "/expense", }, ], }); |
図5 認証部分のVueコンポーネントとVue Router定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |
const Login = { template: "#login", data: function () { return { user: localStorage.user || "", password: localStorage.password || "", remember: localStorage.remember || false, error: false, }; }, methods: { login: function () { axios .post(`${baseUrl}/api/auth`, { user: this.user, password: this.password, }) .then((response) => { if (response.status === 200) { // ログインが成功した場合は、ローカルストレージにトークンを保管する(ログインが成功した状態とする) this.error = false; localStorage.token = response.data.token; // "remember me" チェックボックスが付いていたら、各々の入力項目を保管する if (this.remember) { localStorage.user = this.user; localStorage.password = this.password; localStorage.remember = true; } else { // 逆にオフであれば入力項目の内容を破棄する delete localStorage.user; delete localStorage.password; delete localStorage.remember; } // ログイン成功したら /expense へ切り替える this.$router.replace("/expense"); } else { this.error = true; } }) .catch((response) => { this.error = true; this.remember = false; console.log(response); }); }, }, }; const router = new VueRouter({ routes: [ (略) // ログイン画面 { path: "/login", component: Login, }, // ログアウト処理 { path: "/logout", beforeEnter: (to, from, next) => { delete localStorage.token; next("/login"); }, }, ], }); |
図6 認証部分のHTMLテンプレート
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
<script type="text/x-template" id="login"> <form @submit.prevent="login"> <input v-model="user" type="email" placeholder="Your Email" autofocus="" /> <input v-model="password" type="password" placeholder="Your Password" /> <button type="submit">ログイン</button> </form> <div v-show="error"> <p>ログイン失敗</p> </div> </script> |
図7 請求処理ののVueコンポーネントとVue Router定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
const Expense = { template: "#expense", data: function () { let decoded = {}; if (localStorage.token) { // トークン内のユーザー情報を基に変数へ配置 decoded = jwt_decode(localStorage.token); } return { user: decoded.email || "", id: decoded.id || "", user_name: decoded.user_name || "", date: "", type: "", amount: "", description: "", error: false, }; }, // 経費を登録するメソッド methods: { expense: function () { axios .post( `${baseUrl}/api/expense`, { user: this.user, user_id: this.id, user_name: this.user_name, date: this.date, type: this.type, amount: this.amount, description: this.description, }, { headers: { Authorization: `Bearer ${localStorage.token}`, }, } ) .then((response) => { if (response.status === 200) { // 正常に登録できた場合は、変更が伴うフィールドをクリアーして、再度入力可能な状態にする this.error = false; console.log(response); this.date = ""; this.type = ""; this.amount = ""; this.description = ""; } }) .catch((response) => { this.error = true; console.log(response); }); }, }, }; const router = new VueRouter({ routes: [ // 経費登録 { path: "/expense", component: Expense, beforeEnter: (to, from, next) => { // 認証前の場合は /login ページへ遷移する if (!localStorage.token) { next({ path: "/login", query: { redirect: to.fullPath }, }); } else { next(); } }, }, (略) }); |
図8 請求処理のHTMLテンプレート
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
<script type="text/x-template" id="expense"> <div> <form @submit.prevent="expense"> <input v-model="user_name" type="text" placeholder="Your Name" /> <input v-model="user" type="email" placeholder="Your Email" /> <input v-model="id" type="hidden" placeholder="Your User ID" /> <input v-model="date" type="datetime-local" placeholder="経費利用日" autofocus="" /> <input v-model="type" type="text" placeholder="費目" /> <input v-model="amount" type="number" placeholder="金額" /> <input v-model="description" type="text" placeholder="費用詳細" /> <button type="submit">経費申請</button> </form> <p v-if="error" class="error">経費登録失敗</p> </div> </script> |
図9 支払処理のVueコンポーネントとVue Router定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 |
// 経費リストを axios を利用して取得する関数 const getPayments = function (callback) { axios .get(`${baseUrl}/api/payment`, { // JWTの認可ヘッダー headers: { Authorization: `Bearer ${localStorage.token}`, }, }) .then((response) => { if (response.status === 200) { // "response.data" 配下に経費リストが含まれる callback(null, response.data); } else { callback(true, response); } }) .catch((response) => { callback(true, response); }); }; // 経費リスト用の Vueコンポーネント const Payment = { template: "#payment", data: function () { return { loading: false, error: false, payments: function () { return []; }, }; }, // 初期化されたときにデータを取得する created: function () { this.fetchData(); }, // ルーティングが変更されてきたときに再度データを取得する watch: { $route: "fetchData", }, // 経費データを取得するメソッドのメイン部分 methods: { fetchData: function () { this.loading = true; getPayments( function (err, payments) { this.loading = false; if (!err) this.payments = payments; else this.error = true; }.bind(this) ); }, }, }; const router = new VueRouter({ routes: [ (略) { path: "/payment", component: Payment, beforeEnter: (to, from, next) => { // 認証前の場合は /login ページへ遷移する if (!localStorage.token) { next({ path: "/login", query: { redirect: to.fullPath }, }); } else { next(); } }, }, (略) ], }); |
図10 支払処理のHTMLテンプレート
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
<script type="text/x-template" id="payment"> <div> <table> <tr> <th>ユーザー名</th> <th>発生日</th> <th>費目</th> <th>経費</th> <th>詳細</th> </tr> <tr v-for="payment in payments"> <td>{{payment.user_name}}</td> <td>{{payment.date}}</td> <td>{{payment.type}}</td> <td>{{payment.amount}}</td> <td>{{payment.description}}</td> </tr> </table> <div class="loading" v-if="loading">アクセス中...</div> <p v-if="error" class="error">経費取得失敗</p> </div> </script> |
図14 controllers/auth/authentication.tsファイルの追加・改修部分
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
import jwt from "jsonwebtoken"; export class Authentication { (略) static verifyLocal(username: string, password: string, done: any) { User.findOne({ where: { email: username, deleted_at: null, }, }) .then((user) => { if (user && bcrypt.compareSync(password, user.hash)) { const opts = { issuer: process.env.ISSUER, audience: process.env.AUDIENCE, expiresIn: process.env.EXPIRES, }; const secret: string = process.env.SECRET || "secret"; const token: string = jwt.sign( { email: user.email, id: user.id, user_name: user.last_name + " " + user.first_name, }, secret, opts ); return done(null, token); } return done(true, "authentication error"); }) .catch((err) => done(true, err)); } (略) } |
図15 controllers/auth/authorization.tsファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import { User } from "../../models/user"; import passport from "passport"; import { Strategy as JWTStrategy, ExtractJwt } from "passport-jwt"; export class Authorization { // JWTトークンで該当するユーザーの有無をチェック static verifyJWT(req: Request, jwt_payload: any, done: any) { User.findOne({ where: { email: jwt_payload.email, deleted_at: null, }, }).then((user) => { if (!user) return done(null, false); return done(null, user.get()); }); } // JWT Strategyの定義 static setJWTStrategy() { const field = { jwtFromRequest: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(), issuer: process.env.ISSUER, audience: process.env.AUDIENCE, secretOrKey: process.env.SECRET || "secret", passReqToCallback: true, }; passport.use(new JWTStrategy(field, this.verifyJWT)); } // 認可チェック static isAuthorized(req: Request, res: Response, next: NextFunction) { passport.authenticate("jwt", { session: false }, (err, user) => { if (err) { res.status(401).json({ status: "10001" }); } if (!user) { res.status(401).json({ status: "10002" }); } else { return next(); } })(req, res, next); } } |
図16 API用のモジュールとルーティング定義
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
// API用ルーティング先のモジュール import auth from "./api/auth"; import payment from "./api/payment"; import expense from "./api/expense"; // APIルーティング app.use("/api/auth", auth); app.use("/api/expense", Authorization.isAuthorized, expense); app.use("/api/payment", Authorization.isAuthorized, payment); |
図18 請求処理(/api/expense.ts)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; import { Expense } from "../models/expense"; const router = Express.Router(); // POST 経費の入力 router.post("/", (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { Expense.create(req.body) .then((result) => { res.status(200).json(result); }) .catch((err) => { console.log(err); res.status(400).json({ id: 20002, message: err }); }); }); export default router; |
図19 支払処理(/api/payment.ts)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; import { Expense } from "../models/expense"; const router = Express.Router(); // POST / ユーザーの認証処理 router.get("/", (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { Expense.findAll() .then((results) => { res.status(200).json(results); }) .catch((err) => { res.status(400).json({ id: 20011, message: err }); }); }); export default router; |
図35 修正した/src/index.tsファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 |
import { Request, Response, NextFunction } from "express"; import Express from "express"; const app = Express(); import logger from "morgan"; import { Authentication } from "./controllers/auth/authentication"; import { Authorization } from "./controllers/auth/authorization"; app.use(logger("dev")); app.use(Express.json()); app.use(Express.urlencoded({ extended: true })); Authentication.initialize(app); Authentication.setLocalStrategy(); Authorization.setJWTStrategy(); app.use(Express.static("htdocs")); // API用ルーティング import auth from "./api/auth"; import payment from "./api/payment"; import expense from "./api/expense"; // API app.use("/api/auth", auth); app.use("/api/expense", Authorization.isAuthorized, expense); app.use("/api/payment", Authorization.isAuthorized, payment); app.use((req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { var err: any = new Error("Not Found"); err.status = 404; next(err); }); // error handler app.use((err: any, req: Request, res: Response, next: NextFunction) => { res.locals.message = err.message; res.locals.error = req.app.get("env") === "development" ? err : {}; res.status(err.status || 500); res.json(err); }); const port = process.env.PORT || 3000; app.listen(port, () => { console.log(`http://localhost:${port}`); }); export default app; |
著者:飯尾 淳
前回に引き続き、筆者らの研究グループが開発したTwitterのトレンド分析システムについて解説します。前回は、そもそもTwitterのトレンドとは何かから始まり、開発者登録をしてトレンドAPIを叩き、そのリストを収集する方法まで説明しました。今回は、トレンドをキーにしてツイートを取得する方法と、ツイート群を対象として共起ネットワークグラフを作る方法を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 トレンドを収集して分析するプログラムのコード(その1)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
#!/usr/bin/env python ########################################################### # ヘルパーファンクション ########################################################### import re # 特殊文字をエスケープする def escape(s, quoted=u'\'"\\', escape=u'\\'): return re.sub(u'[%s]' % re.escape(quoted), lambda mo: escape + mo.group(), s) # ノードのプリティプリンタ def pp_node(ary_of_nodes): for node in ary_of_nodes: keyword = escape(node[0]) frequency = node[1] print("node_hash['{0}'] = trend.nodes.create(word: '{1}', freq: {2:6.2f})" .format(keyword, keyword, frequency)) # リンクのプリティプリンタ def pp_link(ary_of_links): for link in ary_of_links: (kw1,kw2) = link[0].split(',') print("link = Link.create(corr: {0:6.2f})".format(link[1])) print("node_hash['{0}'].links << link".format(escape(kw1))) print("node_hash['{0}'].links << link".format(escape(kw2))) # 値を正規化する。p_fragは百分率とするときTrue def normalize(hash_obj, p_flag): maxval = max(hash_obj, key=lambda x: x[1])[1] factor = 100 if p_flag else 1 return [(x[0], x[1] / maxval * factor) for x in hash_obj] |
図5 トレンドを収集して分析するプログラムのコード(その2)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
########################################################### # ワードグラフの作成 ########################################################### import MeCab # 「PATH_TO_MECAB_NEOLOGD」の部分は環境に合わせて修正 m = MeCab.Tagger("-d PATH_TO_MECAB_NEOLOGD") stopwords = {'*', 'HTTPS', 'HTTP', 'WWW', 'の', 'ん', 'ン', 'ω', '???'} def create_graph(keyword, collected, tweets): ary_of_ary = [] for tweet in tweets: ary = [] lines = m.parse(tweet).split('\n') for line in lines: if line.count('\t') == 0: continue (kw, prop) = line.split('\t') props = prop.split(',') if len({props[-3]} & stopwords) > 0: continue if props[1] == '固有名詞': ary.append(props[-3]) ary_of_ary.append(ary) KW_THRESHOLD = 20 kw_dict = {} counter = 0 for ary in ary_of_ary: for kw in ary: if kw in kw_dict: kw_dict[kw] = kw_dict[kw] + 1.0 else: kw_dict[kw] = 1.0 counter = counter + 1 for kw,val in kw_dict.items(): kw_dict[kw] = val / counter * 100 if len(kw_dict) > 0: kw_dict = sorted(kw_dict.items(), key = lambda x: x[1], reverse = True)[0:KW_THRESHOLD-1] kw_dict = normalize(kw_dict, True) print("node_hash = {}") print("trend = Trend.create(label: '{0}', collected:'{1}')" .format(escape(keyword), collected)) pp_node(kw_dict) corr_dict = {} for src in kw_dict: for dst in kw_dict: if src == dst: continue src_w = src[0] dst_w = dst[0] sd_pair = src_w + "," + dst_w if sd_pair in corr_dict: continue prob = 0.0 for ary in ary_of_ary: if ((src_w in ary) & (dst_w in ary)): prob = prob + 1.0 prob = 100 * prob / len(ary_of_ary) if prob > 0: corr_dict[dst_w + "," + src_w] = prob if len(corr_dict) > 0: lk_dict = sorted(corr_dict.items(), key = lambda x: x[1], reverse = True) # 後半3/4をカットして短くする lk_dict = lk_dict[0:int(len(lk_dict)*1/4)] if len(lk_dict) > 0: lk_dict = normalize(lk_dict, True) pp_link(lk_dict) |
図6 トレンドを収集して分析するプログラムのコード(その3)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
########################################################### # すでに登録済みか否かのチェック ########################################################### import sqlite3 from contextlib import closing def has_been_registered(keyword, collected): # 「PATH_TO_THE_DATABASE_FILE」の部分は環境に合わせて修正 dbfile = "PATH_TO_THE_DATABASE_FILE(development.sqlite3)" with closing(sqlite3.connect(dbfile)) as conn: c = conn.cursor() sql = 'select label, collected from trends \ where label=? and collected=?' res = (keyword, collected) c.execute(sql, res) return (len(c.fetchall()) > 0) ########################################################### # メイン関数 ########################################################### from twitter import * from datetime import date def main(): # WOEID を希望の場所に合わせて指定。「23424856」は日本 woeid = 23424856 # アプリ登録時に取得した情報を下記に設定 CK = 'ADD_HERE_YOUR_CONSUMER_KEY' CS = 'ADD_HERE_YOUR_CONSUMER_SECRET' AT = 'ADD_HERE_YOUR_ACCESS_TOKEN' AS = 'ADD_HERE_YOUR_ACCESS_TOKEN_SECRET' twitter = Twitter(auth = OAuth(AT,AS,CK,CS)) results = twitter.trends.place(_id = woeid, exclude="hashtags") d = date.today() collected = d.strftime('%Y-%m-%d') for location in results: for trend in location["trends"]: keyword = trend["name"] if has_been_registered(keyword, collected): continue query_kw = keyword + " exclude:retweets exclude:nativeretweets" tw_rslts = twitter.search.tweets(q=query_kw, lang='ja', locale='ja', count=100) tw_ary = [] for tweet in tw_rslts["statuses"]: tw_ary.append(tweet["text"]) create_graph(keyword, collected, tw_ary) if __name__ == "__main__": main() |
図7 ワードグラフ作成部で出力されるRubyスクリプトの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
node_hash = {} trend = Trend.create(label: 'ホシガリス', collected:'2020-06-07') node_hash['アニポケ'] = trend.nodes.create(word: 'アニポケ', freq: 100.00) node_hash['ポケモン'] = trend.nodes.create(word: 'ポケモン', freq: 56.76) node_hash['ゴルーグ'] = trend.nodes.create(word: 'ゴルーグ', freq: 29.73) node_hash['思'] = trend.nodes.create(word: '思', freq: 18.92) (略) node_hash['ピカチュウ'] = trend.nodes.create(word: 'ピカチュウ', freq: 5.41) node_hash['パチリス'] = trend.nodes.create(word: 'パチリス', freq: 5.41) node_hash['スピアー'] = trend.nodes.create(word: 'スピアー', freq: 5.41) link = Link.create(corr: 100.00) node_hash['ポケモン'].links << link node_hash['アニポケ'].links << link link = Link.create(corr: 75.00) node_hash['ゴルーグ'].links << link node_hash['アニポケ'].links << link (略) link = Link.create(corr: 25.00) node_hash['マユルド'].links << link node_hash['ドクケイル'].links << link node_hash = {} trend = Trend.create(label: '孤独のグルメ', collected:'2020-06-07') (略) |
著者:杉本 拓
「Red Hat Integration」はアプリやデータの連携を実現するための、インテグレーションパターン、API 連携、API管理とセキュリティ、データ変換、リアルタイムメッセージング、データストリーミングなどを提供するオープンソース製品です。同製品には多くの機能が含まれていますが、本連載ではその概要と一部の機能を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図18 二つのdependencyを追加する
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
<dependency> <groupId>org.jboss.resteasy</groupId> <artifactId>resteasy-jackson2-provider</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>io.apicurio</groupId> <artifactId>apicurio-registry-utils-serde</artifactId> <version>1.2.1.Final</version> </dependency> |
図19 「AvroRegistryExample.java」ファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
package com.redhat.kafka.registry; import java.io.File; import java.io.IOException; import java.util.Random; import java.util.concurrent.TimeUnit; import javax.enterprise.context.ApplicationScoped; import org.apache.avro.Schema; import org.apache.avro.generic.GenericData; import org.apache.avro.generic.GenericData.Record; import org.eclipse.microprofile.reactive.messaging.Outgoing; import io.reactivex.Flowable; import io.smallrye.reactive.messaging.kafka.KafkaRecord; @ApplicationScoped public class AvroRegistryExample { private Random random = new Random(); private String[] symbols = new String[] { "RHT", "IBM", "MSFT", "AMZN" }; @Outgoing("price-out") public Flowable<KafkaRecord<String, Record>> generate() throws IOException { Schema schema = new Schema.Parser().parse( new File(getClass().getClassLoader().getResource("price-schema.avsc").getFile()) ); return Flowable.interval(1000, TimeUnit.MILLISECONDS) .onBackpressureDrop() .map(tick -> { Record record = new GenericData.Record(schema); record.put("symbol", symbols[random.nextInt(4)]); record.put("price", String.format("%.2f", random.nextDouble() * 100)); return KafkaRecord.of(record.get("symbol").toString(), record); }); } } |
図20 「price-schema.avsc」ファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
{ "type": "record", "name": "price", "namespace": "com.redhat", "fields": [ { "name": "symbol", "type": "string" }, { "name": "price", "type": "string" } ] } |
図21 登録されたAvroのスキーマ
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
{ "createdOn": 1575919739708, "modifiedOn": 1575919739708, "id": "prices-value", "version": 1, "type": "AVRO", "globalId": 4 } |
図22 プロパティファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
# Configuration file kafka.bootstrap.servers=localhost:9092 mp.messaging.outgoing.price-out.connector=smallrye-kafka mp.messaging.outgoing.price-out.client.id=price-producer mp.messaging.outgoing.price-out.topic=prices mp.messaging.outgoing.price-out.key.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer mp.messaging.outgoing.price-out.value.serializer=io.apicurio.registry.utils.serde.AvroKafkaSerializer mp.messaging.outgoing.price-out.apicurio.registry.url=http://localhost:8081/api mp.messaging.outgoing.price-out.apicurio.registry.artifact-id=io.apicurio.registry.utils.serde.strategy.TopicIdStrategy |
著者:米田 聡
シェルスクリプトマガジンでは、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けのセンサー搭載拡張ボード「ラズパイセンサーボード」を制作しました。最終回は、前回作成したスクリプトによって記録された温度と湿度をグラフ化して、Webブラウザで閲覧可能にします。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図1 サンプルのHTMLテンプレートファイル(~/webapp/templates/hello.html)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>こんにちは世界</title> </head> <body> <div>{{ text }}</div> </body> </html> |
図2 サンプルのWebアプリケーションスクリプト(~/webapp/hello.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
from flask import Flask, request, render_template app = Flask(__name__) @app.route('/' , methods=['GET','POST']) def index(): message = 'Hello, World' return render_template("hello.html", text=message) if __name__ == '__main__': app.run(host='0.0.0.0', port=5000) |
図4 トップページのテンプレートファイル(~/webapp/templates/index.html)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>温度・湿度グラフ化ツール</title> </head> <body> <div>グラフ化する日時の範囲を指定してください。</div> <form action="graph" method="post"> <div>開始日時</div> <input id="startdt" type="datetime-local" name="startdt" min="{{ mindt }}" max="{{ maxdt }}" required> <div>終了日時</div> <input id="enddt" type="datetime-local" name="enddt" min="{{ mindt }}" max="{{ maxdt }}" required> <div><input type="submit" value="実行"></div> </form> </body> </html> |
図5 テンプレートファイルからトップページを作成するスクリプト(~/webapp/app.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
from flask import Flask, request,render_template import sqlite3 import datetime DBNAME="weather.sqlite3" app = Flask(__name__) @app.route('/') def index(): conn = sqlite3.connect(DBNAME) cur = conn.cursor() sql = "SELECT min(dt) from bme" cur.execute(sql) conn.commit() res = cur.fetchone() m = datetime.datetime.fromisoformat(res[0]) mindt = m.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M") sql = "SELECT max(dt) from bme" cur.execute(sql) conn.commit() res = cur.fetchone() m = datetime.datetime.fromisoformat(res[0]) maxdt = m.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M") conn.close() return render_template("index.html", maxdt=maxdt, mindt=mindt) # ここに後でグラフ表示ページの関数を追加する if __name__ == '__main__': app.run(host='0.0.0.0', port=5000) |
図8 グラフを表示するページのテンプレートファイル(~/webapp/templates/graph.html)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>グラフ</title> </head> <body> <canvas id="bmeChart"></canvas> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.3/Chart.bundle.js"></script> <script> var elm = document.getElementById("bmeChart"); var bmeChart = new Chart(elm, { type: 'line', data: { labels: [ {% for d in data %} '{{ d[0] }}', {% endfor %} ], datasets: [ { label: '気温(度)', data:[ {% for d in data %} {{ d[1] }}, {% endfor %} ], borderColor: "rgba(255,0,0,1)", backgroundColor: "rgba(0,0,0,0)", }, { label: '湿度(%)', data: [ {% for d in data %} {{ d[2] }}, {% endfor %} ], borderColor: "rgba(0,255,0,1)", backgroundColor: "rgba(0,0,0,0)", }, ], }, options: { }, }); </script> </body> |
図9 app.pyに追加する関数
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
@app.route('/graph', methods=['POST']) def graph(): if request.method == 'POST': startdt = datetime.datetime.fromisoformat(request.form['startdt']) enddt = datetime.datetime.fromisoformat(request.form['enddt']) conn = sqlite3.connect(DBNAME) cur = conn.cursor() sql = "SELECT dt,temp,hum from bme where dt < " + "'" + enddt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") + "' and dt > '" + startdt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") + "'" cur.execute(sql) conn.commit() res = cur.fetchall() conn.close() # データ件数が200件以上なら100件台になるよう抑える if len(res) > 200: p = int(len(res) / 100) res = res[::p] return render_template("graph.html", data=res) |
著者:川嶋 宏彰
最近、プログラミング言語「Python」による自動化やデータ分析が注目されています。本特集では、Pythonと、Webブラウザを自動操作するためのライブラリ「Selenium WebDriver」を用いて、インターネットから取得できるオープンデータを例に、Webブラウザの自動操作方法およびデータ分析方法を分かりやすく紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.67は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 非headlessモードのサンプルコード(sample.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
import time from selenium import webdriver driver = webdriver.Chrome() driver.get('https://www.google.com/') time.sleep(5) search_box = driver.find_element_by_name('q') search_box.send_keys('ChromeDriver') search_box.submit() time.sleep(5) driver.quit() |
図7 headlessモードのサンプルコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument('--headless') options.add_argument('--disable-gpu') driver = webdriver.Chrome(options=options) driver.get('https://www.google.com/') print(driver.title) search_box = driver.find_element_by_name('q') search_box.send_keys('ChromeDriver') search_box.submit() print(driver.title) driver.save_screenshot('search_results.png') driver.quit() |
図24 Seleniumを用いた気温データの自動取得プログラム
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |
import time from pathlib import Path from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC from selenium.webdriver.support.select import Select # ダウンロード先フォルダの指定 dldir_path = Path('csv') # csv という名前のフォルダとする dldir_path.mkdir(exist_ok=True) # なければ作成 download_dir = str(dldir_path.resolve()) # 絶対パスを取得 print("download_dir: " + download_dir) options = webdriver.ChromeOptions() options.add_experimental_option('prefs', { # Chrome のオプションに 'download.default_directory': download_dir # 絶対パスで指定 }) driver = webdriver.Chrome(options=options) wait = WebDriverWait(driver, 10) # 明示的待機用 (Timeout 10秒) # 自動操作開始 driver.get('https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php') # 「地点を選ぶ」 xpath = '//div[@class="prefecture" and text()="東京"]' time.sleep(2) driver.find_element_by_xpath(xpath).click() xpath = '//div[@class="station" and contains(@title, "地点名:東京")]' time.sleep(2) # (★) driver.find_element_by_xpath(xpath).click() # (★) # 「項目を選ぶ」 driver.find_element_by_id('elementButton').click() xpath = '//span[text()="月別値"]/preceding-sibling::input' time.sleep(2) driver.find_element_by_xpath(xpath).click() css = '#日最高気温の平均' time.sleep(2) driver.find_element_by_css_selector(css).click() # 「期間を選ぶ」 driver.find_element_by_id('periodButton').click() time.sleep(2) # <select>内の<option>要素を選択 Select(driver.find_element_by_name('iniy')).select_by_value('2010') Select(driver.find_element_by_name('inim')).select_by_value('1') time.sleep(2) # いったん止めてみる Select(driver.find_element_by_name('endy')).select_by_value('2019') Select(driver.find_element_by_name('endm')).select_by_value('12') time.sleep(2) # 「CSVファイルをダウンロード」 driver.find_element_by_id('csvdl').click() time.sleep(2) driver.quit() |
図27 e-StatのAPI機能を利用した家計調査データを取得するプログラム
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |
import sys import urllib import urllib.request import json import calendar import matplotlib.pyplot as plt import japanize_matplotlib # japanize-matplotlib を使う場合 import pandas as pd from scipy import stats url = 'https://api.e-stat.go.jp/rest/3.0/app/json/getStatsData?' app_id = '<e-Statマイページで取得したアプリケーションIDを挿入>' cat01 = '010800150' # アイスクリーム・シャーベット # cat01 = '010800130' # チョコレート # cat01 = '011100030' # ビール remove_month = 0 # 特定月を除く場合は1-12のいずれかを指定 # 指定する数字の桁数は決まっているので注意 keys = { 'appId' : app_id, 'lang' : 'J', 'statsDataId' : '0003343671', # 家計調査データ 'metaGetFlg' : 'Y', 'cntGetFlg' : 'N', 'cdTab' : '01', # 金額 'cdTimeFrom' : '2010000101', # 2010年1月から 'cdTimeTo' : '2019001212', # 2019年12月まで 'cdArea' : '00000', # 全国 'cdCat01' : cat01, 'cdCat02' : '03' # 二人以上世帯 } params = urllib.parse.urlencode(keys) r_obj = urllib.request.urlopen(url + params) # データを取得 r_str = r_obj.read() res = json.loads(r_str) # Pythonの辞書へ stats_data = res['GET_STATS_DATA']['STATISTICAL_DATA'] class_obj = stats_data['CLASS_INF']['CLASS_OBJ'] # メタ情報 if 'DATA_INF' not in stats_data: # ['DATA_INF']が入らないときのチェック用 for co in class_obj: if 'CLASS' not in co: print("ERROR: Check params @id= {}, @name= {}" \ .format(co['@id'], co['@name'])) sys.exit(1) values = stats_data['DATA_INF']['VALUE'] # 統計データの数値情報を取得 # メタ情報(CLASS_INF)から取得した品目名称を図のタイトルに使う title = [co['CLASS']['@name'] for co in class_obj if co['@id'] == 'cat01'][0] print(title) # 各要素が [年, 月, 支出金額] の2次元リストにする data = [[int(v['@time'][0:4]), int(v['@time'][6:8]), int(v['$'])] for v in values] print("n =", len(data)) # 120 = 10年 x 12カ月 # Pandasデータフレームの準備 df = pd.DataFrame(data, columns=['year', 'month', '支出(円)']) df['days'] = [calendar.monthrange(df.loc[i, 'year'], df.loc[i, 'month'])[1] for i in df.index] # 各月の日数 df['支出(円/日)'] = df['支出(円)'] / df['days'] # 1日あたりの支出金額 df['y/m'] = df['year'].astype(str) + '/' + df['month'].astype(str) # 結合用 # 気象庁の気温データとマージ df_jma = pd.read_csv('csv/data.csv', skiprows=5, header=None, usecols=[0,1], encoding='Shift_JIS') df_jma.columns = ['y/m', '平均最高気温(℃)'] df = pd.merge(df, df_jma, on='y/m') # データフレームの結合 if remove_month > 0: df = df.query('month != @remove_month') # 特定月を除く場合 # 相関係数を計算 corr, _ = stats.pearsonr(df['平均最高気温(℃)'], df['支出(円/日)']) corr_str = "相関係数: {:2f}".format(corr) print(corr_str) # 散布図をプロット ax = df.plot(kind='scatter', x='平均最高気温(℃)', y='支出(円/日)') ax.set_title(title + ', ' + corr_str) plt.show() |
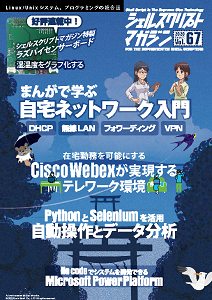
004 レポート Microsoft社製BASICのソースコード公開
005 NEWS FLASH
008 特集1 まんがで学ぶ自宅ネットワーク入門/麻生二郎
014 特集2 Cisco Webexが実現するテレワーク環境/粕谷一範
022 特集3 PythonとSeleniumを活用 自動操作とデータ分析/川嶋宏彰 コード掲載
035 Hello Nogyo!
036 特別企画 Microsoft Power Platform(後編)/清水優吾
050 ラズパイセンサーボードで学ぶ 電子回路の制御/米田聡 コード掲載
056 レッドハットのプロダクト/杉本拓 コード掲載
064 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
066 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
072 tele-/桑原滝弥、イケヤシロウ
074 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
078 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載
092 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
094 香川大学SLPからお届け!/山内真仁 コード掲載
102 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
108 Techパズル/gori.sh
110 コラム「ユニケージの本領発揮」/シェル魔人
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言により、在宅勤務やテレワークが普及しました。今号に掲載した二つの特集では、在宅勤務やテレワークをテーマにしています。
特集1では、在宅勤務で重要になる「自宅ネットワーク」を扱いました。冒頭部分にまんがを使って、自宅ネットワークの仕組みを知らない人にも分かりやすく解説しています。
特集2は、テレワーク環境での会議やイベント、共同作業を実現するためのサービスの「Cisco Webex」です。現在、一番注目されているサービスの一つと言ってよいでしょう。機能概要、オンライン会議の開催方法や会議中の操作方法、将来実装される機能を詳しく紹介しています。
特集3では、PythonとSelenium WebDriverを利用した、Webブラウザの自動操作と、Webブラウザから取得したデータの分析を扱っています。Selenium WebDriverを用いることで、さまざまなWebサイト上のデータをスクレイピングできます。
特別企画では、前回と同様にMicrosoft Power Platform」を解説します。今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.67。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
著者:大津 真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。第3回は、シェルスクリプトにおける条件分岐の使用方法を中心に解説します。
図1 シェルスクリプト「ping.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash if ping -c1 192.168.0.2 > /dev/null then echo " 応答あり" fi |
図2 シェルスクリプト「secret1.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
#!/bin/bash secret=" ひらけごま" echo -n " 合言葉は?: " read aikotoba if test $secret = $aikotoba; then echo " 正しい合言葉です!" fi |
図3 シェルスクリプト「secret2.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
#!/bin/bash secret=" ひらけごま" echo -n " 合言葉は?: " read aikotoba if [[ $secret = $aikotoba ]]; then echo " 正しい合言葉です!" fi |
図4 シェルスクリプト「secret3.sh」の内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#!/bin/bash secret=" ひらけごま" echo -n " 合言葉は?: " read aikotoba if [[ $secret = $aikotoba ]]; then echo " 正しい合言葉です!" else echo " 合言葉が間違っています" fi |
図5 平成年を西暦年に変換するシェルスクリプト「heiseiToSeireki.sh」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo " 平成年を指定してください" exit 1 fi if [[ "$1" -lt 1 || "$1" -gt 31 ]]; then echo "1〜31 までの数値を入力してください" exit 1 fi echo " 平成$1 年は西暦$(($1+1988)) 年" |
図6 指定したファイル中のコロンをカンマに変換するシェルスクリプト「colon_to_comma.sh」
|
1 2 3 4 |
#!/bin/bash fname=$1 cp "$fname" "${fname}~" tr ":" "," < "${fname}~" > "$fname" |
図7 引数チェック用のコードを追加した「colon_to_comma2.sh」
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
#!/bin/bash if [[ $# -eq 0 ]]; then echo " 引数でファイルを指定してください" exit 1 fi if [[ ! -f $1 ]]; then echo "$1 が見つかりません" exit 1 fi fname=$1 cp "$fname" "${fname}~" tr ":" "," < "${fname}~" > "$fname" |
インターネットのWebサイトへのアクセスや、インターネットサービスの利用が最近のパソコンの使い道です。Linuxパソコンでもそれは変わりません。しかし、WindowsやMacと違い、インターネットで提供されているサービスのほとんどがLinuxをサポートしていません。そのため、何か問題が発生した場合は自力で解決しなくてはいけません。また、Linux自体が原因の場合、問題を解決できないこともあります。できるだけそのようなことが起きないように、WindowsやMacに提供されているツールと同じものを使います。
インターネットへのアクセスには「Webブラウザ」を使います。これはLinuxでも同じです。本連載で利用しているLubuntuにはWebブラウザとして「Mozilla Firefox」がインストールされています。ただし、バージョンが古かったり、Linux版Mozilla Firefoxだと一部の機能が使えなかったりします。WindowsとMacと同じとは言い難いです。
そこで、Linuxで最もお薦めなWebブラウザは「Google Chrome」です(図1)。公式サイトから入手してインストールする必要がありますが、米Google社がLinux向けに無償で提供していてWindows版やMac版のGoogle Chromeと同じように動作します。

ちなみに、Lubuntuでは、Google Chrome(以下、Chrome)のオープンソース版である「Chromium」なら標準でインストールできます。ただし、ChromiumにはFlash Playerが同こんされないなど、いくつかの違いがあるのであまりお薦めはできません(Flash Playerは2020年12月31日に提供終了予定)。
前回は、パソコンにLubuntuをインストールしました。Lubuntuのインストール時に、利用地域やタイムゾーンで日本(Aisa/Tokyo)を選んでいるので、英語が一部残っているものの、メニューなどは日本語で表示されています。そのため、Linux(Lubuntu)パソコンを日本語で使う環境が整っているように見えますが、日本語の入力ができません。
Windowsパソコンと同様に、キーボードの[半角/全角]キーを押したら、日本語入力へ切り替えられるようにします(図1)。
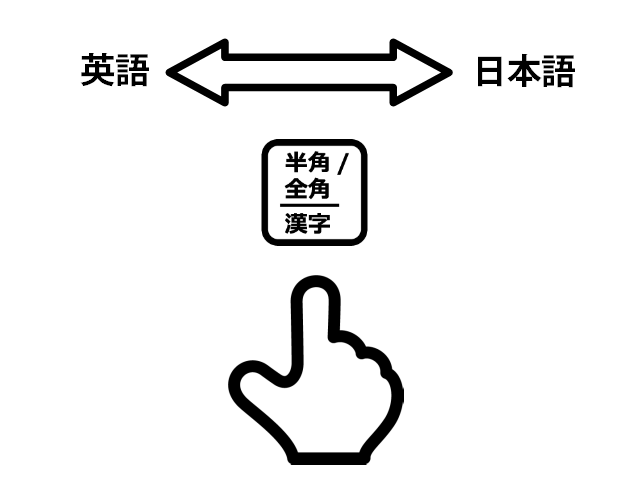
Lubuntuで日本語入力を可能にするには、インプットメソッドフレームワークと、そのフレームワークに対応した日本語入力システム(インプットメソッド)が必要です。インプットメソッドとは、パソコンなどのコンピュータ上で文字を入力するためのソフトウエア、インプットメソッドフレームワークとは、インプットメソッドと他のアプリケーションを結び付けるための機能やライブラリを含んでいるソフトウエアです。
Lubuntuでは、「Fcitx」というインプットメソッドフレームワークと、それに対応した日本語入力システムの「Mozc」を使います。Mozcは米Google社が開発した「Google日本語入力」のオープンソース版です。Google日本語入力は、WindowsやmacOS、Android向けにも用意されていて、とても評判が高いソフトウエアです。Mozcでは一部の機能が提供されていないものの、便利に使えます。
Fcitxは、すでにLubuntuにインストールされています。Fcitx対応のMozcは、Lubuntuにインストールしてすぐに実行できる形式の「パッケージ」としてインターネット上で配布されています。パッケージについては、別の回に詳しく紹介する予定ですが、ここでは「apt」というコマンドで、パッケージのインストール(導入)やアンインストール(削除)、アップデート(更新)ができることだけを覚えておいてください。この後で、aptコマンドを使って、Fcitx対応のMozcをインストールします。
前回、パソコンの内蔵ストレージを丸ごとバックアップしてLinuxをインストールする準備をしました。今回は、内蔵ストレージをすべて消去し、いよいよLinuxをインストールします。インストールするLinuxディストリビューションは、第1回で決定した「Lubuntu 20.04 LTS」です(図1)。
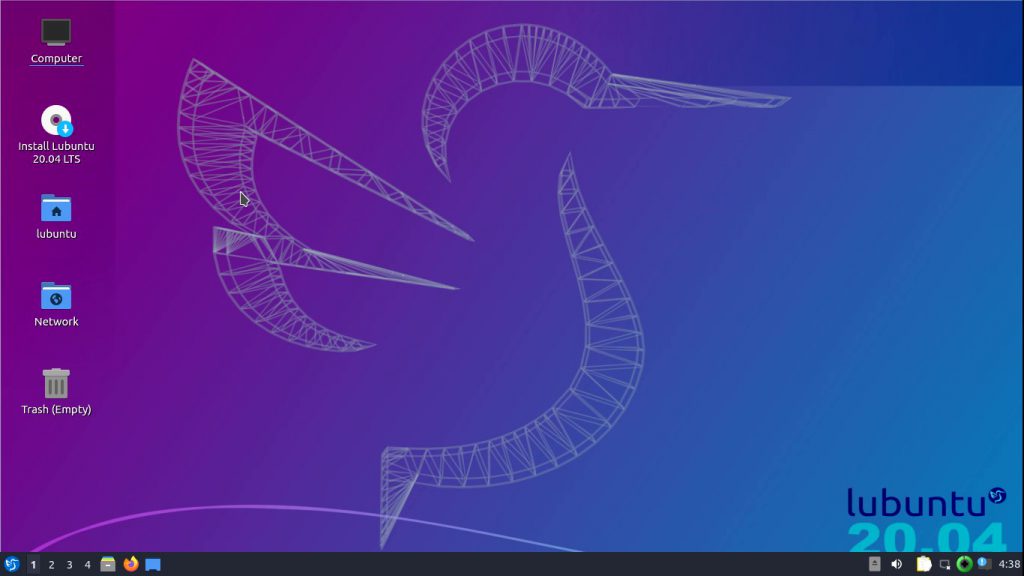
前回と同様に、Linuxのメディアとして作成したUSBメモリーからLubuntuをライブで起動しましょう。手順は、前回を参照してください。最初に図2の画面が開くので「Start Lubuntu」が選ばれた状態でキーボードの[Enter]キーを押します。そのまま待っても構いません。
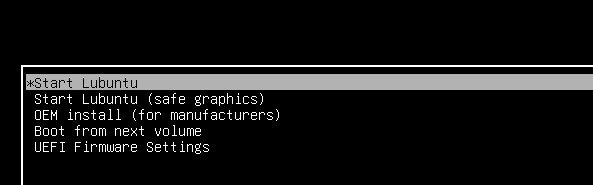
しばらくするとLubuntuのデスクトップ画面が開きます(図3)。
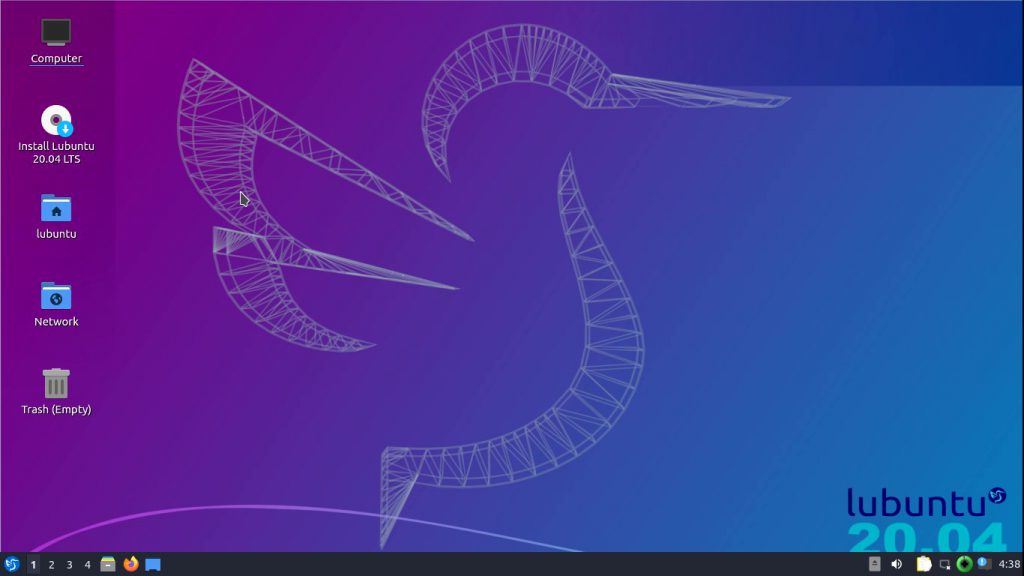
まずは、Lubuntuからインターネットへアクセス可能にします。こうしておくと、日本という利用地域や時間の基準となる「タイムゾーン」を自動で取得できます。また、インストール後に自動でネットワークに接続され、後述するLubuntuを構成するソフトウエアのアップデートもスムーズに行えます。なお、有線LANで接続している場合は、基本的にインターネットにアクセスできる状態になっているので、以下の設定は不要です。無線LANの場合にのみ設定してください。
デスクトップ画面の右下にある、ディスプレイのようなアイコンをクリックします(図4)。
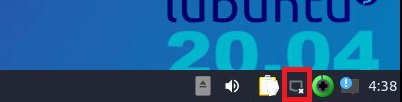
無線LANのSSID(Service Set IDentifier)一覧が表示されます。一覧の中から自分が利用しているブロードバンドルーターのSSIDを探して、それをクリックします(図5)。
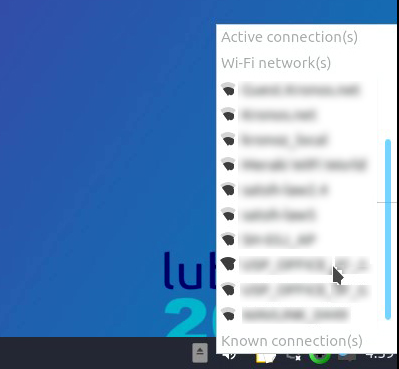
通常、WPA2-PSKなどの認証および暗号化を利用しているので、パスワードの入力ダイアログが表示されます(図6)。ブロードバンドルーターに設定されている無線LANへの接続パスワードを入力します。
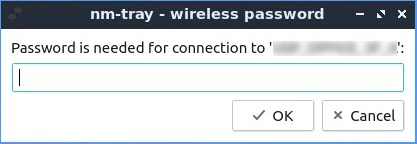
パスワードが正しければ、右上に無線LANへの接続メッセージが表示されます(図7)。
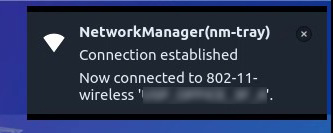
著者:大津 真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とするシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして採用する「Bash」です。第2回では、変数の概要と、シェルスクリプト内でコマンドライン引数を扱う方法について解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 シェルスクリプト「 permtest1.sh 」の内容
|
1 2 3 4 5 6 |
#!/bin/bash echo " スクリプト名: $0" echo " 引数の数: $#" echo " 引数1: $1" echo " 引数2: $2" echo " 引数3: $3" |
図5 シェルスクリプト「 colon_to_comma.sh 」の内容
|
1 2 3 4 |
#!/bin/bash fname=$1 cp "$fname" "${fname}~" tr ":" "," < "${fname}~" > "$fname" |
図6 加工対象のファイル「 customer.txt 」の内容
|
1 2 3 |
010: 白戸二郎: 男:39: 北海道 011: 小山田花子: 女:24: 福岡 012: 三村美子: 女:29: 東京 |
著者:石崎 博之、掛本 健一
ユニケージ開発手法によるシステムの設計・実装・保守を数年以上経験したメンバーが、業務システム構築のための「ユニケージ開発手法」を解説します。我々の経験に基づきながら、具体的なシステム構築の流れを示していきます。第1回は、ユニケージ開発手法の特徴をつかむです。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 ユニケージのシェルスクリプトの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
#!/bin/bash join0 key=1 MASTER TRAN | self 2 3 4 5 | msort key=1/2 | sm2 1 2 3 4 | sm4 1 1 2 2 3 4 | self 1 2 3 4 | sm5 1 3 4 4 | map num=1 | sed 's/A/Sales/g' | sed 's/B/Profit/g | keta 4 6@NF-1 | comma 3/NF | cat header - | tocsv > result exit 0 |
著者:檜垣 龍德
今回は、Pythonとそのライブラリである「slacker」「python-crontab」を用いて、チャットサービス「Slack」にメッセージを自動投稿するbo(t Slackbot)を開発する方法を解説します。例として開発するのは、参加者からメッセージが投稿されるまで「Get Up !!」というメッセージを連続投稿するbotです。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図7 「.env」ファイルに記述する内容
|
1 2 |
ACCESS_TOKEN=アクセストークン CHANNEL_ID=チャンネルID |
図8 「settings.py」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
import os from os.path import join, dirname from dotenv import load_dotenv dotenv_path = join(dirname(__file__), '.env') load_dotenv(dotenv_path) ACCESS_TOKEN = os.environ.get("ACCESS_TOKEN") CHANNEL_ID = os.environ.get("CHANNEL_ID") |
図9 「main.py」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 |
from slacker import Slacker import settings slack = Slacker(settings.ACCESS_TOKEN) slack.chat.post_message("チャンネル名", "Get Up !!") |
図11 「cron.py」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
from crontab import CronTab cron = CronTab() job = cron.new('python main.py') job.setall('00 00 * * *') for result in cron.run_scheduler(): print("Done Job" |
図12 書き換えたmain.pyファイルの内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
from slacker import Slacker from time import sleep import settings slack = Slacker(settings.ACCESS_TOKEN) channel_id = settings.CHANNEL_ID slack.chat.post_message("チャンネル名", "Get Up !!") history = slack.channels.history(channel_id) start_ts = history.body["messages"][0]["ts"] while True: sleep(1) history = slack.channels.history(channel_id, count=10000, oldest=start_ts) not_bot_users = [message["user"] for message in history.body["messages"] if "bot_id" not in message] if len(not_bot_users): break else: slack.chat.post_message("チャンネル名", "Get Up !!") |
図14 書き換えたmain.pyファイルに追記する内容
|
1 2 3 4 5 |
history = slack.channels.history(channel_id, count=10000, oldest=start_ts) ts_list = [message["ts"] for message in history.body["messages"] if 'bot_id' in message] ts_list.append(start_ts) for ts in ts_list: slack.chat.delete(channel_id, ts=ts, as_user=True) |
著者:しょっさん
ソフトウエアを正しく作るために、エンジニアたちはどんなことを知らなければならないでしょうか。実際のコードを使って、より良くしていくためのステップを考えてみましょう。第6回は、アプリケーションの開発やテストを実施する環境について詳しく考えます。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 モックのコード(swagger.json)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |
{ "openapi" : "3.0.0", "servers" : [ { "description" : "Expense Reporter Sample API", "url" : "https://virtserver.swaggerhub.com/sho7650/ExpenseMockServices/0.5.0" } ], "info" : { "description" : "シェルスクリプトマガジン用サンプル", "version" : "0.5.0", "title" : "Expense API", "contact" : { "email" : "sho@oshiire.to" }, "license" : { "name" : "Apache 2.0", "url" : "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html" } }, "tags" : [ { "name" : "users", "description" : "一般利用者" }, { "name" : "approvers", "description" : "承認者" } ], "paths" : { (略) "/payment" : { "get" : { "tags" : [ "approvers" ], "summary" : "支払い待ち一覧", "operationId" : "findPayments", "description" : "一般利用者からの請求一覧を表示", "security" : [ { "bearerAuth" : [ ] } ], (略) "responses" : { "200" : { "description" : "success", "content" : { "application/json" : { "schema" : { "type" : "array", "items" : { "$ref" : "#/components/schemas/ExpenseItem" } } } } }, "400" : { "description" : "bad input parameter" } } } } }, "components" : { "securitySchemes" : { "bearerAuth" : { "type" : "http", "scheme" : "bearer", "bearerFormat" : "JWT" } }, "schemas" : { "id" : { "type" : "integer", "format" : "int32", "example" : 120 }, (略) } } } |
著者:飯尾 淳
計量社会学や数理社会学という学問分野があります。人々の行動や社会活動から生み出される多様なデータを定量的に分析することによって、その背景となる社会的な構造や原理を見いだそうという社会学です。筆者はそれらの専門家ではありませんが、社会情報学の文脈で似たような研究に従事しています。今回は、筆者らの研究成果の一つであるTwitterのトレンド分析について、その概要を紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図6 トレンドのキーワードを取得するPythonコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
#!/usr/bin/env python from twitter import * woeid = 23424856 # Japan CK = 'ADD_YOUR_KEY_HERE' # Consumer Key CS = 'ADD_YOUR_KEY_SECRET_HERE' # Consumer Key Secret AT = 'ADD_YOUR_TOKEN_HERE' # Access Token AS = 'ADD_YOUR_TOKEN_SECRET_HERE' # Accesss Token Secert twitter = Twitter(auth = OAuth(AT,AS,CK,CS)) results = twitter.trends.place(_id = woeid, exclude="hashtags") for location in results: for trend in location["trends"]: print (trend["name"]) |
著者:平田 千浩
「Red Hat Ansible Automation Platform」は、OSS のAnsibleとAWXを基とした企業向け自動化の基盤です。RHELを含むさまざまなOS、さまざまなアプリケーション、さまざまな機器に対応し、局所的な作業からバージョン管理システムと連携した構成管理までを自動化できます。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 インベントリファイルの例(hosts)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
[all:vars] ansible_ssh_private_key_file=/home/student1/.ssh/aws-private.pem [ios] ios1 ansible_host=XX.XX.XX.XX [ios:vars] ansible_user=ec2-user ansible_network_os=ios ansible_connection=network_cli |
図3 Cisco IOS向けの簡単なPlaybookの例(snmp.yml)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
--- - name: snmp ro / rw string configuration hosts: ios gather_facts: no tasks: - name: ensure that the desired snmp strings are present ios_config: commands: - snmp-server community ansible-public RO - snmp-server community ansible-private RW |
図6 Arista EOSを追加したインベントリファイル例(hosts)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
[all:vars] ansible_ssh_private_key_file=/home/student1/.ssh/aws-private.pem [ios] ios1 ansible_host=XX.XX.XX.XX [ios:vars] ansible_user=ec2-user ansible_network_os=ios ansible_connection=network_cli [eos] eos1 ansible_host=YY.YY.YY.YY [eos:vars] ansible_user=ec2-user ansible_network_os=eos ansible_connection=network_cli ansible_become=true ansible_become_method=enable [control] ansible ansible_host=AA.AA.AA.AA ansible_user=student1 ansible_password=PASSWORD |
図7 Arista EOSのコンフィグをバックアップするPlaybookの例(eos_backup.yml)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
--- - name: retrieve router configurations hosts: eos gather_facts: no tasks: - name: BACKUP THE CONFIG eos_config: backup: yes register: config_output - name: Save THE CONFIG vars: ansible_connection: ssh copy: src: "{{config_output.backup_path}}" dest: "/backup/{{inventory_hostname}}" delegate_to: ansible become: yes |
図10 CISCO IOSのコンフィグをバックアップするPlaybookの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
- name: retrieve router configurations hosts: ios gather_facts: no tasks: - name: BACKUP THE CONFIG ios_config: backup: yes register: config_output - name: REMOVE NON CONFIG LINES - REGEXP lineinfile: path: "{{config_output.backup_path}}" line: "Building configuration..." state: absent - name: Save THE CONFIG vars: ansible_connection: ssh copy: src: "{{config_output.backup_path}}" dest: "/backup/{{inventory_hostname}}" delegate_to: ansible become: yes |
図11 保存したArista EOSのコンフィグからリストアするPlaybookの例(eos_restore.yml)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
--- - name: Restore the EOS Config hosts: eos gather_facts: no tasks: - name: RESTORE THE CONFIG eos_config: replace: config src: "/backup/{{inventory_hostname}}" |
図12 保存したCisco IOSのコンフィグからリストアするPlaybookの例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
--- - name: Restore the IOS Config hosts: ios gather_facts: no tasks: - name: RESTORE THE CONFIG ios_config: src: "/backup/{{inventory_hostname}}" |
著者:米田 聡
シェルスクリプトマガジンでは、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)向けのセンサー搭載拡張ボード「ラズパイセンサーボード」を制作しました。第13 回では、同ボードに搭載された湿温度・気圧センサー「BME280」から取得したデータをグラフ化する準備をします。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 PythonからSQLiteを操作するサンプルプログラム(test_sqlite3.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
import sqlite3 DBNAME = "test.sqlite3" # データベースファイル名 conn = sqlite3.connect(DBNAME) # SQLite 3に接続 cur = conn.cursor() # カーソルを得る cur.execute("SQL文") # SQLを発行 conn.commit() # コミット data = cur.fetchall() # 結果をdataに格納 conn.close() # データベースを閉じる |
図3 温度、湿度、気圧のデータをSQLiteに保存するプログラム(storebme.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
import time, os, sys, signal import smbus2 import bme280 import sqlite3 BME280_ADDR = 0x76 BUS_NO = 1 DBNAME = 'weather.sqlite3' def store_values(values): conn = sqlite3.connect(DBNAME) cur = conn.cursor() sql = "INSERT INTO bme(dt,temp,hum,press) VALUES(datetime('now', '+9 hours'),?,?,?)" cur.execute(sql,(values[0],values[1],values[2])) conn.commit() conn.close() def signal_handler(sig, handler): sys.exit() # テーブル作成 if not os.path.exists(DBNAME): conn = sqlite3.connect(DBNAME) cur = conn.cursor() cur.execute("CREATE TABLE bme(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, dt TEXT,temp REAL, hum REAL, press REAL)") conn.commit() conn.close() # BME280 i2c = smbus2.SMBus(BUS_NO) bme280.load_calibration_params(i2c, BME280_ADDR) # signal signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler) signal.signal(signal.SIGTERM, signal_handler) # メインループ while True: data = bme280.sample(i2c, BME280_ADDR) store_values([data.temperature,data.humidity,data.pressure ]) time.sleep(60) |
著者:麻生 二郎
センサーをつないで状態を監視するだけのIoT(モノのインターネット)を
始めるには、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」は高機能かつ高価で
す。そこで1000円以下で購入できるマイコンボード「ESP32 ESP-32S」を使
って、簡単なプログラムと共にI oTを始めてみましょう。
シェルスクリプトマガジン Vol.66は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 ネットワーク接続プログラム(wlan.py)
|
1 2 3 4 5 6 |
import network wlan_if = network.WLAN(network.STA_IF) wlan_if.active(True) wlan_if.ifconfig(('192.168.1.100', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '192.168.1.1')) wlan_if.connect('SSID', 'パスワード') wlan_if.inconfig() |
図3 簡易サーバーを立ち上げるプログラム(webserver_test.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
import picoweb app = picoweb.WebApp(__name__) @app.route("/") def index(req, resp): yield from picoweb.start_response(resp) yield from resp.awrite("こんにちは") app.run(debug=True, host = "192.168.1.100") |
図12 Webブラウザから湿温度・気圧を取得するプログラム(web_bme280.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
import picoweb, machine, bme280 i2cpin = machine.I2C(scl=machine.Pin(22), sda=machine.Pin(21)) bme = bme280.BME280(i2c=i2cpin) app = picoweb.WebApp(__name__) @app.route("/") def index(req, resp): bme280values = bme.values yield from picoweb.start_response(resp) yield from resp.awrite("気温:" + bme280values[0]) yield from resp.awrite("|湿度:" + bme280values[2]) yield from resp.awrite("|気圧:" + bme280values[1]) app.run(debug=True, host = "192.168.1.100") |
図16 明るさによってライトの点灯を促すプログラム(web_cds.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
import picoweb, machine adc = machine.ADC(machine.Pin(36)) adc.atten(machine.ADC.ATTN_11DB) app = picoweb.WebApp(__name__) @app.route("/") def index(req, resp): csdvalue = adc.read() yield from picoweb.start_response(resp) if csdvalue < 2500: yield from resp.awrite("明かりをつけましょう") else: yield from resp.awrite("十分な明るさです") app.run(debug=True, host = "192.168.1.100") |
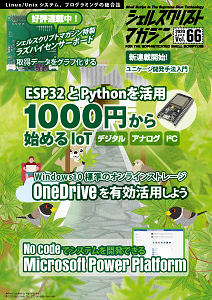
004 レポート Linuxの新版「Ubuntu 20.04 LTS」リリース
005 レポート VS Codeライクな「Eclipse Theia」登場
006 NEWS FLASH
008 特集1 1000円から始めるIoT/麻生二郎 コード掲載
023 Hello Nogyo!
026 特集2 OneDriveを有効活用しよう/三沢友治
042 特別企画 Microsoft Power Platform(前編)/清水優吾
050 ラズパイセンサーボードで学ぶ 電子回路の制御/米田聡 コード掲載
054 レッドハットのプロダクト/平田千浩 コード掲載
056 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
062 μ(マイクロ)/桑原滝弥、イケヤシロウ
064 Webアプリの正しい作り方/しょっさん コード掲載
070 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
072 MySQL Shellを使おう/梶山隆輔
079 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
084 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
086 香川大学SLPからお届け!/檜垣龍德 コード掲載
092 ユニケージ開発手法入門/石崎博之、掛本健一 コード掲載
098 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
104 Techパズル/gori.sh
106 コラム「コロナ禍の中で」/シェル魔人
小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)が高性能になり、センサー制御などの組み込み機器の用途で違和感を感じるようになりました。また、発熱量や消費電力が大きいのも問題です。
センサーを制御するなら、1000円以下で購入できるマイコンボードで十分です。そこで、特集1では「ESP32 ESP-32S」というマイコンボードと、プログラミング言語「Python」を組み合わせて、簡易なIoT(モノのインターネット)環境を構築します。ラズパイと同じようにPythonプログラムでセンサーを制御できるので、初心者でも十分楽しめる内容です。
特集2では、Windows 10の標準オンラインストレージ「OneDrive」の有効活用する方法を紹介します。Windows 10のパソコンなら、無料で5Gバイトのストレージ容量が利用できるOneDriveを使うべきです。OneDriveでより快適で便利なパソコン環境を手に入れましょう。
特別企画では、最近注目されている「ノーコーディングプラットフォーム」「ローコーディングプラットフォーム」の一つである「Microsoft Power Platform」を解説します。前後編でMicrodsoft PowerPlatformが備える機能を一つひとつ詳しく紹介します。
このほか、業務システムを構築するための「ユニケージ開発手法」の入門連載が開始しました。同入門連載では、実際に業務システム構築の流れを示しながら、実際の経験を基にユニケージ流のやり方を分かりやすく解説していきます。
今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.66。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら
Linuxをパソコンにインストールする前に、元の状態に戻せるようにパソコンの内蔵ストレージ(ハードディスクやSSD)を丸ごとバックアップします。Windows 10の場合、回復ドライブを使ってイメージファイルとして丸ごとバックアップできますが、少々手順が面倒です。
そこで、Linuxをライブで起動して「dd」コマンドを使ってイメージファイルとしてバックアップします。ddは、ストレージの書き込まれているデータを「ブロック」という単位でコピーできるコマンドです(図1)。
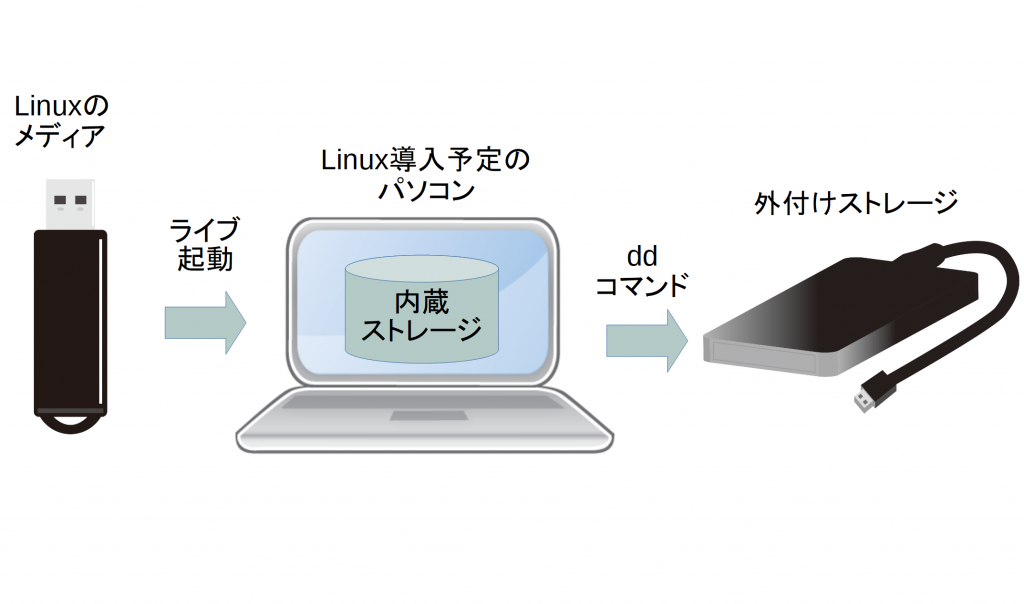
ddコマンドなら、ストレージの一部が壊れていて読みだせないファイルも、読み出せるブロックだけを取り出してバックアップできます。そして、バックアップ時に1行のddコマンドを実行すればよく、復元時も、指定する入出力の引数が変わるだけで、同じ1行のddコマンドを実行するだけです。
Linuxとは、OS(基本ソフト)のコア(核)となるソフトウエア(カーネル)の名前です。WindowsやmacOSのようにパソコン上で動作させるには、このカーネルと、各種のツールやユーティリティ、ライブラリなどのソフトウエアをソースコードからビルド(コンパイル)して組み合わせる必要があります。
ソースコードのほとんどは無償で公開されているので、それなりの知識があれば自らビルドして組み合わせることも可能です。ただし、すでにOSとして動作する状態して配布されている「Linuxディストリビューション」があります。Linuxを使いたいだけなら、こちらのLinuxディストリビューションを用います。
Linuxディストリビューションは、一つではありません。DebianやUbuntu、Fedora、CentOSなどの複数の種類があります。これは、異なる団体が自分たちが決めたポリシーに従って構成するソフトウエアを決定し、それらをソースコードからビルドして組み合わせて配布しているからです。
個々のLinuxディストリビューションによって、それぞれ特徴が違います。ノートパソコンやデスクトップパソコンに導入して使うなら、次の五つを満足するものがよいでしょう。

テレワークや在宅勤務というビジネススタイルが広がってきています。職場と同じように自宅で効率良く仕事をこなすためには、ある程度性能の高いパソコンが不可欠です。また、カメラやマイク付きのノートパソコンなら、そのままテレワークに使えます。これらの理由から、自宅で使っていたパソコンを買い替えた人も多いでしょう。
買い替えによって、今まで使っていたパソコンが不要になります。それを予備機として使い続けるのもよいですが、この機会にLinuxに入れ替えて、快適で十分実用に耐え得るパソコンとして復活させてみましょう。
本連載では、WindowsがインストールされたノートパソコンやデスクトップパソコンにLinuxを導入し、普段使えるパソコンに仕立てていきます。
第1回 Linuxのメディアを作る
第2回 パソコンのストレージをバックアップする
第3回 Lubuntuをインストールする
第4回 日本語入力を可能にする
第5回 Chromeブラウザを導入する
第6回 外付けストレージを利用する 諸事情により公開延期
筆者:大津 真
本連載ではシェルスクリプトの書き方をやさしく紹介します。対象とす
るシェルは、多くのLinuxディストリビューションが標準シェルとして
採用する「Bash」です。第1回目となる今回は、シェルスクリプトの概要
と作成、実行の方法を解説します。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 ホスト名と日時を表示するシェルスクリプト「 today1.sh 」
|
1 2 |
hostname date '+ 今日は%Y 年%m 月%d 日(%a) です' |
図5 シバンを追加したシェルスクリプト「 today2.sh 」
|
1 2 3 |
#!/bin/bash hostname date '+ 今日は%Y 年%m 月%d 日(%a) です' |
図6 コメントを追加したシェルスクリプト「 today3.sh 」
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash # ホスト名と今日の日時を表示する # ver.1.0 2020/2/1 hostname date '+ 今日は%Y 年%m 月%d 日(%a) です' |
図8 コマンド置換を使用したシェルスクリプト「today4.sh」
|
1 2 3 4 5 |
#!/bin/bash # ホスト名と今日の日時を表示する # ver.1.1 2020/2/1 echo " ホスト名は$(hostname) です" date '+ 今日は%Y 年%m 月%d 日(%a) です' |
筆者:重松 亜夢
はじめまして!香川大学の重松亜夢です。2019年秋にSLPの所長を引き継ぎま
した。SLPの最近の主な活動はチーム開発です。2019年12月には部員が最近の活動をブログに投稿し、Advent Calendarを作成しました。また、2020年1月には餅つきで親交を深めました。
今回は、Webアプリケーションに認証機能を実装します。具体的には、米Google社の「Google Cloud Platform」のAPIを使って「Googleでログイン」を実装します。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図9 「.env」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 |
SAMPLE_HOST="localhost:1323" GOOGLE_CLIENT_ID="クライアントID" GOOGLE_CLIENT_SECRET="クライアントシークレット" |
図10 「main.go」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 |
package main import ( route "example.com/user_name/sample-app/route" ) func main() { route.Echo.Logger.Fatal(route.Echo.Start(":1323")) } |
図11 「router.go」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
package route import ( "fmt" "log" "os" "example.com/user_name/sample-app/handler" "github.com/joho/godotenv" "github.com/labstack/echo/v4" "github.com/labstack/echo/v4/middleware" "github.com/stretchr/gomniauth" "github.com/stretchr/gomniauth/providers/google" "github.com/stretchr/signature" ) var Echo *echo.Echo func init() { e := echo.New() err := setupOAuth() if err != nil { log.Fatal("Error loading .env file") } e.Use(middleware.Logger()) e.GET("/auth/login/:provider", handler.LoginHandler) e.GET("/auth/callback/:provider", handler.CallbackHandler) Echo = e } |
図12 「router.go」ファイルに追記する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
func setupOAuth() error { err := godotenv.Load() if err != nil { return err } host := os.Getenv("SAMPLE_HOST") googleCallbackURL := fmt.Sprintf("http://%s/auth/callback/google", host) gomniauth.SetSecurityKey(signature.RandomKey(64)) gomniauth.WithProviders( google.New( os.Getenv("GOOGLE_CLIENT_ID"), os.Getenv("GOOGLE_CLIENT_SECRET"), googleCallbackURL, ), ) return nil } |
図13 「sesseion.go」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
package handler import ( "net/http" "github.com/labstack/echo/v4" "github.com/stretchr/gomniauth" "github.com/stretchr/objx" ) func LoginHandler(c echo.Context) error { provider, err := gomniauth.Provider(c.Param("provider")) if err != nil { return err } authURL, err := provider.GetBeginAuthURL(nil, nil) if err != nil { return err } return c.Redirect(http.StatusTemporaryRedirect, authURL) } |
図13 「sesseion.go」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
package handler import ( "net/http" "github.com/labstack/echo/v4" "github.com/stretchr/gomniauth" "github.com/stretchr/objx" ) func LoginHandler(c echo.Context) error { provider, err := gomniauth.Provider(c.Param("provider")) if err != nil { return err } authURL, err := provider.GetBeginAuthURL(nil, nil) if err != nil { return err } return c.Redirect(http.StatusTemporaryRedirect, authURL) } |
図14 「sesseion.go」ファイルに追記する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
func CallbackHandler(c echo.Context) error { provider, err := gomniauth.Provider(c.Param("provider")) if err != nil { return err } omap, err := objx.FromURLQuery(c.QueryString()) if err != nil { return err } _, err = provider.CompleteAuth(omap) if err != nil { return err } return c.String(http.StatusOK, "Login Success!") } |
図16 「sesseion.go」ファイルのCallbackHandler関数の変更コード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
creds, err := provider.CompleteAuth(omap) if err != nil { return err } user, err := provider.GetUser(creds) if err != nil { return err } authCookieValue := objx.New(map[string]interface{}{ "name": user.Name(), "email": user.Email(), "avatarURL": user.AvatarURL(), }).MustBase64() cookie := &http.Cookie{ Name: "auth", Value: authCookieValue, Path: "/", Expires: time.Now().Add(24 * time.Hour), } c.SetCookie(cookie) return c.Redirect(http.StatusTemporaryRedirect, "/") |
図17 「router.go」ファイルに追記する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
type TemplateRenderer struct { templates *template.Template } func (t *TemplateRenderer) Render(w io.Writer, name string, data interface{}, c echo.Context) error { return t.templates.ExecuteTemplate(w, name, data) } |
図18 「router.go」ファイルのinit関数に挿入する内容
|
1 2 3 4 5 |
renderer := &TemplateRenderer{ templates: template.Must(template.ParseGlob("templates/*.html")), } e.Renderer = renderer e.GET("/", handler.MainPageHandler) |
図19 「handler.go」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
package handler import ( "net/http" "github.com/labstack/echo/v4" "github.com/stretchr/objx" ) func MainPageHandler(c echo.Context) error { auth, err := c.Cookie("auth") if err != nil { return c.Render(http.StatusOK, "welcome", map[string]interface{}{ "title": "Welcome", }) } userData := objx.MustFromBase64(auth.Value) return c.Render(http.StatusOK, "top", map[string]interface{}{ "name": userData["name"], "email": userData["email"], "avatarURL": userData["avatarURL"], "title": "TopPage", }) } |
図20 「index.html」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
{{define "top"}} {{template "head" .}} <img src={{.avatarURL}} width="10%"> <h2>Hello, {{.name}}</h2> Your Email : {{.email}} {{end}} {{define "welcome"}} {{template "head" .}} <h1>ようこそ</h1> <ul> <li> <a href="/auth/login/google">Googleでログイン</a> </li> </ul> {{end}} |
図21 「base.html」ファイルに記述する内容
|
1 2 3 |
{{define "head"}} <title>{{ .title }} / Sample-App</title> {{end}} |
図23 「router.go」ファイルのinit関数定義部分に挿入する内容
|
1 2 |
e.Pre(middleware.RemoveTrailingSlash()) e.Group("", authCheckMiddleware()) |
図24 「router.go」ファイルの末尾に追記する内容
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
func authCheckMiddleware() echo.MiddlewareFunc { return func(next echo.HandlerFunc) echo.HandlerFunc { return func(c echo.Context) error { _, err := c.Cookie("auth") if err != nil { return c.Redirect(http.StatusTemporaryRedirect, "/") } return next(c) } } } |
図25 認証後だけアクセスできるルートを設定する例
|
1 2 |
authCheck := e.Group("", authCheckMiddleware()) authCheck.GET("/fuga", handler.SamplePage) |
筆者:飯尾 淳
今回はデータ分析から少し離れてフラクタル図形について語りましょ
う。例として、縦棒(バーティカルバー)と横棒が縦横無尽に組み合わさっ た図形であるヒルベルト曲線を考えます。ヒルベルト曲線はフラクタル図形の一つで、自己相似性という特徴を持ちます。本記事ではこれを描画するプログラムを紹介します。シンプルなプログラムでこんなにも複雑な図形を描くことができるのかと驚くはずです。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図4 図を出力するためのHTMLコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Hilbert Curve</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="description" content="Drawing Hilbert curve"> <meta name="author" content="Jun Iio"> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> </head> <body> <canvas id="theCanvas" width="1000" height="1000"></canvas> <script src="hilbert.js"></script> </body> </html> |
図5 1次ヒルベルト曲線を描くJavaScriptコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
// the canvas and its graphic context var cs = document.getElementById('theCanvas'); var ctx = cs.getContext('2d'); ctx.lineWidth = 5; ctx.strokeStyle = 'black'; ctx.beginPath(); [ [0.25, 0.25], [0.25, 0.75], [0.75, 0.75], [0.75, 0.25] ] .map(p => [p[0]*cs.width, p[1]*cs.height]) .forEach(p => { ctx.lineTo(p[0],p[1]); }); ctx.stroke(); |
図7 n次のヒルベルト曲線を描く手続き
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
function hilbert(n, R) { if (n > 1) { hilbert(n-1, R’=f(R,"左上")); hilbert(n-1, R’=f(R,"左下")); hilbert(n-1, R’=f(R,"右下")); hilbert(n-1, R’=f(R,"右上")); } else { (Rで示される座標上で1次のヒルベルト曲線を描くコード) } |
図10 座標変換ルールを格納した 配列を定義するコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
var tm = [ // tm[0] [ [ 0, 1/2, 0], [ 1/2, 0, 0], [ 0, 0, 1] ], // tm[1] [ [ 1/2, 0, 0], [ 0, 1/2, 1/2], [ 0, 0, 1] ], // tm[2] [ [ 1/2, 0, 1/2], [ 0, 1/2, 1/2], [ 0, 0, 1] ], // tm[3] [ [ 0, -1/2, 1], [-1/2, 0, 1/2], [ 0, 0, 1] ] ] |
図11 1次から8次までのヒルベルト曲線を描くコード
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 |
// the canvas and its graphic context var cs = document.getElementById('theCanvas'); var ctx = cs.getContext('2d'); // line style var colors = [ 'gray', 'navy', 'purple', 'brown', 'red', 'orange', 'yellowgreen', 'skyblue' ]; var widths = [5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0.5 ]; var tm = [ [ [ 0, 1/2, 0], [ 1/2, 0, 0], [0, 0, 1] ], [ [1/2, 0, 0], [ 0, 1/2, 1/2], [0, 0, 1] ], [ [1/2, 0, 1/2], [ 0, 1/2, 1/2], [0, 0, 1] ], [ [ 0, -1/2, 1], [-1/2, 0, 1/2], [0, 0, 1] ] ]; var E = [ [ 1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1] ]; function affine_transform(m, p) { return [ m[0][0] * p[0] + m[0][1] * p[1] + m[0][2], m[1][0] * p[0] + m[1][1] * p[1] + m[1][2] ]; } function mat_mul(m0, m1) { return [ [m0[0][0]*m1[0][0]+m0[0][1]*m1[1][0]+m0[0][2]*m1[2][0], m0[0][0]*m1[0][1]+m0[0][1]*m1[1][1]+m0[0][2]*m1[2][1], m0[0][0]*m1[0][2]+m0[0][1]*m1[1][2]+m0[0][2]*m1[2][2]], [m0[1][0]*m1[0][0]+m0[1][1]*m1[1][0]+m0[1][2]*m1[2][0], m0[1][0]*m1[0][1]+m0[1][1]*m1[1][1]+m0[1][2]*m1[2][1], m0[1][0]*m1[0][2]+m0[1][1]*m1[1][2]+m0[1][2]*m1[2][2]], [m0[2][0]*m1[0][0]+m0[2][1]*m1[1][0]+m0[2][2]*m1[2][0], m0[2][0]*m1[0][1]+m0[2][1]*m1[1][1]+m0[2][2]*m1[2][1], m0[2][0]*m1[0][2]+m0[2][1]*m1[1][2]+m0[2][2]*m1[2][2]] ]; } function hilbert(n, m) { if (n > 0) { tm.forEach(mm => { hilbert(n-1, mat_mul(m, mm)); }); } else { [ [0.25, 0.25], [0.25, 0.75], [0.75, 0.75], [0.75, 0.25] ] .map(p => affine_transform(m, p)) .map(p => [p[0]*cs.width, p[1]*cs.height]) .forEach(p => { ctx.lineTo(p[0],p[1]); }); } } function drawHilbert(i) { ctx.beginPath(); ctx.lineWidth = widths[i]; ctx.strokeStyle = colors[i]; hilbert(i, E); ctx.stroke(); } for(i=0; i<colors.length; i++) { drawHilbert(i); } |
筆者:松田 絵里奈
「Red Hat Decision Manager」は、OSSの「Drools」がベースのルールエンジンです。同製品で業務ロジックを実装することで、アプリから業務ロジックを分離でき、メンテナンスが容易になります。また、複雑なロジックでも簡単で分かりやすい形式で記述できます。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図11 pom.xml(抜粋)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
(略) <dependencies> <dependency> <groupId>org.kie</groupId> <artifactId>kie-api</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.drools</groupId> <artifactId>drools-core</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.drools</groupId> <artifactId>drools-decisiontables</artifactId> </dependency> </dependencies> (略) |
図12 過去利用状況ファクト(過去利用状況.java)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
package com.example.rhdm; public class 過去利用状況 { private String ユーザーID; private int 過去利用回数; private int 過去利用額計; public String get ユーザーID() { return ユーザーID; } public void set ユーザーID(String ユーザーid) { ユーザーID = ユーザーid; } public int get 過去利用回数() { return 過去利用回数; } public void set 過去利用回数(int 過去利用回数) { this.過去利用回数 = 過去利用回数; } public int get 過去利用額計() { return 過去利用額計; } public void set 過去利用額計(int 過去利用額計) { this.過去利用額計 = 過去利用額計; } } |
図13 今回利用ファクト(今回利用.java)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
package com.example.rhdm; public class 今回利用 { private String ユーザーID; private int 利用額; private String 割引ランク; private int 割引率; public String get ユーザーID() { return ユーザーID; } public void set ユーザーID(String ユーザーid) { ユーザーID = ユーザーid; } public int get 利用額() { return 利用額; } public void set 利用額(int 利用額) { this.利用額 = 利用額; } public String get 割引ランク() { return 割引ランク; } public void set 割引ランク(String 割引ランク) { this.割引ランク = 割引ランク; } public int get 割引率() { return 割引率; } public void set 割引率(int 割引率) { this.割引率 = 割引率; } } |
図14 最初の/src/main/resources/割引決定.drlファイル
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
package com.example.rhdm import com.example.rhdm.* dialect "java" rule "利用回数2回未満、利用額1万未満" when $過去利用:過去利用状況(過去利用回数 < 2, 過去利用額計 < 10000) $今回利用:今回利用(ユーザーID == $過去利用.ユーザーID) then // modify($今回利用) {set 割引ランク("X")} $今回利用.set 割引ランク("X"); System.out.println($今回利用.get ユーザーID() + "の割引ランクは" + $今回利用.get 割引ランク() + "です"); end |
図16 ルールを動かすためのJavaクラス
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
package com.example.rhdm; import org.kie.api.KieServices; import org.kie.api.runtime.KieContainer; import org.kie.api.runtime.KieSession; public class DrlTest { public static final void main(String[] args) { try { KieServices ks = KieServices.Factory.get(); KieContainer kContainer = ks.getKieClasspathContainer(); // 実行対象ルールを指定 KieSession kSession = kContainer.newKieSession("ksession-rules"); // ファクトを生成 過去利用状況 fact1 = new 過去利用状況(); fact1.setユーザーID("A001"); fact1.set過去利用回数(1); fact1.set過去利用額計(5000); 今回利用 fact2 = new 今回利用(); fact2.setユーザーID("A001"); // ルールエンジンにファクトをインサート kSession.insert(fact1); kSession.insert(fact2); // ルール実行 kSession.fireAllRules(); } catch (Throwable t) { t.printStackTrace(); } } } |
図17 追加するルール
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
rule "利用回数2回未満、利用額1万以上" when $過去利用:過去利用状況(過去利用回数 < 2, 過去利用額計 >= 10000) $今回利用:今回利用(ユーザーID == $過去利用.ユーザーID) then $今回利用.set割引ランク("E"); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引ランクは"+ $今回利用.get割引ランク() + "です"); end rule "利用回数2回以上5回未満、利用額1万未満" when $過去利用:過去利用状況(過去利用回数 >= 2, 過去利用回数 < 5, 過去利用額計 < 10000) $今回利用:今回利用(ユーザーID == $過去利用.ユーザーID) then $今回利用.set割引ランク("E"); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引ランクは"+ $今回利用.get割引ランク() + "です"); end rule "利用回数2回以上5回未満、利用額1万以上" when $過去利用:過去利用状況(過去利用回数 >= 2, 過去利用回数 < 5, 過去利用額計 >= 10000) $今回利用:今回利用(ユーザーID == $過去利用.ユーザーID) then $今回利用.set割引ランク("D"); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引ランクは"+ $今回利用.get割引ランク() + "です"); end |
図18 さらに追加するルール
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
rule "割引ランクX割引率設定" when $今回利用:今回利用(割引ランク == "X") then $今回利用.set割引率(0); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引率は"+ $今回利用.get割引率() + "です"); end rule "割引ランクE割引率設定" when $今回利用:今回利用(割引ランク == "E") then $今回利用.set割引率(3); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引率は"+ $今回利用.get割引率() + "です"); end rule "割引ランクD割引率設定" when $今回利用:今回利用(割引ランク == "D") then $今回利用.set割引率(5); System.out.println($今回利用.getユーザーID() + "の割引率は"+ $今回利用.get割引率() + "です"); end |
筆者:米田 聡
シェルスクリプトマガジンでは、小型コンピュータボード「Raspberry Pi」(ラズパイ)は2種類の拡張ボードを制作しています。第12回は、最初に作成した「ラズパイ入門ボード」に「ロータリエンコーダ」を接続し、オーディオのボリュームのようなコントローラを実装します。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図5 ロータリエンコーダ用のクラスファイル(rotary.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
import RPi.GPIO as GPIO import time P_A = 21 P_B = 25 class rotaryenc(): def __init__(self, phase_a = P_A, phase_b = P_B): self.phase_a = phase_a self.phase_b = phase_b GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(phase_a, GPIO.IN) GPIO.setup(phase_b, GPIO.IN) GPIO.add_event_detect(phase_a, GPIO.RISING, callback=self.__changeStatus) self.__callback = None self.prev_forward_time = 0 self.prev_backward_time = 0 def __changeStatus(self, gpio): pa = GPIO.input(self.phase_a) pb = GPIO.input(self.phase_b) if pa == GPIO.LOW: # チャタリング等 return value = 0 current = time.time() if pb == GPIO.LOW: # 時計回り value = 1 if self.prev_forward_time != 0: if (current - self.prev_forward_time) < 0.1: # 100ms以内 value = 10 self.prev_forward_time = current self.prev_backward_time = 0 if pb == GPIO.HIGH: value = -1 if self.prev_backward_time != 0: if (current - self.prev_backward_time) < 0.1: # 100ms以内 value = -10 self.prev_forward_time = 0 self.prev_backward_time = current if value != 0 and self.__callback is not None: self.__callback(value) def registerCallback(self, c): self.__callback = c return def unregisterCallback(self): self.__callback = None def __del__(self): GPIO.cleanup() |
図6 テスト用のサンプルプログラム(test.py)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
from rotary import rotaryenc from EbOled import EbOled import time # OLED oled = EbOled() oled.begin() oled.clear() oled.display() value = 0 def callback(r): global value value += r oled.drawString('value=' + str(value)) oled.display() re = rotaryenc() re.registerCallback(callback) try: time.sleep(120) except KeyboardInterrupt: pass |
著者:髙田 知典
「NGINX」(エンジンエックス)は、人気の高いWebサーバーソフトウエ
アです。「NGINX Plus」は、オープンソース版のNGINXにさまざまな
機能拡張を施した商用版です。追加された拡張機能を利用すること
で、システムの可用性と堅牢性の向上や、運用の簡素化を実現できま
す。本特集では、NGINX Plusの機能や試用方法などを紹介します。
シェルスクリプトマガジン Vol.65は以下のリンク先でご購入できます。![]()
![]()
図2 アクティブヘルスチェックの設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
upstream my_upstream { zone my_upstream 64k; server server1.example.com slow_start=30s; server server2.example.com slow_start=30s; } server { location / { proxy_pass http://my_upstream; health_check interval=5s uri=/test.php match=statusok; } } match statusok { status 200; header Content-Type = text/html; body ~ "Server[0-9]+ is alive"; } |
図3 Sticky cookie の設定例
|
1 2 3 4 5 |
upstream my_upstream { server server1.example.com; server server2.example.com; sticky cookie srv_id expires=1h; } |
図4 Sticky route の設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
map $cookie_jsessionid $route_cookie { ~.+\.(?P<route>\w+)$ $route; } map $request_uri $route_uri { ~jsessionid=.+\.(?P<route>\w+)$ $route; } upstream backend { server backend1.example.com route=a; server backend2.example.com route=b; sticky route $route_cookie $route_uri; } |
図5 Sticky learnの設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
upstream backend { server backend1.example.com; server backend2.example.com; sticky learn create=$upstream_cookie_examplecookie lookup=$cookie_examplecookie zone=client_sessions:1m timeout=1h; } |
図6 DNS名をAレコード情報を使って解決する設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
resolver 10.0.0.2 valid=10s; upstream backends { zone backends 64k; server backends.example.com:8080 resolve; } server { location / { proxy_pass http://backends; } } |
図7 DNS名をSRVレコード情報を使って解決する設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
resolver 10.0.0.2 valid=10s; upstream backends { zone backends 64k; server backends.example.com service=_http._tcp resolve; } server { location / { proxy_pass http://backends; } } |
図9 コンテンツキャッシュのパージ設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
http { (略) proxy_cache_path /data/nginx/cache levels=1:2 keys_zone=mycache:10m purger=on; map $request_method $purge_method { PURGE 1; default 0; } server { listen 80; server_name www.example.com; location / { proxy_pass https://localhost:8002; proxy_cache mycache; proxy_cache_purge $purge_method; } } geo $purge_allowed { default 0; 10.0.0.1 1; 192.168.0.0/24 1; } map $request_method $purge_method { PURGE $purge_allowed; default 0; } } |
図15 nginx-sync.confの設定例
|
1 2 3 |
NODES="node2.example.com node3.example.com node4.example.com" CONFPATHS="/etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/conf.d" EXCLUDE="default.conf" |
図16 NGINX Plus APIの設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
http { (略) # Configuration of the server group upstream appservers { # 共有メモリーにサーバーグループ構成を保存するようにゾーンを設定 zone appservers 64k; server appserv1.example.com weight=5; server appserv2.example.com:8080 fail_timeout=5s; server reserve1.example.com:8080 backup; server reserve2.example.com:8080 backup; } server { location / { proxy_pass http://appservers; health_check; } location /api { # GET以外のメソッドをBasic認証で制限 limit_except GET { auth_basic "NGINX Plus API"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; } # APIを書き込みモードで動作させる api write=on; # アクセス元をローカルホストのみに制限 allow 127.0.0.1; deny all; } } } |
図18 stateファイルの設定を追加した例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
http { (略) # Configuration of the server group upstream appservers { zone appservers 64k; state /var/lib/nginx/state/appservers.conf; # server appserv1.example.com weight=5; # server appserv2.example.com:8080 fail_timeout=5s; # server reserve1.example.com:8080 backup; # server reserve2.example.com:8080 backup; } } |
図19 キーバリューストアの設定例
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
http { # キーバリューストアの定義 keyval_zone zone=blacklist:1M state=/tmp/blacklist.json; keyval $remote_addr $black_list zone=blacklist; server { listen 80; location / { root /usr/share/nginx/html; if ($black_list = 0) { return 403; } } location /api { # GET以外のメソッドをベーシック認証で制限 limit_except GET { auth_basic "NGINX Plus API"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; } # APIを書き込みモードで動作させる api write=on; #アクセス元をローカルホストのみに制限 allow 127.0.0.1; deny all; } } } |

004 レポート WebブラウザMicrosoft Edgeの新版
005 レポート 仮想マシン構築・運用ソフト「Multipass」
006 NEWS FLASH
008 特集1 知っておきたいDebian/やまねひでき
026 特集2 NGINX Plus徹底解説/髙田知典 コード掲載
042 特別企画 詳説 OpenPOWER/OpenCAPI/河井裕
050 ラズパイ入門ボードで学ぶ 電子回路の制御/米田聡 コード掲載
054 レッドハットのプロダクト/松田絵里奈 コード掲載
064 姐のNOGYO
066 漢のUNIX/後藤大地
072 円滑コミュニケーションが世界を救う!/濱口誠一
074 バーティカルバーの極意/飯尾淳 コード掲載
080 中小企業手作りIT化奮戦記/菅雄一
084 やっつける/桑原滝弥、イケヤシロウ
086 Webアプリの正しい作り方/しょっさん
096 法林浩之のFIGHTING TALKS/法林浩之
098 香川大学SLPからお届け!/重松亜夢 コード掲載
106 MySQL Shellを使おう/梶山隆輔
114 シェルスクリプトの書き方入門/大津真 コード掲載
120 Techパズル/gori.sh
122 コラム「社訓」/シェル魔人
「自由なソフトウエアによるOSを作り上げたい」という志を共にするボランティアの開発者の協力によって開発が続いているLinuxディストリビューションがあります。それが「Debian」(デビアン)です。特集1では、Debianの概要、最新の安定版であるDebian 10の特徴やインストール方法、導入時や使いこなしの注意点を解説します。Red Hat Enterprise Linux(RHEL)やUbuntuに引けを取らない、Debainに注目してみてください。
特集2では、オープンソースのWebサーバーソフトウエアとして人気が高い「NGINX」の商用版「NGINX Plus」について解説します。オープンソース版にはない機能により、システムの可用性と堅牢性の向上や、運用の簡素化を実現できます。試用も可能なので、特集2を読んで実際に試してみてください。
ソフトウエアだけでなく、ハードウエアのオープン(オープンソース)化も進んでいます。特集3では、米IBM社が開発した、POWERプロセッサに関連する技術をオープン化にするコミュニティ「OpenPOWER」と、プロセッサ拡張バス標準「CAPI」のオープンな仕様である「OpenCAPI」について分かりやすく紹介します。
このほか、二つの連載を開始しました。一つは、オープンソースソフトウエアを基に開発されている米Red Hat製品を紹介する「レッドハットのプロダクト」。もう一つは、初めての人や初心者にもシェルスクリプトの書き方を紹介する「シェルスクリプトの書き方入門」です。
今回も読み応え十分のシェルスクリプトマガジン Vol.65。お見逃しなく!
※読者アンケートはこちら